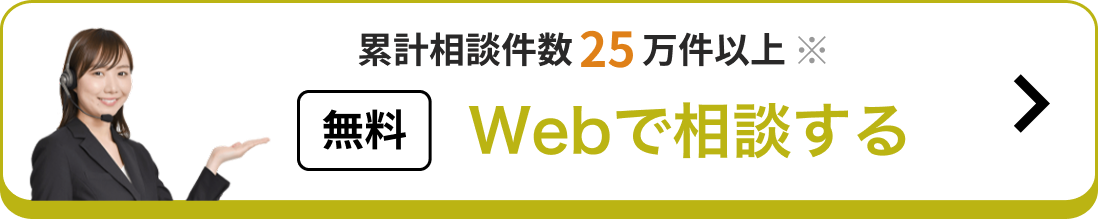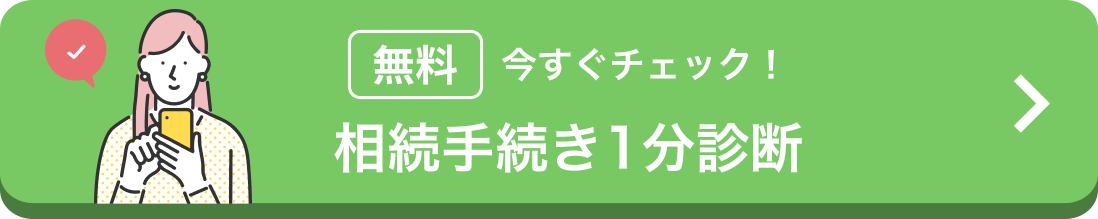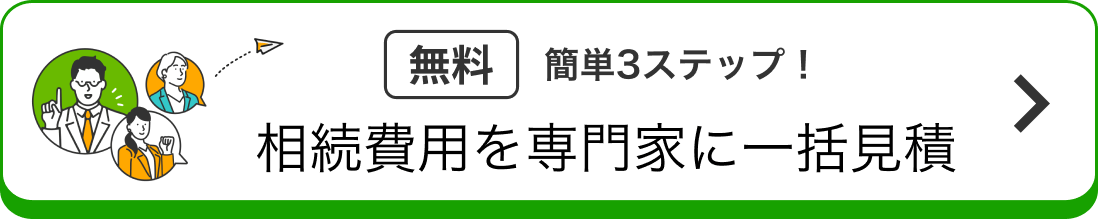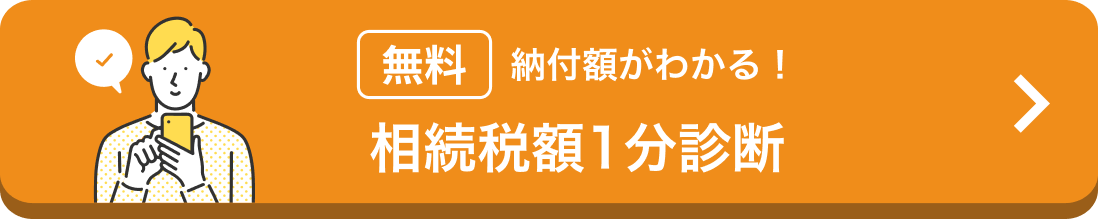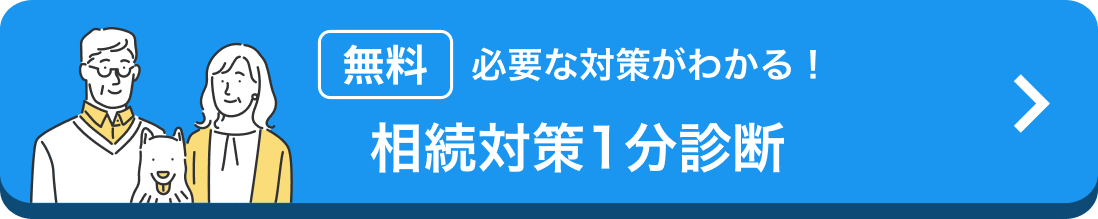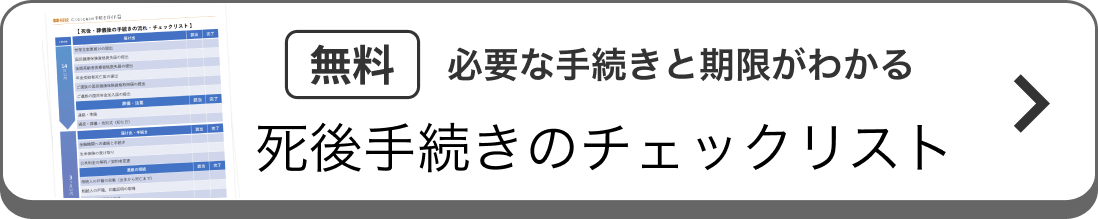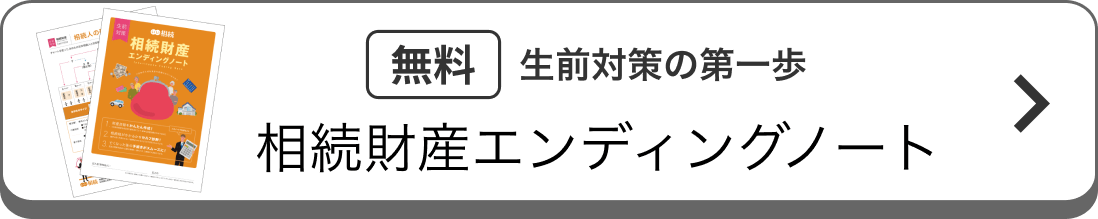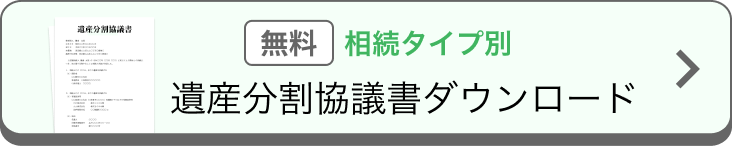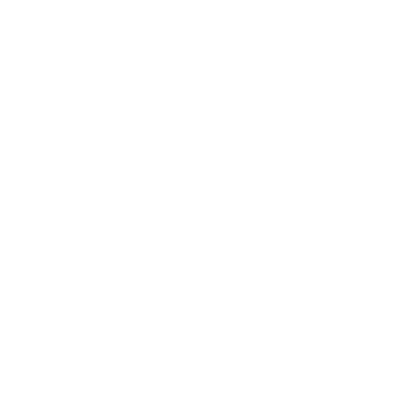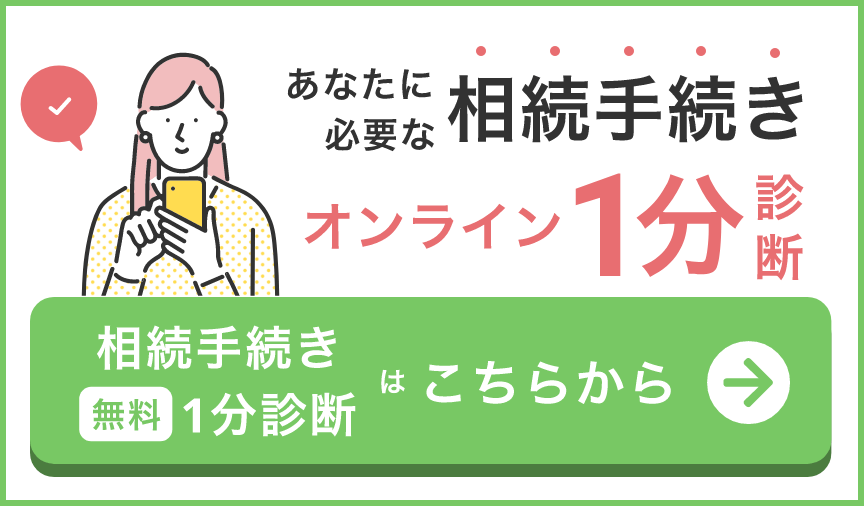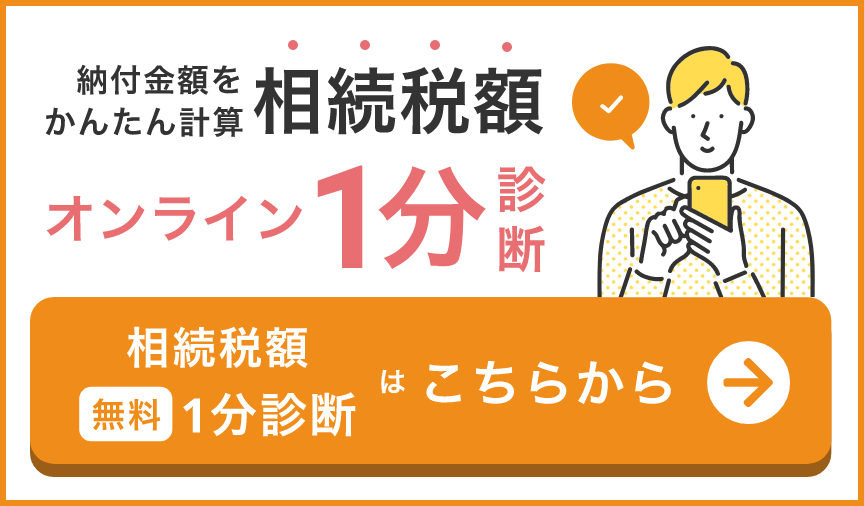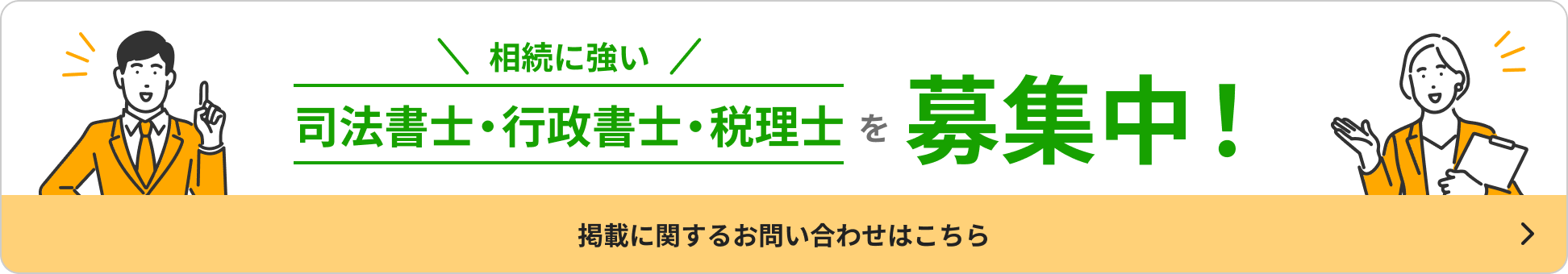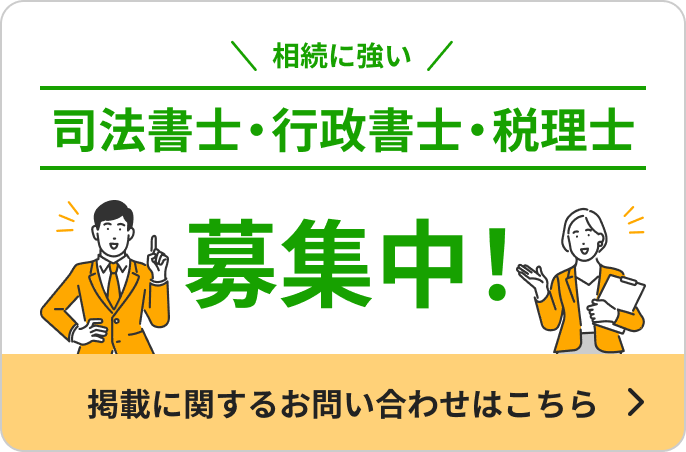多すぎる弔慰金は相続税の課税対象となることも!?弔慰金と死亡退職金の違い

この記事はこんな方におすすめ:
企業からもらった弔慰金にかかる相続税について知りたい方
- 一定額までの弔慰金には相続税がかからない
- 相続税が非課税となる弔慰金の額は、死亡時の給与と死亡理由によって決まる
- 弔慰金と死亡退職金の違いは?両方受け取ったときの相続税計算は要注意
企業に勤務していた方が亡くなられたとき、企業から弔慰金等(花輪代、葬祭料等を含みます)が支給されることがあります。弔慰金には、通常税金はかかりませんが、一定額を超えると相続税の課税対象となる場合があります。
この記事では、弔慰金とはどのようなお金で死亡退職金とはどう違うのか、また、どのような場合に相続税の課税対象となるのかについて紹介しています。


弔慰金とは?
弔慰金とは、亡くなった人を弔い、遺族を慰めるという趣旨で贈られるお金です。 弔慰金には、故人が働いていた企業から支給されるものと、市町村等から災害等で亡くなった人に支払われるもの、法律等の規定により支払われるものがありますが、ここでは企業から支給される弔慰金について説明します。
企業から支給される弔慰金
弔慰金は 企業の福利厚生の一環として支給されるもので、企業によっては従業員本人だけでなく家族が亡くなった場合にも支給されます。2017年に実施された調査によると、約86%の企業で「慶弔見舞金制度」が導入されています。
出典:独立行政法人労働政策研究・研修機構「企業における福利厚生施策の実態に関する調査」
弔慰金の支給額
弔慰金の支給額は、企業の「慶弔見舞金規程」等で規定されています。 全従業員一律の定額支給としている企業もありますが 、勤続年数等に応じた額を 支給する企業が多いようです 。また、業務上の死亡か否かによっても金額が変わってきます。業務上の死亡の方が支給額は大きくなることが多いです。弔慰金は基本的に非課税ですが、一定額を超えると相続税の課税対象となってしまいます。遺族の生活を支えるために支給されるものですので、相続税のかからない範囲の金額で支払われることが多いです。
死亡退職金と弔慰金の違い
死亡退職金は、従業員がもともと受け取るはずだった退職金を遺族の生活を支えるために支給するものです。弔慰金も死亡退職金も企業から遺族に支払われるお金という意味では同じですが、税金の取り扱いが異なります。
死亡退職金
死亡退職金は、故人の死亡によって発生したものを遺族が受け取るため、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
対象となるのは、被相続人(亡くなった人)の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金です。3年経過後に支給が確定したものは、受け取った遺族の一時所得として所得税の課税対象となります。
弔慰金
弔慰金は基本的に相続税の課税対象にはなりません。相続税の計算では、原則として、相続等により取得した財産すべてが課税対象となりますが、社会政策的見地や国民感情等から相続税の対象とすることが適当でないものについては「非課税財産」として相続財産から除くこととされています。
弔慰金(葬祭料、花輪代などの名目で贈られたものも同様)は非課税財産にあたり、一定の金額までは相続税がかかりません。また、社会通念上相当と認められるものは、所得税・贈与税もかかりません。


弔慰金には相続税が課されるのか?
上述のとおり、弔慰金は基本的に相続税の課税対象とはなりません。
しかし、弔慰金として取り扱われる金額には上限 が定められており、それを超える部分は死亡退職金として取り扱われます。そのため超過分についてはみなし相続財産として相続税の課税対象となります。なお、被相続人の雇用主などから弔慰金などの名目で受け取った金銭などのうち、実質上死亡退職金等に該当すると認められる部分は相続税の課税対象になります。

では、相続税が非課税となる弔慰金の額と弔慰金を受け取った場合の相続税の計算の仕方について確認しましょう。
相続税が非課税となる弔慰金の額
被相続人の死亡が業務上の死亡であるとき:死亡時の普通給与×36ヵ月年分
被相続人の死亡が業務上の死亡でないとき:死亡時の普通給与×6ヵ月分
業務上の死亡の場合、弔慰金には遺族への補償の意味も込められるため、金額が大きくなるケースが多いです。
業務上の死亡に該当するのは 、
・業務遂行中の事故
・出張中に起きた事故
・職業病
・通勤途中の災害
などです。
(例)被相続人の死亡時の給与が月額40万円だった場合
非課税となる弔慰金の額は
業務上の死亡であるとき:40万円×36ヵ月=1,440万円
業務上の死亡でないとき:40万円×6ヵ月=240万円
業務上の死亡か否かにより、非課税となる金額に大きな差が出ます。
弔慰金が非課税となる金額を超える場合の相続税の計算
弔慰金が非課税となる額を超える場合、超過分は死亡退職金とみなされます。
死亡退職金(退職手当金、功労金など名称は問わない)はみなし相続財産として相続税の課税対象となりますが、死亡退職金には非課税枠があります。死亡退職金の非課税枠は「法定相続人1人あたり500万円」です。
法定相続人が3人いる場合の非課税枠は、500万円×3人=1,500万円です。したがって、死亡退職金として受け取る金額が1,500万円を超えるとき、その部分が課税対象となります。
<非課税枠の計算方法と課税対象金額>
法定相続人の数には、相続放棄した人も含めますが、実際に死亡退職金を受け取る人が相続放棄した人である場合、非課税枠の適用を受けることはできません。
(課税対象金額 計算例)
死亡退職金:2,000万円
法定相続人:長男、長女、次女の3名 そのうち次女は相続放棄
非課税枠:500万円×法定相続人の数=500万円×3人(長男・長女・次女)=1,500万円
課税対象額
長男または長女が死亡退職金を受け取る場合:2,000万円-1,500万円(非課税枠適用)=500万円
次女が死亡退職金を受け取る場合:2,000万円-0(非課税枠の適用なし)=2,000万円
また、相続人以外が受け取る場合、非課税枠は適用されません。
退職金規程などで、「本人死亡のときの退職金を受ける遺族の範囲及び順位は、労働基準法施行規則の第42条から第45条までに定めるところによる。」と規定している企業が多くあります。この場合、死亡退職金を受け取る順位は以下のとおりです。
1.配偶者(事実婚含む)
2.生計を一にしていた、子、父母、孫、祖父母の順
3.上記2に該当しない子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順(兄弟姉妹については生計を一にするものを先にする)
第1順位は事実婚を含む配偶者となり、民法に定める法定相続人の順位とは異なります。また、このように受取人が指定されている場合の死亡退職金は受取人固有の財産となり、遺産分割協議の対象外となります。


弔慰金と死亡退職金を両方受け取った場合
勤務先の規程にもよりますが、故人が従業員本人であれば弔慰金と死亡退職金の両方を受け取ることがあります。
この場合、弔慰金と死亡退職金は課税対象額の計算の仕方が異なるので、別々に処理する必要があります。これらを一緒にして処理してしまうと、弔慰金がすべて死亡退職金として計算されるので、相続税の課税対象となる金額が増えてしまいます。
弔慰金と死亡退職金が両方支給された場合は、最初に非課税となる弔慰金の額 を確認します。以下の計算例で具体的な方法をご説明します。
計算例
被相続人:サラリーマンの夫。死亡時の普通給与は月40万円。業務以外の原因で死亡。
相続人:妻と子ども2人(計3人)。
相続財産:持ち家と預金で6,000万円。死亡退職金1,500万円。
弔慰金:300万円。
まず、弔慰金から確認しましょう。
①非課税となる弔慰金の額(業務以外の原因):240万円(給与の6ヵ月分相当額)
②弔慰金のうち、死亡退職金に算入される額:60万円(弔慰金300万円-①)
③死亡退職金として取り扱われる金額:1,560万円(死亡退職金1,500万円+③)
④死亡退職金の非課税枠:1,500万円(500万円×3人)
⑤相続税の課税対象となる金額:60万円(③‐④)
弔慰金を死亡退職金と一緒に処理した場合
死亡退職金+弔慰金 :1,800万円
非課税枠:1,500万円 (500万円×3人)
相続税の課税対象額となる金額:300万円
このように、弔慰金と死亡退職金を別々で処理したときよりも課税対象となる額が大きくなってしまうため、必ず分けて処理しましょう。
(ご参考)退職金とみなされない弔慰金
以下の法律等の規定により遺族が受け取る弔慰金等は、死亡退職金等に該当しないものとされていて、税金はかかりません。
・労働者災害補償保険法に掲げる遺族補償給付及び葬祭料並びに遺族給付及び葬祭給付
・労働基準法に規定する遺族補償及び葬祭料
・健康保険法に規定する埋葬料
などです。(相続税法基本通達3-23)
まとめ
今回は故人が勤めていた企業から支払われる弔慰金や死亡退職金について解説してきました。どちらも遺族の生活を支えるために支払われるものですが、弔慰金は基本的に非課税で死亡退職金は相続税の対象となる点が異なります。万が一の場合に備えて、弔慰金や死亡退職金の有無・金額を勤務先の規程等で確認しておきましょう。
弔慰金を受け取ったときや、弔慰金と死亡退職金の両方を受け取り処理の仕方に不安がある方は、相続税の計算を間違えないためにもプロに相談することをおすすめします。


▼実際に「いい相続」を利用して、税理士に相続税申告を依頼した方のインタビューはこちら
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。