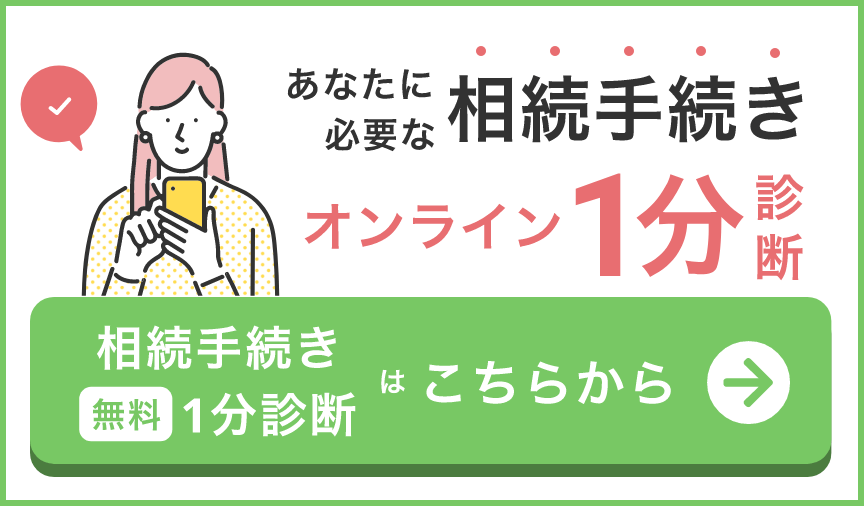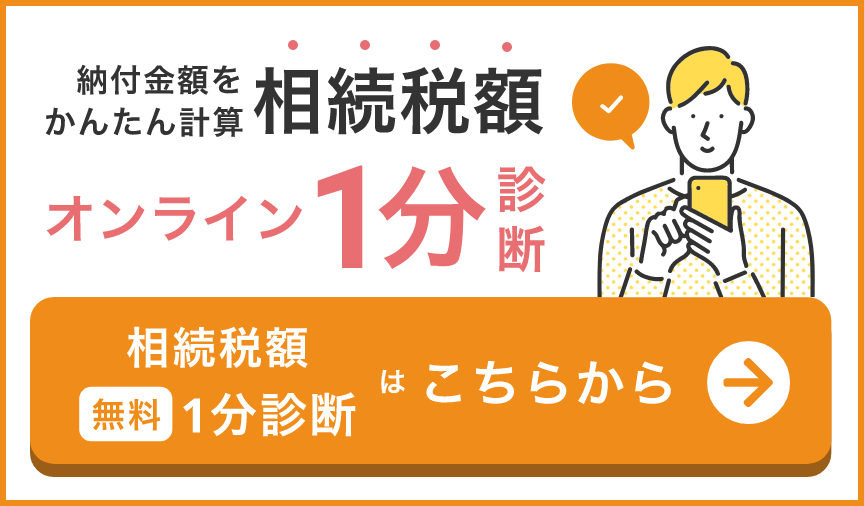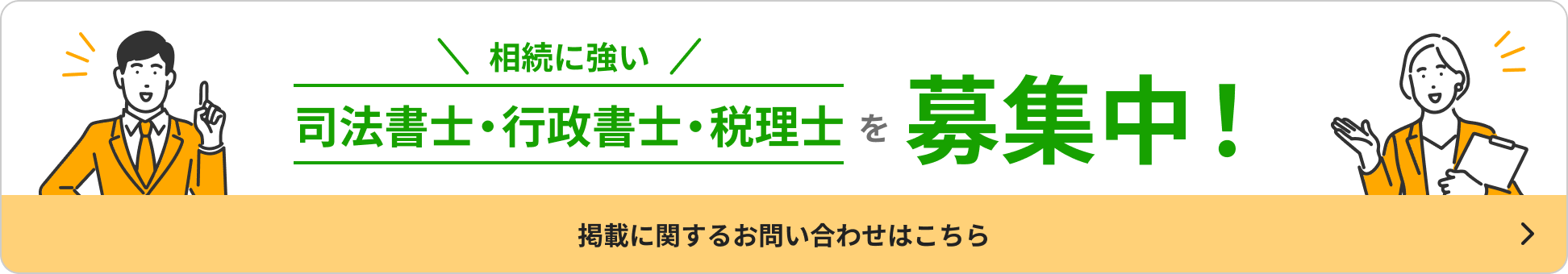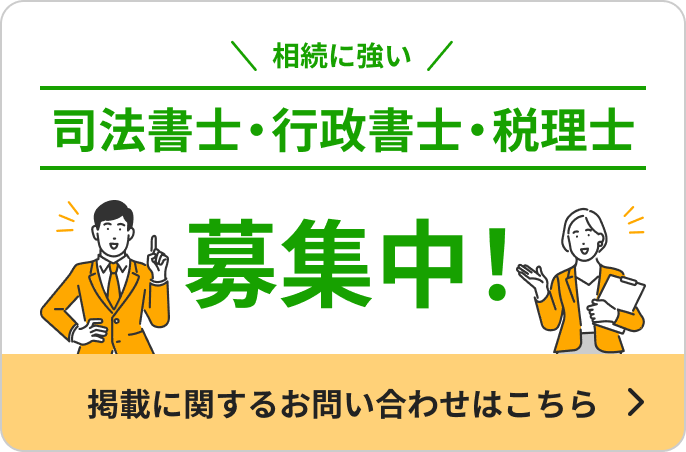遺言無効確認訴訟(遺言無効確認の訴え)とは?納得いかない遺言書を無効にする方法

故人の遺言書を見たら「思っていた内容と違う」と感じることもあるでしょう。事前に聞いていた内容と異なる場合、「こんな遺言書を作成するはずがない」と疑う場合もあると思います。
偽造された遺言書や、認知症等により判断能力が低下により言いくるめられ作成させられた遺言書、詐欺や強迫、勘違いによって作成された遺言書、その他の要件を満たしていない遺言書は基本的には無効です。
このような、遺言書があることによって遺産を取得できない場合は、「遺言無効確認訴訟」(「遺言無効確認の訴え」とも言います)の提起によって、その遺言が無効であるか確認することができます。この記事では、遺言無効確認訴訟の提起の方法や注意点について説明します。


遺言無効確認訴訟とは?

遺言無効確認訴訟とは、遺言が無効であることを確認する裁判手続きです。
遺言無効確認訴訟で勝訴して遺言が無効であることが確認されると、その遺言を執行することはできなくなり、既に執行した遺産については請求に基づき返還しなければならなくなります。そして、他に有効な遺言がない場合、原則として法定相続分に基づき遺産分割をすることになります。
遺言書の無効性を認めてもらう必要があり、訴訟に至るまでに一定の時間と費用がかかります。


主な遺言無効原因
遺言無効確認訴訟で主張される主な無効原因として、以下が挙げられます。
- 遺言能力の欠如
- 公序良俗違反
- 錯誤、詐欺、脅迫による遺言の取消し
- 方式違背
- 共同遺言
- 証人欠格
- 遺言の「撤回の撤回」
以下、それぞれについて説明します。
遺言能力の欠如
認知症等によって遺言するための判断能力(遺言能力)がない時に作成された遺言書は無効です。既に遺言を残す能力がない可能性があるとして、他の相続人とトラブルになる場合があります。
公序良俗違反
「公序良俗」に反する行為は無効となります。例えば、愛人に全財産を遺贈するといった遺言は、公序良俗に反して無効となる可能性があります。
実際に遺言の有効・無効を判断するに当たっては、次の点が考慮されています。
- 遺言者と愛人との生活状況
- 遺言の前後による生活状況の変化
- 夫婦の生活実態
- 妻及び子の生活状況
- 妻及び子の生活基盤に対する遺言者の配慮(生前贈与又は遺贈の有無・内容)等
錯誤、詐欺、脅迫による遺言の取消し
錯誤(勘違い)、詐欺、脅迫に基づく遺言は相続人によって取消すことができます。ただし、どのような錯誤でも取消しができるわけではありません。
ただし、遺言者本人が亡くなっている場合、第三者がこの事実を立証することは難しいでしょう。
方式違背
遺言書の作成には方式があり、これに背く遺言は無効となります。日付や押印がなかったり、遺言書がパソコンで作成されていた場合などは無効となります。ただし、これで無効となるのは明らかなので、訴訟となることは少ないでしょう。
共同遺言
夫婦が同じ用紙に遺言を書いていたなど、2人以上で同じ遺言書で遺言をすると無効となります。
証人欠格
公正証書遺言または秘密証書遺言で、証人の数が不足していた場合(2人以上必要)や、証人になることができないはずの人が証人になっていた場合は、無効となります。
証人になることができない人とは、次のいずれかに該当する人のことです。
- 未成年者
- 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
- 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
遺言の「撤回の撤回」
撤回を撤回された遺言は、基本的には無効となります。
遺言は撤回されると無効になりますが、その撤回をさらに撤回しても、遺言の効力は復活しません。
ただし、この撤回が詐欺又は強迫による場合は、例外的に有効となります。


遺言無効確認手続きの流れ
遺言の無効について当事者間で争いがある場合、まずは当事者間の話し合いをします。しかし話し合いで決着しない場合は、裁判所に遺言無効確認調停か遺言無効確認訴訟の申立てをします。
調停の場合は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または当事者の合意で定めた家庭裁判所に、訴訟の場合は亡くなった人の最後の住所地もしくは被告の住所地を管轄する地方裁判所または当事者の合意で定めた地方裁判所に申立てをします。
調停は、家庭裁判所の調停委員会(裁判官1名と調停委員2名で構成)が、当事者に対して解決のための助言や説得をして、合意を目指して話合いを進める手続きです。
原則としては訴訟の前に調停の申立てをしなければならないことになっていますが(「調停前置主義」といいます)、遺言が有効か無効かを争っている場合、お互い歩み寄って合意に至るということが難しく、あまり調停向きではありません。
したがって、遺言の無効が争点のケースでは、調停を経ずに、訴訟を提起することが多いです。ただし、訴訟を提起しても、裁判官が調停による解決の見込みがあると判断した場合は、調停に付されます。
訴訟では、当事者による事実関係の主張と、その主張を裏付ける証拠の取り調べというかたちで審理が進みます。
提訴から判決までの期間は、事案によってそれぞれですが1年くらいはかかります。なお、この申し立てに時効はありません。亡くなってから何年経っても申し立て可能です。
なお、遺言無効の主張を認めてもらうことは大変難しいので、まずは専門家に相談することをお勧めします。
この記事のポイントとまとめ
以上、遺言無効確認訴訟について解説しました。最後にこの記事のポイントをまとめます。
- 遺言無効確認訴訟とは遺言が無効であることを確認する裁判手続き
- 遺言能力の欠如や共同遺言などの遺言無効となる要因を探す必要がある
- 遺言無効確認訴訟は終了までに1年程度かかる
遺言無効確認訴訟を一般の人がおこなうのは大変です。まずは専門家に相談することをおすすめします。他に終わっていない相続手続きがあれば、あわせて依頼しても良いでしょう。
いい相続ではお近くの専門家との無料相談をご案内することが可能ですので、遺言書の無効でお困りの方はお気軽にご相談ください。


▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きや遺言書の作成を依頼した方のインタビューはこちら
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。





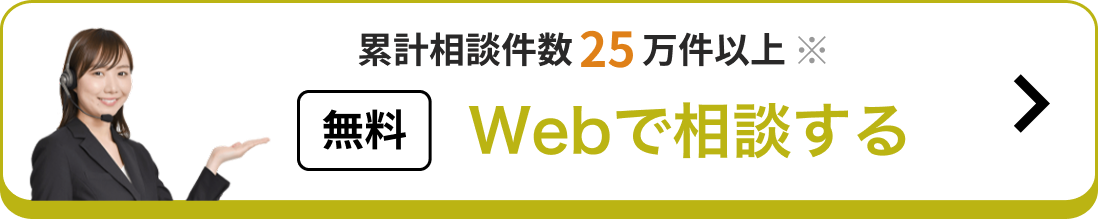
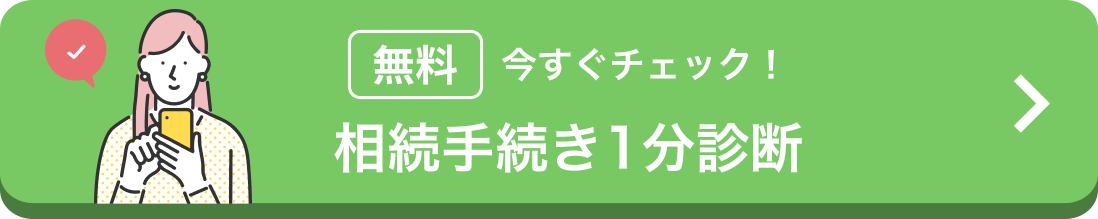
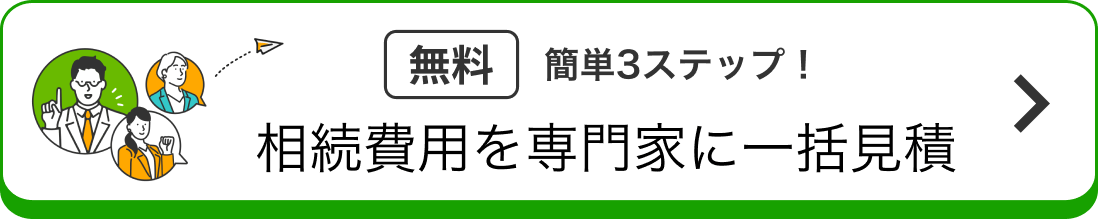
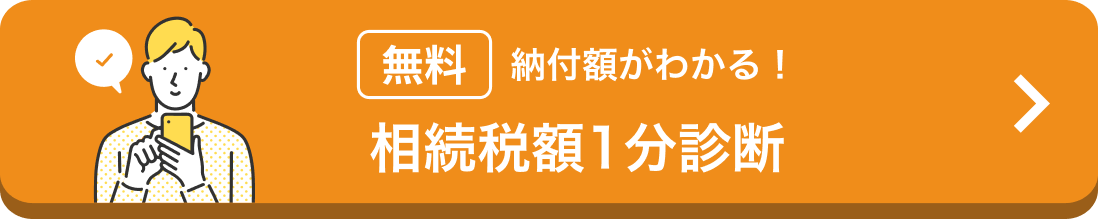
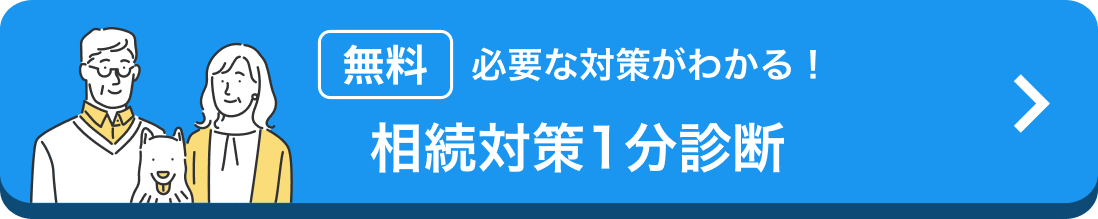
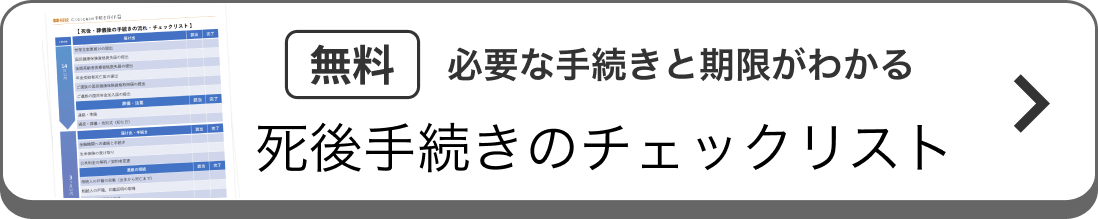
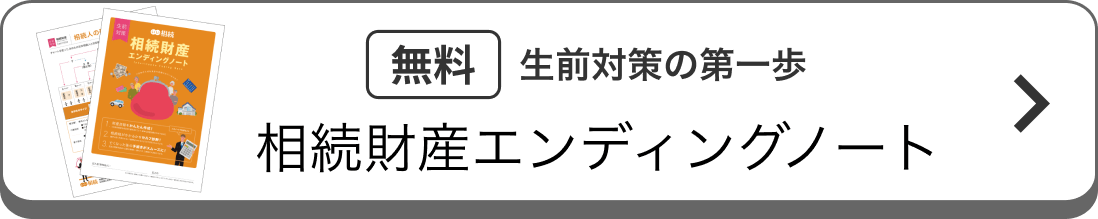
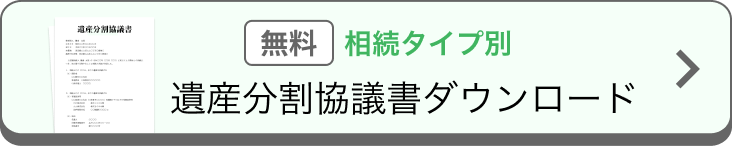
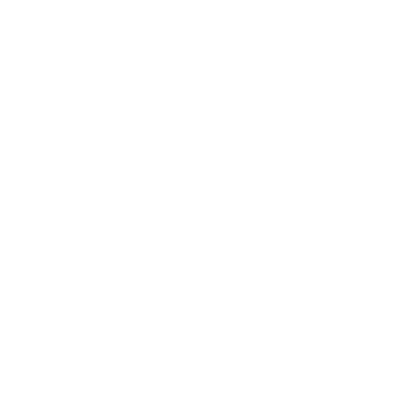
 Webで無料相談はこちら
Webで無料相談はこちら