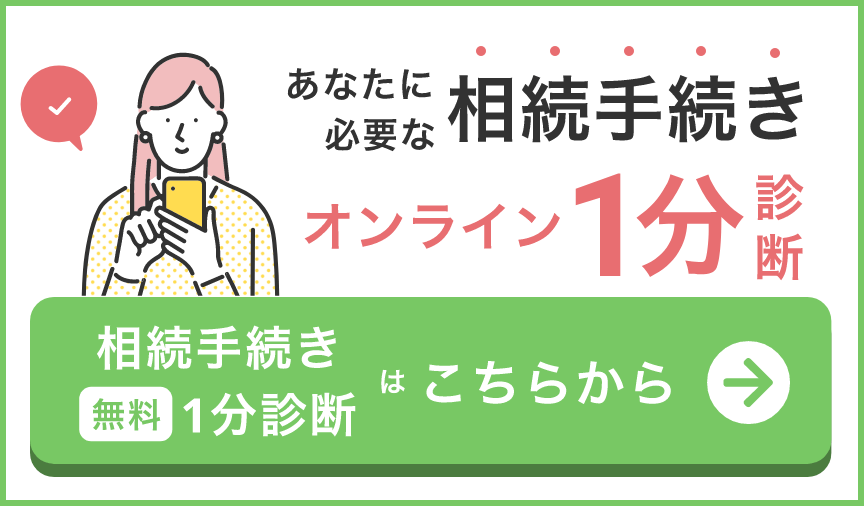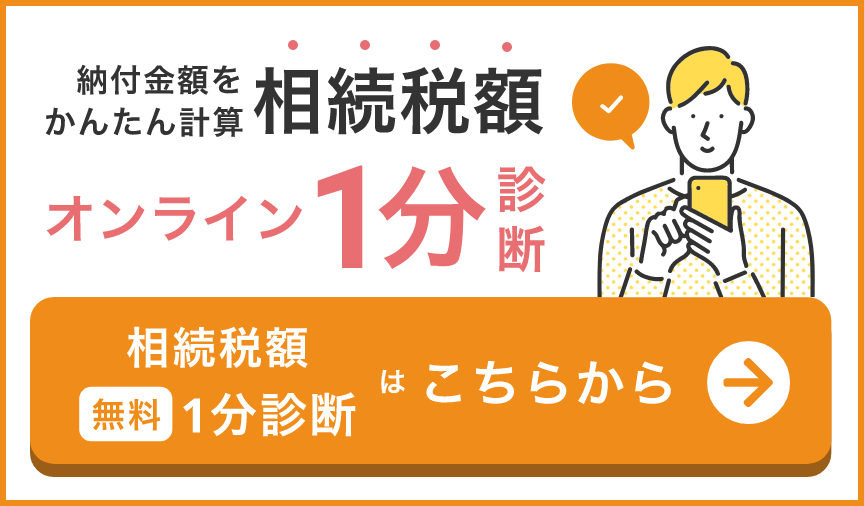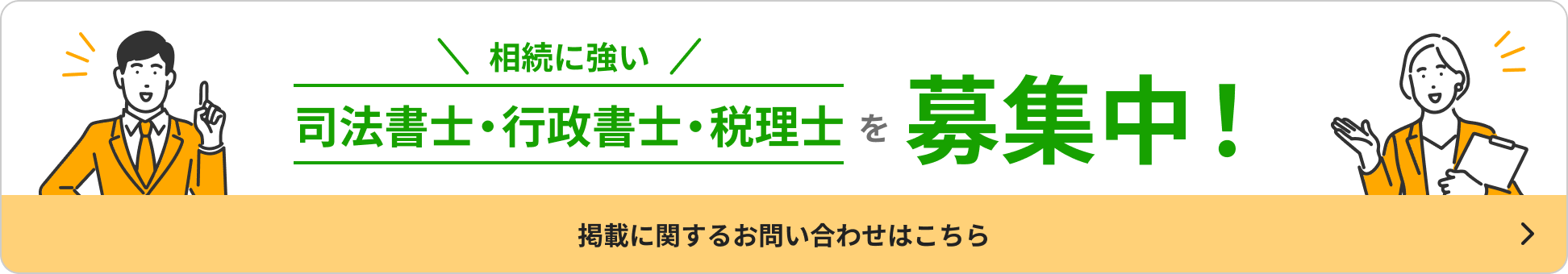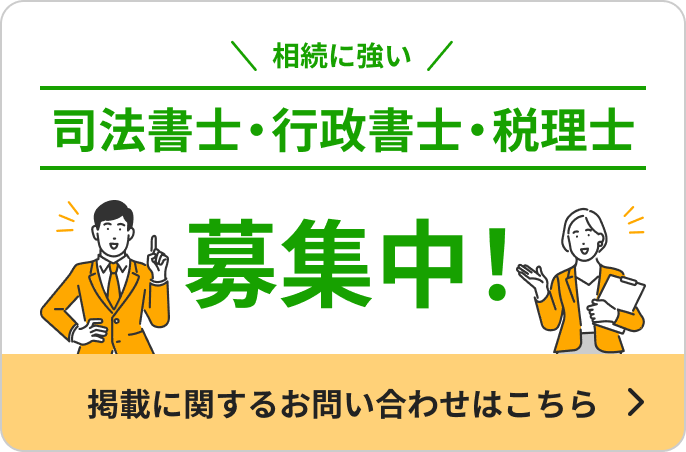準確定申告と確定申告との違い、必要になる人の要件や注意点をわかりやすく解説!

亡くなった方の所得については相続人が代わりに準確定申告おこなうことで所得税の納税や還付をします。
では、準確定申告と確定申告は何が違うのでしょうか。だれでもおこなわなくてはいけないのでしょうか。
この記事では準確定申告と確定申告の違い、準確定申告をおこなわなくてはいけない要件や方法について説明します。是非参考にしてください。


目次 [隠す]
「準確定申告」と「確定申告」の違い
準確定申告と確定申告の大きな違いは所得税の申告を相続人がおこなうのか、本人がおこなうのか、という部分でしょう。
また、申告期限についても準確定申告は被相続人が亡くなってから4カ月以内であることに対し、確定申告は全国一斉に決められている(翌年2月16日から3月15日)ことなどがあげられます。
準確定申告
死亡した人の場合は、相続人や包括受遺者(遺贈を受けた方)が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内に申告と納税をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。
確定申告
生きている方の所得税の申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告書の提出を行います。これが「確定申告」と言われるものになります。
年末調整
会社勤めの方などは12月に給与内で所得税の納税額を調整します。これを年末調整といい、対象の方は確定申告をおこなう必要がありません。
ただし、給与が2000万円以上であったり、副収入があるなど、一定の条件にあてはまると会社で年末調整の対応ができない方もいます。そのような場合は個人で確定申告をおこないます。
▼めんどうな相続手続きは専門家に依頼しましょう▼
「準確定申告」が必要となる人は?
亡くなられたすべての方が、準確定申告が必要となるわけではありません。生前に一定以上の所得があり、確定申告の必要がある方は必要となります。国税庁では下記の4分類に該当される方について確定申告の対象とされております。
①給与所得がある方
次の1~3の計算において残額があり、さらに(1)から(6)のいずれかに該当する場合。
- 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
- 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
- 所得税額から、配当控除額と年末調整の際に控除を受けた(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を差し引きます。
- (1) 給与の収入金額が2,000万円を超える
- (2) 給与を1か所から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円を超える
- (3) 給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える
※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く。)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)の合計額が20万円以下の方は、申告は不要です。 - (4) 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた
- (5) 給与について、災害減免法により所得税等の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた
- (6) 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税等を源泉徴収されないこととなっている
大部分の方は、年末調整により所得税等が精算されるため、準確定申告は不要です。
年の途中で行う年末調整
年度中に死亡した従業員がいる場合、会社は最後の給料を支払う際に年末調整を行い源泉徴収票を発行します。そうしないと相続財産の正確な金額が算出できないからです。
ただし、退職金は本人の所得ではないので年末調整の対象にはなりませんので、混同しないようにしましょう。
②公的年金等に係る雑所得のみの方
公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある場合。 ※公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。
③退職所得がある方
外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある場合。 ※退職金などの支払者に『退職所得の受給に関する申告書』を提出した場合、一般的に、退職所得に係る所得税等は源泉徴収により課税が済むことになりますので、退職所得の申告は不要になります。
なお、退職所得以外の所得がある方は、1または4を参照してください。
④1から3以外の方
次の計算において残額がある場合。
- 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む。)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求めます。
- 課税される所得金額に所得税の税率を乗じて、所得税額を求めます。
- 所得税額から、配当控除額を差し引きます。
※公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となる場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときには、所得税等の確定申告は必要ありません。
なお、住民税については各自治体の「市区町村からのお知らせ」等を参照してください。
上場株式等に係る譲渡損失と配当所得等との損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けようとする方などは、1から4に当てはまらない方であっても確定申告が必要です(国税庁 確定申告が必要な方より)
▼相続手続きは一人で悩まず専門家に相談しましょう▼


「準確定申告」するとどんなメリットがある?しないと罰則は?
高額の医療費の支払いがあったり、給与や年金収入の源泉徴収が行われている場合など、準確定申告をすることで還付金を受け取れることがあります。
同時に、準確定申告の義務がありながら無申告であったり、申告期限に遅れてしまった場合、本来納める税金のほかに無申告加算税や延滞税等が課され、併せて刑事罰も科されるおそれがあります。準確定申告が必要な場合は必ず行うようにしましょう。
▼今すぐ診断してみましょう▼


「準確定申告」の注意点

①期限と期間
本来確定申告をしなければならない人が、1月1日から確定申告期限の3月15日までの間に確定申告書を提出することができずに死亡した場合は、確定申告を行う予定であった前年分と、亡くなってしまった本年分の2年分の申告が必要となります。申告期限はともに相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヵ月以内となります。
②相続人等が複数人の場合
相続人等が2人以上いる場合、各相続人等が連署により準確定申告書を提出することになります。。
他の相続人等の氏名を付記して各人が別々に提出することもできますが、この場合、当該申告書を提出した相続人等は、他の相続人等に申告した内容を通知しなければならないことになっています。
③所得控除の適用
控除対象となるのは死亡日までに支払った金額になり、国税庁にてそれぞれ下記のとおり案内されております。
- 医療費控除の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った医療費であり、死亡後に相続人等が支払ったものを被相続人の準確定申告において医療費控除の対象に含めることはできません。
- 社会保険料、生命保険料、地震保険料控除等の対象となるのは、死亡の日までに被相続人が支払った保険料等の額です。
- 配偶者控除や扶養控除等の適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。なお、配偶者控除額、配偶者特別控除額及び扶養控除額の月割計算等は行いません。
▼めんどうな相続手続きは専門家に依頼しましょう▼
「準確定申告」の提出先
準確定申告の提出先は亡くなられた方の住所地の税務署となります。以前、準確定申告はe-taxの利用ができなかったため、管轄税務署の窓口にいくか、郵送での提出のみでした
令和2年分以降の所得税及び復興特別所得税の準確定申告についても、利便性向上のためe-Taxでの電子申告に対応となりました。(※令和元年分以前については、電子申告できません。)。
郵送での提出の際は、控えの返送に必要な切手を貼り付け済みの封筒を同封しましょう。管轄税務署の場所を調べたい場合は、国税庁ホームページの「税務署の所在地などを知りたい方」のページより、郵便番号にて検索が行えます。
▼どの程度相続税がかかるか計算してみましょう▼


「準確定申告」の提出書類

準確定申告の際に必要な書類は下記のとおりとなります。
- 確定申告書
- 確定申告書付表
- 納付書(納付する税額がある場合)
- マイナンバーカード(マイカードがない場合は番号確認書類と身元確認書類)
- 源泉徴収票や控除に関する書類
- 委任状(還付金を代表相続人が受け取る場合)
確定申告書、確定申告書付表、委任状の書式は国税庁ホームページよりダウンロードできます。
「準確定申告」のマイナンバーの取り扱い
マイナンバーはマイナンバー法にて、収集、利用、保管、提供が制限されております。相続人等が複数人の場合、同じ書類の上に複数人の方のマイナンバーを記入することがあります。その場合の取り扱いの説明として、一人目の相続人がマイナンバーを記載した準確定申告の書類を二人目以降の相続人に渡す行為について、国税局は下記のように記しています。
所得税準確定申告書の付表や消費税申告書の付表6(死亡した事業者の消費税及び地方消費税の確定申告明細書)、相続税の申告書や贈与税の申告書付表の作成に当たり、複数の相続人がそれぞれのマイナンバー(個人番号)を記載するために、一の相続人が当該付表等にマイナンバー(個人番号)を記載してその他の相続人に渡す行為は、番号法上の特定個人情報の提供には該当しません。
マイナンバーを記載した申告書などを相続人等の間で引き渡す行為は、特定個人情報の提供はあたらないと案内されていると同時にこのケースにおいて、一の相続人のマイナンバー(個人番号)が記載された当該付表等を受け取ったその他の相続人は、番号法の規定により、そのマイナンバー(個人番号)を書き写したり、コピーを取る等を行うことはできませんので、付表等の控えを保管する場合は、記載されたマイナンバー(個人番号)をマスキングするなどの対応をお願いします。
上記のように、他の相続人のマイナンバーが記載された状態での書類を保管することのないように注意してください。
▼あなたに必要な相続手続き、ポチポチ選択するだけで診断できます!▼


準確定申告でよくある質問や疑問
相続人の中に相続放棄をした人がいる場合は?
民法の規定により、相続放棄者は始めから相続人ではなかったものとみなされます。そのため確定申告書付表にも記されておりますが、準確定申告時に相続放棄をされた方の記載やマイナンバー等は必要ありません。
また準確定申告は相続人等が行うものとされているため、相続放棄を検討されている場合は、準確定申告をすることによって相続人としての意思表示を示したとして、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるので注意してください。
「準確定申告」による還付金はだれのもの?
準確定申告によって受け取る還付金は相続財産となります。そのため相続税の申告が必要な方の場合は相続税の課税対象となります。
▼相続手続きは一人で悩まず専門家に相談しましょう▼亡くなった方の確定申告の情報がわからない
亡くなられた方の前年の申告内容等を参考に準確定申告を行いたい場合、一定の手続きを得た上で税務署で閲覧することが可能です。そのような場合は早めに管轄の税務署に早めに相談しましょう。
準確定申告は自分でしたほうがいい?
相続人等の中に詳しい方がいれば、お願いすることも可能だと思います。
しかし、書類の作成や収集等の負担が特定の相続人等にかかるってしまうこと、亡くなったことを知ってからの4ヵ月以内期間の制限、場合によってはその後相続税の申告が発生することなどを踏まえると、税理士に相談した方がスムーズでしょう。
▼あなたに必要な相続手続き1分で診断できます。▼

まとめ
相続が発生した場合、時間的制約がある手続きがいくつかあります。準確定申告はその中の代表的なもの一つでしょう。
身近な方が亡くなられて心休まらぬ中で、相続人の調査、財産の調査、税務申告準備等を行うのは相続人の方々にとって大変なご負担なりえるため、早めに相続の専門家に相談することをおすすめします。
また故人が個人事業主であった場合などは、消費税の申告もあわせて発生することもあります。繰り返しになりますが、税務に関する部分はとかく専門性が高い部分になりますので、専門家である税理士にお任せするのがよいでしょう。
▼実際に「いい相続」を利用して、行政書士に相続手続きを依頼した方のインタビューはこちら
ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。





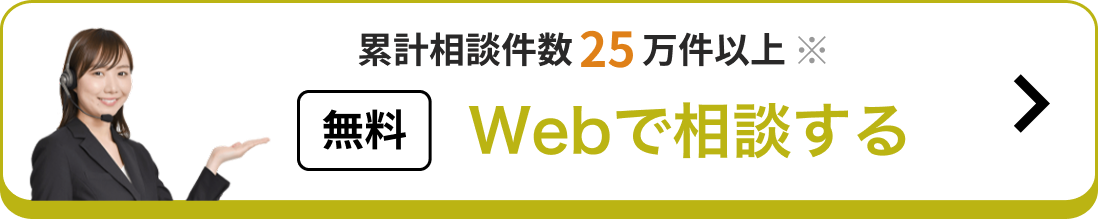
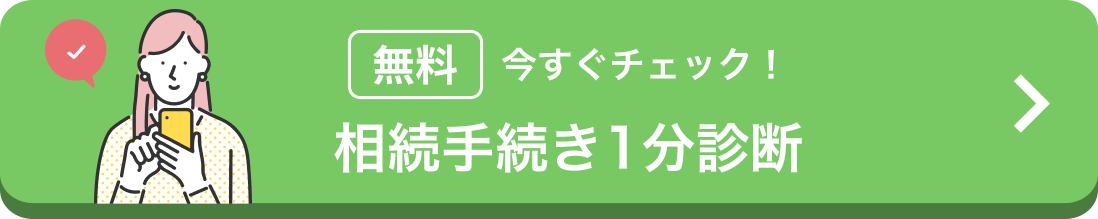
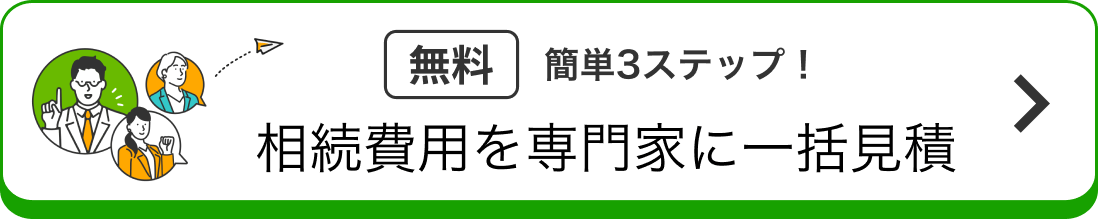
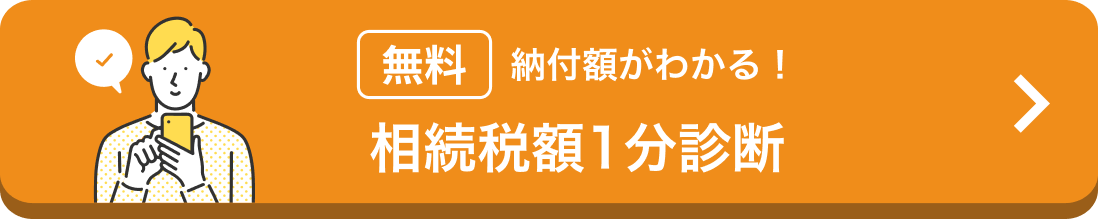
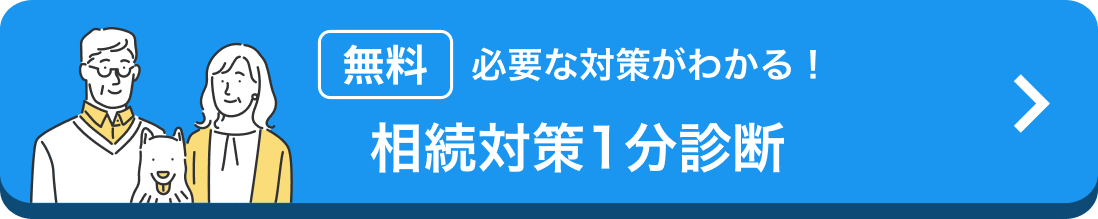
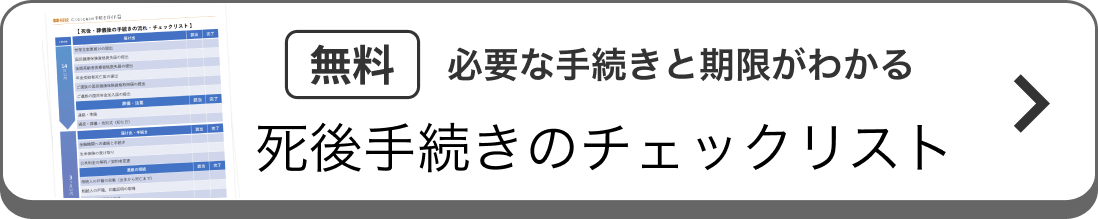
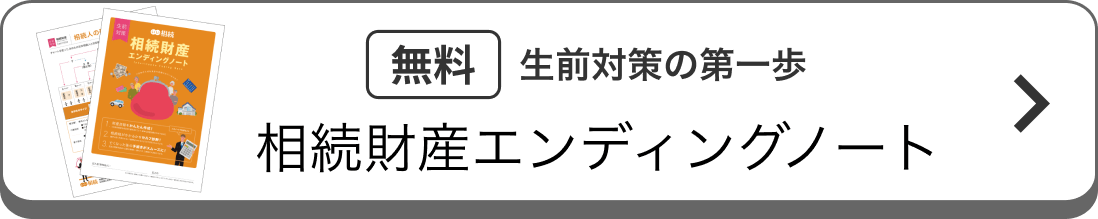
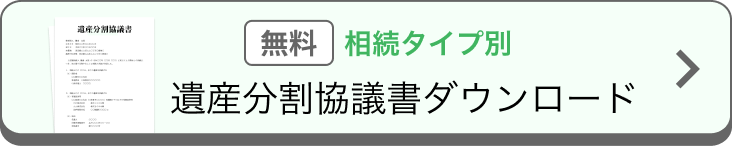

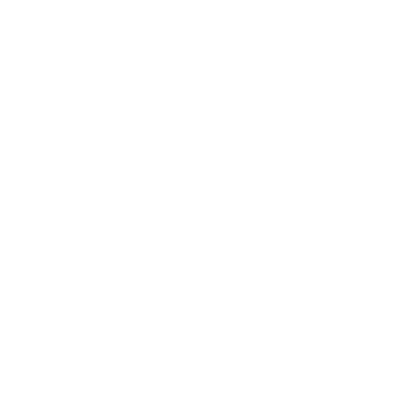
 Webで無料相談はこちら
Webで無料相談はこちら