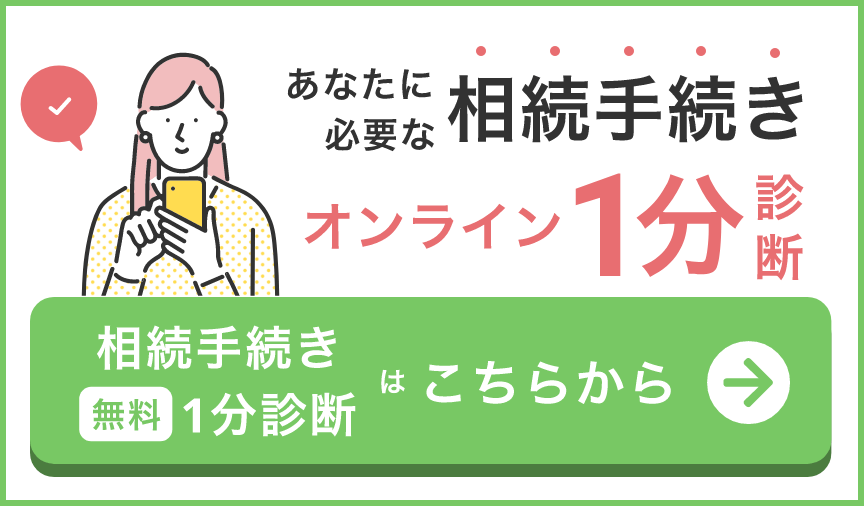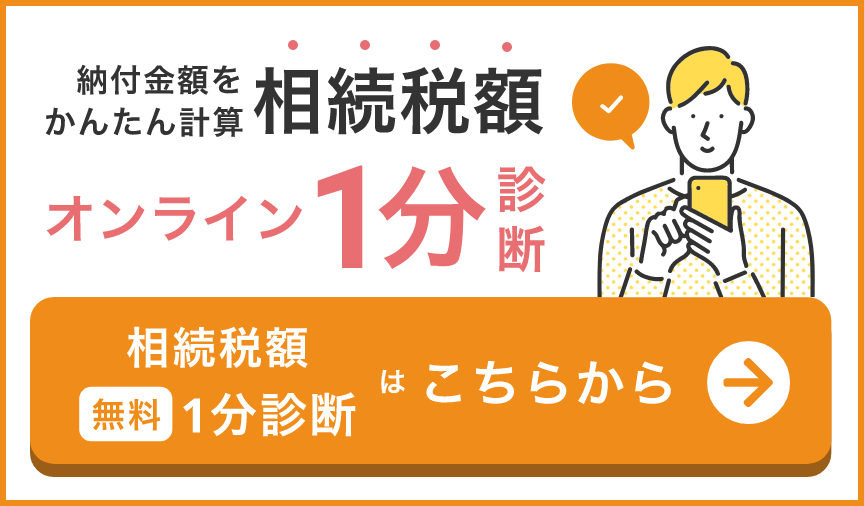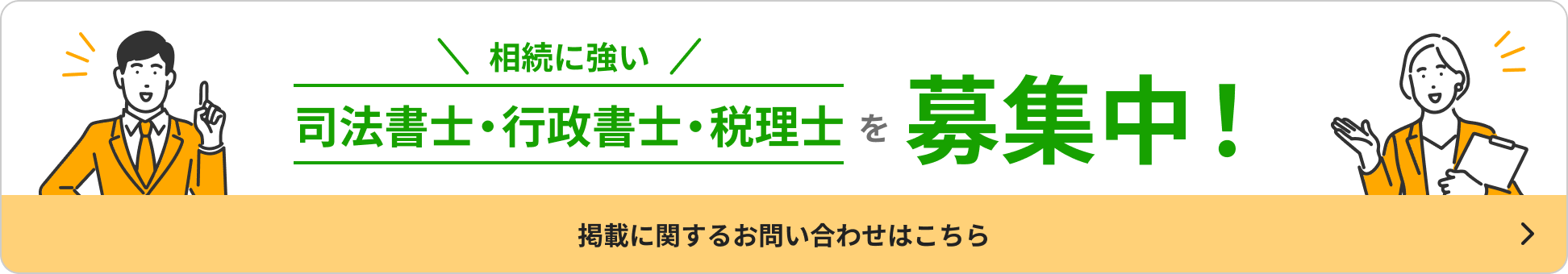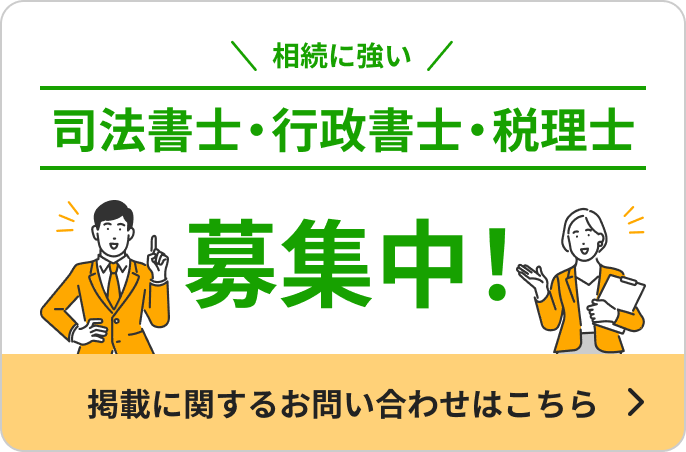相続税の債務控除とは?控除できる債務についてわかりやすく説明
本記事は、いい相続の姉妹サイト「遺産相続弁護士ガイド」で2020年5月13日に公開された記事を再編集したものです。
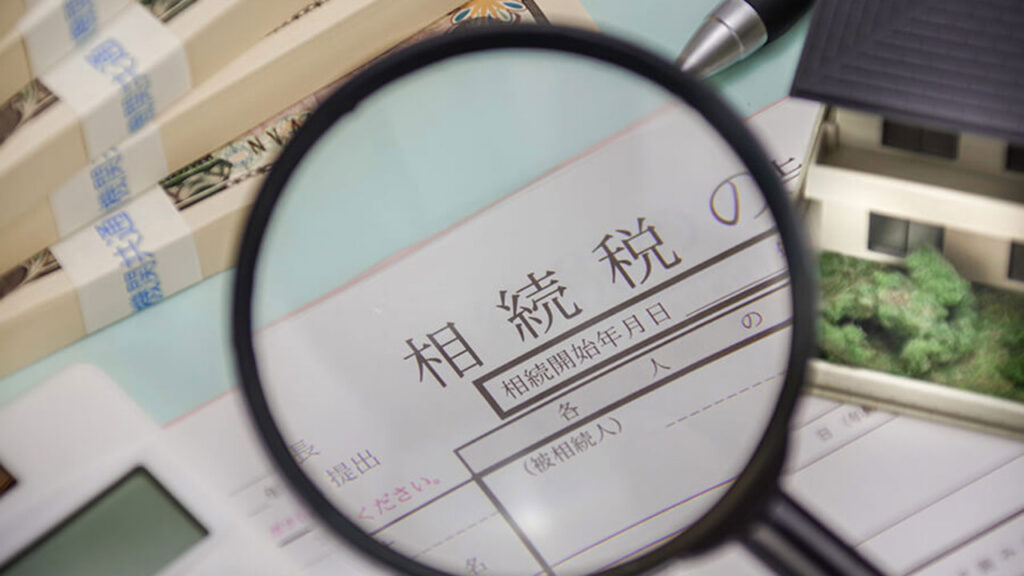
相続した遺産の総額が一定額を超える場合には、相続税がかかります。
相続税を計算するときは、被相続人(亡くなった人)が残した借入金などの債務を遺産総額から差し引く(控除する)ことができます。
相続税を安くできるように、相続税の債務控除の制度について、わかりやすく説明します。


この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士・司法書士・弁護士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。提携する税理士・行政書士は初回面談無料、相続のお悩みをプロが解決します。遺言書や遺産分割協議書の作成、相続税申告のご相談、相続手続の代行など「いい相続」にお任せください。
また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。


相続税の債務控除とは?
相続税の債務控除とは、相続税を計算するときに、遺産総額から被相続人が残した借入金などの債務を差し引くことをいいます。
例えば、遺産総額が1億円で、控除できる債務が1000万円あるとしたら、相続税は「1億円−1000万円=9000万円」に対してかかることになります。
債務控除の対象となる債務、対象とならない債務
差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときにあった債務で確実と認められるものです。
なお、被相続人に課される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税などの税金については被相続人が死亡したときに確定していないものであっても、債務として遺産総額から差し引くことができます。
ただし、相続人などの責任に基づいて納付したり、徴収されることになった延滞税や加算税などは遺産総額から差し引くことはできません。
また、被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできません。
そして、保証債務は原則として債務控除の対象となりません。
これは、保証債務は、保証債務を履行した場合は求償権の行使により補てんされるという性質を有するため、確実な債務とはいえないからです。
ただし、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証人がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償権を行使しても弁済を受ける見込みのない場合には、その弁済不能部分の金額については、債務控除の対象となります。
また、連帯債務については、ケースによって対応が異なります。
連帯債務者のうちで債務控除を受けようとする人の負担すべき金額が明らかとなっている場合には、当該負担金額を控除します。
連帯債務者のうちに弁済不能の状態にある人がおり、かつ、求償して弁済を受ける見込みがなく、当該弁済不能者の負担部分をも負担しなければならないと認められる場合には、その負担しなければならないと認められる部分の金額も当該債務控除を受けようとする人の負担部分として控除します。
具体例
具体例を挙げてみましょう。債務控除できるものの具体例
債務控除の対象となる債務として、例えば、次のようなものが挙げられます。
- 借入金、住宅ローン(団体信用生命保険で補填される金額を除く)
- 被相続人に課される税金で被相続人の死亡後相続人などが納付又は徴収されることになった所得税、住民税、固定資産税、個人事業税などの公租公課(税金)
- 医療費などの未払金
- 立替金(例えば、相続開始前に相続人が立て替えた医療費)
- 預かり敷金の返還債務
- 保証債務(保証人がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償権を行使しても弁済を受ける見込みのない場合における弁済不能部分のみ)
- 連帯債務(前述の要件を満たすものに限ります)
債務控除できないものの具体例
債務控除の対象とならない債務としては、例えば、次のようなものが挙げられます。
- お墓や仏壇などの非課税財産に関する債務(未払金)
- 団体信用生命保険で補填される住宅ローン
- 税理士報酬等の相続税申告に関する費用
- 司法書士報酬等の相続登記や相続手続き、遺言執行等に関する費用
- 遺産分割協議や遺留分減殺額請求等に関する弁護士報酬
- 戸籍謄本等の相続手続きの必要経費
- 保証債務、連帯債務(前述の要件を満たす場合を除く)
- 遺品整理費用


葬式費用は債務ではないが控除できる
葬式費用は債務ではありませんが、相続税を計算するときは遺産総額から差し引くことができます。
なお、死亡診断書等の医師による文書作成手数料は、債務控除ではなく、葬式費用として控除の対象となります。
葬式費用控除について詳しくは「相続税の計算時に控除できる葬儀(葬式)費用の範囲を具体的に説明!」をご参照ください。


相続税の控除制度
相続税の他の控除制度については「相続税の控除の仕組みと種類を理解して適用漏れで損しないための知識」をご参照ください。まとめ
以上、相続税の債務控除について説明しました。
相続税には様々な控除制度があり、うまく活用すれば、相続税がかからないようになったり、安く済ませたりすることができます。
相続税で損をしないように、一度、相続税に精通した税理士に相談することをお勧めします。税理士をお探しの方はお気軽にご連絡ください。


▼実際に「いい相続」を利用して、税理士に相続税申告を依頼した方のインタビューはこちら
この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士・司法書士・弁護士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。提携する税理士・行政書士は初回面談無料、相続のお悩みをプロが解決します。遺言書や遺産分割協議書の作成、相続税申告のご相談、相続手続の代行など「いい相続」にお任せください。
また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。


ご希望の地域の専門家を探す
ご相談される方のお住いの地域、遠く離れたご実家の近くなど、ご希望に応じてお選びください。




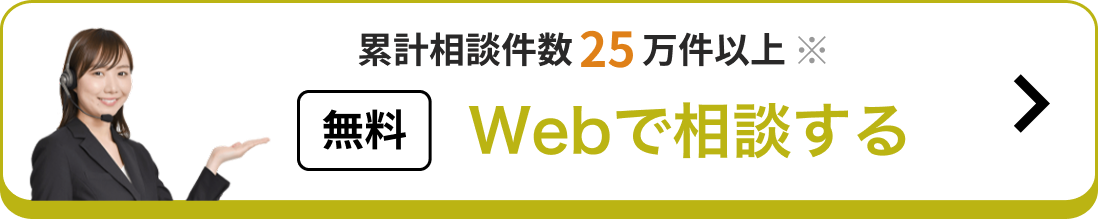
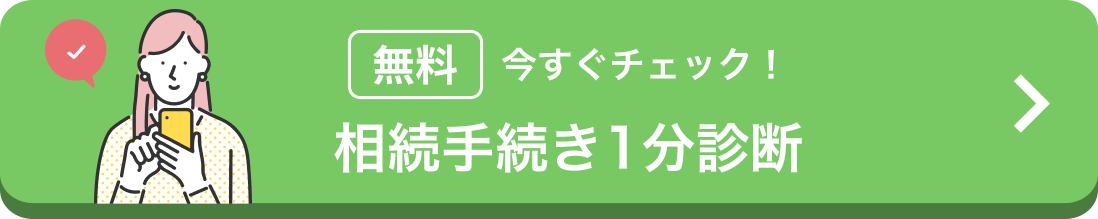
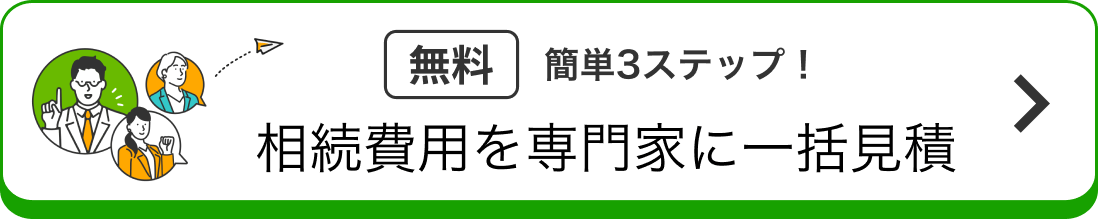
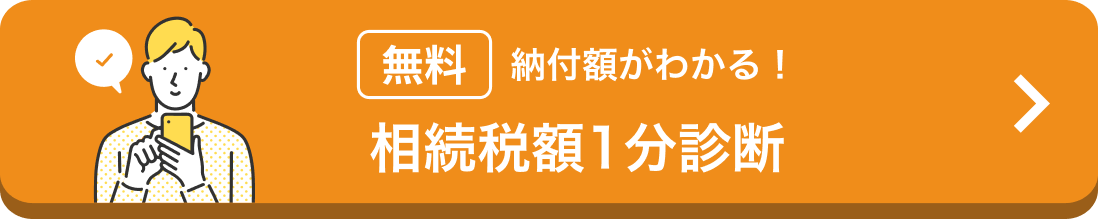
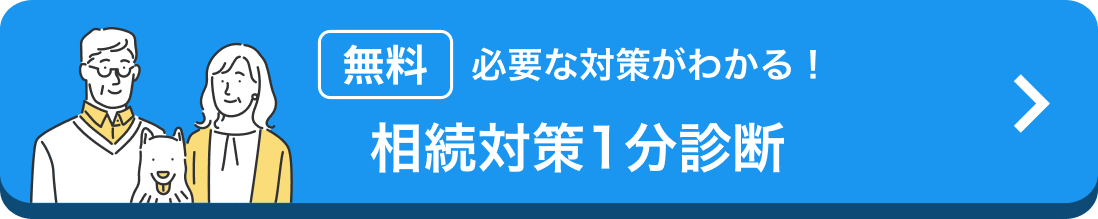
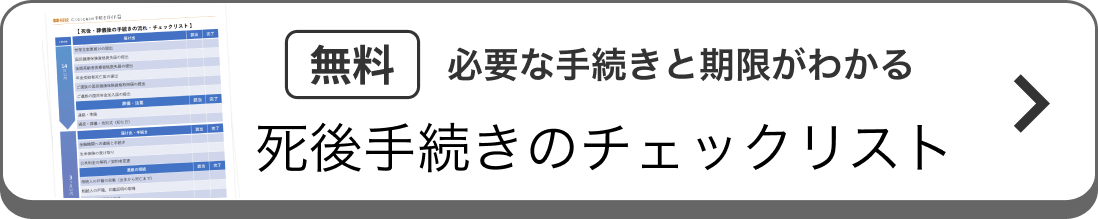
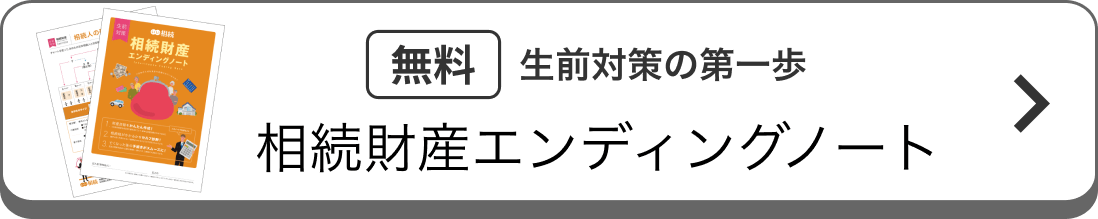
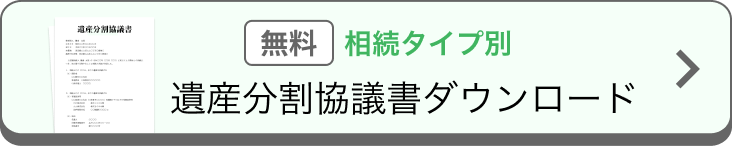
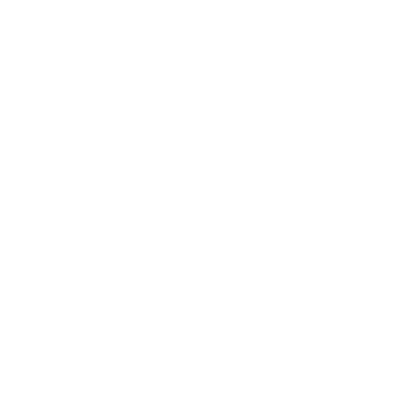
 Webで無料相談はこちら
Webで無料相談はこちら