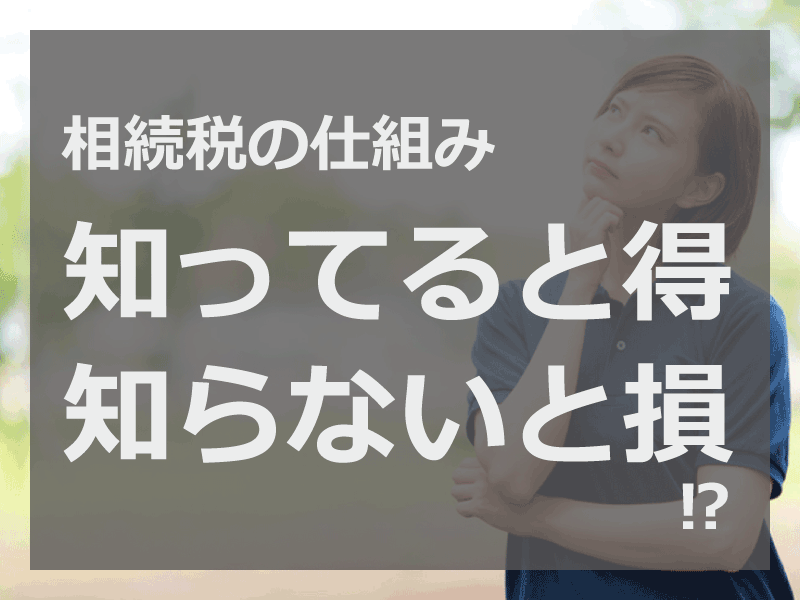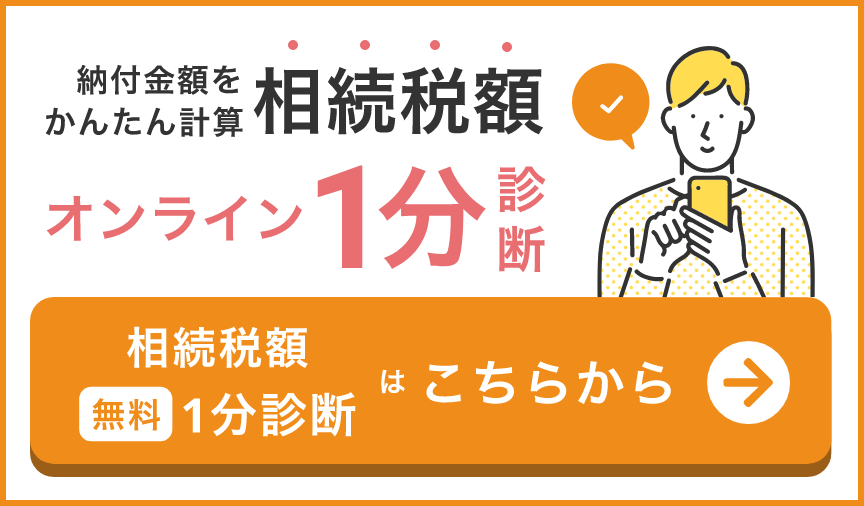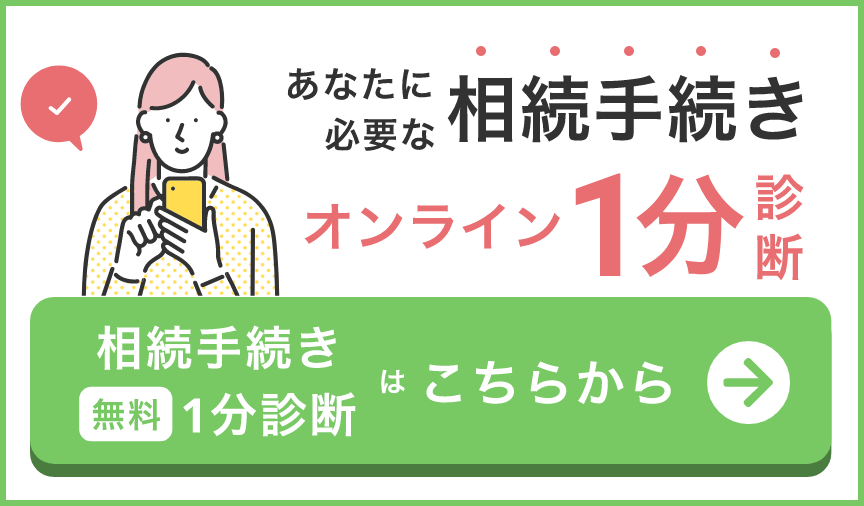tungsten
遺産相続弁護士ガイドでは
無料の電話相談を行っています。
相続でお悩みの方は、ぜひ一度、
専門家にご相談ください。
※当サイトは東証プライム上場・鎌倉新書が運営しています。
税務署は「○○控除の適用を受けると相続税を安くできますよ」とは教えてくれません。
制度の仕組みについて理解しておかなければ、相続税を高く計算してしまって損してしまうおそれも…。
そもそも、相続税がかかるかどうかを判断するためにも、控除等の仕組みを理解しておく必要があります。
そこで、この記事では、課税価格の計算上控除できるもの、相続税の税額控除、非課税となる財産、相続財産評価の特例について説明します。


[ご注意]
記事は、公開日(2019年5月3日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
location_onご希望の地域から弁護士を探す
課税価格の計算上控除できるもの
相続税の課税価格を計算する際に一定の金額を控除できる制度には、次のものがあります。
以下、主なものについて、説明します。
債務控除
差し引くことができる債務は、被相続人(亡くなって財産を残す人)が死亡したときにあった債務で確実と認められるもので、次のようなものが含まれます。
一方、被相続人が生前に購入したお墓の未払代金など非課税財産(
後述)に関する債務は、遺産総額から差し引くことはできません。
葬式費用控除
差し引くことができる葬式費用には、次のようなものが含まれます。
- 葬式や葬送に際し、又はこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用(仮葬式と本葬式を行ったときにはその両方にかかった費用)
- 遺体や遺骨の回送にかかった費用
- 葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用(例えば、お通夜などにかかった費用)
- 葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用
- 死体の捜索又は死体や遺骨の運搬にかかった費用
一方、次のような費用は含まれません。
- 香典返しのためにかかった費用
- 墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用
- 初七日や法事などのためにかかった費用
基礎控除
基礎控除額算定の計算式
基礎控除額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。
法定相続人とは、相続することができると法律で定められた人のことです。
上記の式に当てはめると、相続税の基礎控除額は、法定相続人の数ごとに次のようになります。
| 法定相続人の数 |
基礎控除額 |
| 1人 |
3600万円 |
| 2人 |
4200万円 |
| 3人 |
4800万円 |
| 4人 |
5400万円 |
| 5人 |
6000万円 |
| 以降も法定相続人が1人増えるごとに600万円を加算 |
基礎控除額の算定の基礎となる法定相続人の数とは?
誰が法定相続人になるかについては「
相続順位のルールを図や表を用いて弁護士が詳しく分かりやすく解説!」をご参照ください。
相続税の基礎控除額算定の基礎となる法定相続人の数え方について、次の場合は、注意が必要です。
- 被相続人に養子が複数いる場合
- 相続放棄をした人がいる場合
- 相続欠格者、推定相続人の廃除を受けた人がいる場合
以下、それぞれについて説明します。
被相続人に養子が複数いる場合
養子も通常の実子と同様に法定相続人となります。
しかし、相続税の基礎控除額の算定の基礎となる法定相続人の数には、すべての養子をカウントするわけではありません。
すべての養子をカウントすると、養子を増やすことによって、基礎控除を増やし、税金逃れができてしまうからです。
基礎控除の計算時に参入できる養子の数は、実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までと制限されています。
しかし、
次の場合は、実子として扱い、養子の算入制限による影響を受けず法定相続人としてカウントすることができます。
- 特別養子
- 配偶者の実子で、かつ、被相続人の養子(いわゆる連れ子養子)
- 代襲相続人(ただし、養子としての立場と併せて二重にカウントするわけではない)
代襲相続とは、相続人となるべき者(被代襲者)が、相続開始以前に死亡しているときや相続欠格または廃除により相続権を失ったときにおいて、その被代襲者の直系卑属(代襲者)が被代襲者に代わって、その受けるはずであった相続分を相続することをいいます(「
代襲相続とは?範囲は?孫や甥・姪でも相続できる代襲相続の全知識」参照)
相続放棄をした人がいる場合
相続財産がプラスの財産よりも借金等のマイナスの財産の方が多い場合は、相続すると損してしまいます。
相続放棄とは、このような場合等に、相続する権利を放棄することをいいます(「
財産放棄と相続放棄の違いを理解して財産放棄で損しないための全知識」参照)。
相続放棄があっても、相続税の基礎控除額の計算上は、相続放棄した法定相続人を除かずに計算します。
例えば、法定相続人が
3人いて、そのうちの
1人が相続放棄をしたとします。
その場合も、法定相続人は
3人として計算して、基礎控除額は
4800万円になります。
この原則は、相続放棄者が何人でも変わりありません。
例えば、子の全員が相続放棄をすると相続権は直系尊属に移り、直系尊属の全員が相続放棄をすると相続権は兄弟姉妹に移ります。
このように、
相続順位が高順位のグループが全員相続放棄をして、新たな法定相続人が生じても、基礎控除額の算定の基礎となる法定相続人の数は、相続放棄する前の当初の法定相続人の数から変わりません。
相続欠格者、推定相続人の廃除を受けた人がいる場合
相続欠格とは、相続人が遺言書の偽造等の不正をはたらいた場合に、その相続人が相続人となれなくする制度のことです(「
相続欠格とは?相続欠格事由とは?判例に基づいてわかりやすく説明」参照)。
推定相続人の廃除とは、相続人が被相続人を虐待する等の著しい非行を行った場合に、その相続人が相続人となれなくする制度のことです(「
相続廃除の意味とは?排除は誤字!推定相続人の廃除で遺留分をなくす」参照)。
欠格や廃除で相続人でなくなった人は、基礎控除額の算定の基礎となる法定相続人の数にもカウントしません。
放棄の場合とは異なる扱いになります。
なお、欠格や廃除を受けた人に子がいれば、代襲相続が可能です。
その場合、代襲相続人の人数は、基礎控除額の算定の基礎となる法定相続人の数にカウントします。
なお、放棄の場合は、代襲ができないので、この問題は生じえません。
課税価格が基礎控除額以下の場合は申告不要
相続税の課税価格(小規模宅地等の特例等の適用前)が基礎控除額以下の場合は、相続税はかからず、相続税の申告は不要です。
相続税の税額控除
相続税の税額を計算する際に一定の金額を控除できる制度には、次のものがあります。
- 暦年課税分の贈与税額控除
- 配偶者の税額軽減(いわゆる配偶者控除)
- 未成年者控除
- 障害者控除
- 相次相続控除
- 外国税額控除
- 相続時精算課税分の贈与税額相当額の控除
- 医療法人持分税額控除
以下、主なものについて、説明します。
暦年課税分の贈与税額控除
贈与を受けた財産については、原則として、贈与税が課されます(暦年課税の場合。「
暦年課税とは?暦年課税と相続時精算課税はどちらが得か?」参照。)
しかし、相続又は遺贈により財産を取得した者に対して、亡くなる前の
3年間に行われた贈与は、相続税の計算に足し戻されるため、相続税が課されます。
既に贈与税を支払っている場合は、相続税も課されることとなり、贈与税と相続税の
2重課税となってしまいます。そこで、相続税から既に支払った贈与税の金額を差し引いた金額を相続税として納めればよいこととなっています。
ただし、
贈与税として支払った金額が、課されるべき相続税よりも大きかったとしても、差額の贈与税は還付されません。
ちなみに、住宅取得等資金の贈与の特例を利用しての贈与の場合は、亡くなる前
3年以内の贈与であっても、贈与税非課税とされた金額については相続税も非課税となります(つまり、足し戻しの計算は行なわれません。住宅取得等資金の贈与の特例については「
住宅取得資金贈与を非課税にする方法と使わない方が節税になるケース」参照)。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
「配偶者の税額軽減」は、配偶者だけが利用できる制度で、「相続税の配偶者控除」と呼ばれることもあります。
配偶者が遺産分割や遺贈により取得した遺産額から、配偶者の法定相続分
相当額か
1億
6000万円のいずれか大きい方の金額を差し引いて、残った金額にのみ課税するという制度です。
差し引く金額の方が大きい場合は、課税されません。
つまり、法定相続分の範囲内で遺産分割や遺贈を受ける分においては、配偶者は相続税が課されることはないのです。
法定相続分を超えて遺産を取得した場合にのみ、相続税が課される可能性が生じますが、それでも
1億
6000万円までは課税されないので、ほとんどの家庭では配偶者はまったく課税されないということになります。
配偶者控除を受けることができる配偶者は、相続開始の時点(被相続人が亡くなった時点)において、法律上婚姻関係にあった配偶者に限られます。
そのため、内縁関係にあった(事実婚状態にあった)事実上の配偶者や、被相続人が亡くなる前に離婚届を提出してしまった元配偶者は、仮に、遺言等によって財産を相続したとしても、この配偶者控除を利用することはできません。
逆に、法律上婚姻関係にあればよいので、別居しているとか、離婚調停中であるような場合でも、この配偶者控除の制度を利用することは可能です。
なお、配偶者の税額軽減の適用を受けた結果、相続税額が0円になる場合がありますが、その場合でも、相続税の申告は必要です。
配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書において、税額軽減の明細を記載する方法で行います。
そのうえで、相続税の申告書を提出する際に、遺言書の写しや遺産分割協議書の写しなど、配偶者が取得した財産がわかる書類を添付する必要があります。
そのため、原則として、相続税の申告期限までに、遺産分割等が終了している必要がありますが、仮に、相続税の申告期限までに遺産分割等が終了していない場合は、相続税の申告書に、「申告期限後3年以内の分割見込書」と添付した上でいったん相続税の申告を行い、その後申告期限から3年以内に分割をした場合には、配偶者控除の対象とすることが可能です。
未成年者控除
未成年者の税額控除は、相続人が未成年者の場合(一定の要件を満たす必要があります)に利用できる税の軽減制度です。
控除額は年齢によって異なり、年齢が低い方が控除額が大きくなるようになっています。
具体的には、次の式で計算できます。
例えば、相続時の年齢が満
10歳だった場合は、次のように計算します。
6万円 ×(
20 -
10)=
60万円
なお、計算に用いるのは、相続時の「満年齢」なので、
10歳になったばかりでも、
10歳
11か月でも、同じ
10歳として計算します。
控除額が相続税額よりも大きい場合は、差額をその未成年者の扶養義務者の相続税額から控除します。
なお、以前も未成年者の税額控除を受けている場合は、控除額が制限されることがあります。
障害者控除
障害者の税額控除は、相続人が85歳未満の障害者の場合(一定の要件を満たす必要があります)に、相続税額から一定の控除額を差し引く制度です。
控除額は次の計算式で算出することができます。
なお、特別障害者(重度の障害のある方)の場合は、上式の「
10万円」を「
20万円」に変更して計算します。
控除額が相続税額よりも大きい場合は、差額をその障害者の扶養義務者の相続税額から控除します。
なお、以前も障害者の税額控除を受けている場合は、控除額が制限されることがあります。
相次相続控除
相次相続控除は、今回の相続開始前10年以内に、被相続人が相続や遺贈などによって財産を取得し相続税が課されていた場合に、その被相続人から相続や遺贈などによって財産を取得した人の相続税額から一定の金額を控除する制度です。
相次相続控除の額は、前回の相続において課税された相続税額のうち、
1年につき
10%の割合で逓減した金額です。
相次相続控除額は次の式で計算することができます。
| A × C ÷(B - A)※× D ÷ C ×(10 - E) ÷ 10 |
※
C ÷(
B -
A)が
100/100を超えるときは、
100/100とします。
- A:二次相続の被相続人の一次相続における相続税額
- B:二次相続の被相続人の一次相続における純資産価額
- C:二次相続における純資産価額の合計額
- D:二次相続における相次相続控除適用者の純資産価額
- E:一次相続の開始から二次相続の開始までの経過年数(端数切捨て)
相次相続控除について詳しくは「
相次相続控除で相続税を安くするために絶対に知っておくべき10のこと」をご参照ください。
外国税額控除
外国税額控除とは、外国に納めた相続税額のうち、一定の要件を満たすものについて、日本で課せられる税額から控除する制度です。
外国税額控除については、一般の人が適用可否を判断するのは難しいでしょうから、税理士に相談することをお勧めします。


相続時精算課税分の贈与税額相当額の控除
相続時精算課税とは、一定の条件を満たすことで親や祖父母から贈与された財産の贈与税が2500万円まで非課税になって、その分、相続時に相続税として課税される制度です(「
相続時精算課税制度を迂闊に利用して大損しないために知るべきこと」参照)。
2500万円を超える部分については、一律
20%の贈与税が課せられます。
この贈与税相当額は相続税額から控除することができます。
その際、相続税額から控除しきれない相続時精算課税に係る贈与税相当額については、相続税の申告をすることにより還付を受けることができます。
医療法人持分税額控除
相続人等が、被相続人から相続又は遺贈により医療法人の持分を取得した場合において、その医療法人が相続開始の時において認定医療法人であり、かつ、相続人等が相続開始の時から相続税の申告期限までの間に、認定医療法人の持分の全部又は一部を放棄したときは、その相続人等の相続税額から、放棄相当相続税額を控除します。
詳しくは、
国税庁ウェブサイトの「医療法人の持分についての相続税の納税猶予の特例」のページをご参照ください。
小規模宅地等の特例
相続税は相続財産の価額(相続税評価額)に応じて課税されるので、評価額を減額して計算することができれば、相続税の税額も減らせます。
一定の要件を満たせば、宅地の相続税評価額を減額できる「小規模宅地等の特例」という制度があります。
小規模宅地等の特例の適用を受けた結果、相続税の課税価格が控除額以下になり、相続税がかからなくなることがありますが、その場合でも、相続税の申告は必要です。
相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、小規模宅地等に係る計算の明細書や遺産分割協議書の写しなど一定の書類を添付する必要があります。
小規模宅地等の特例について詳しくは「
小規模宅地等の特例で8割減で大幅に節税する方法と意外な落とし穴」をご参照ください。
相続税の非課税財産
相続税がかからない非課税財産には、相続税が非課税となる財産には、主に次のものがあります。
- 皇室経済法第7条の規定により皇位とともに皇嗣が受け継ぐ由緒ある物
- 墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
- 一定の公益事業を行う者が取得した一定の公益事業用財産
- 条例による心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
- 相続人が取得した生命保険金等及び退職手当金等のうち一定の金額
- 相続税の申告書の提出期限までに国、地方公共団体、特定の公益法人又は認定特定非営利活動法人に寄附等をした財産
このうち、一般の人が特に関係しそうなものは次の
2点でしょう。
- 墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
- 相続人が取得した生命保険金等及び退職手当金等のうち一定の金額
以下、この
2点について、それぞれ説明します。
墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
まず、「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」について説明します。
墓所とはお墓を建てる場所(区画)のことです。
霊びょうは、漢字では「霊廟」と書き、霊を祀る建物のことです。
「墓所、霊びょう」には、墓地、墓石及びおたまやのようなもののほか、これらのものの尊厳の維持に要する土地その他の物件をも含みます。
祭具とは、祭祀に用いられる道具のことです。
「これらに準ずるもの」とは、庭内神し、神たな、神体、神具、仏壇、位はい、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に供しているものをいいます。
例えば、純金製の高価な仏像を金庫に保管している場合は、日常礼拝の用に供しているとは認められずに相続税の課税価格に算入すべきと判断される可能性があります。
ただし、
商品、骨とう品又は投資の対象として所有するものは含まれません。
例えば、墓石屋さんのご主人が亡くなって、商品である墓石を息子が相続した場合は、「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」には含まれず、その墓石の価額は相続税の課税価格に算入されます。
なお、「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」は相続税の課税価格に算入しませんが、「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」の購入資金は相続税の課税価格に算入します。
つまり、被相続人の死亡後に、相続人が「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」を相続したお金で購入した場合は、その資金は相続税の課税価格に算入し、被相続人が生前に購入した「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」を相続した場合は、その価額は相続税の課税価格に算入されません。
要するに、「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」を購入するなら、被相続人が生前に購入した方が相続税対策になるということです。
相続人が取得した生命保険金等及び退職手当金等のうち一定の金額
生命保険金と退職手当金は、必ずしも全額が課税対象となるわけではありません。
受取人が相続人の場合は、生命保険金や退職手当金のうち一定額までは非課税とされますが、受取人が相続人でない場合は非課税とされる金額はありませんので、全額が課税対象となります。
非課税限度額は、次の式で計算することができます。
法定相続人の数え方については前述のとおりです。
まとめ
以上、相続税の控除について説明しました。
相続税の申告の際は、税理士に相談をして、控除の適用漏れや、反対に適用できないはずの控除をしてしまって申告漏れが生じないように気を付けましょう。
相続税に強い税理士の一覧は、以下のリンク
もご参照ください。