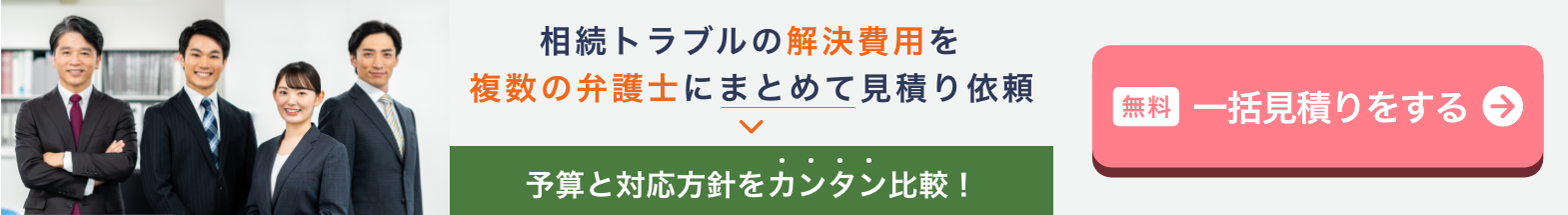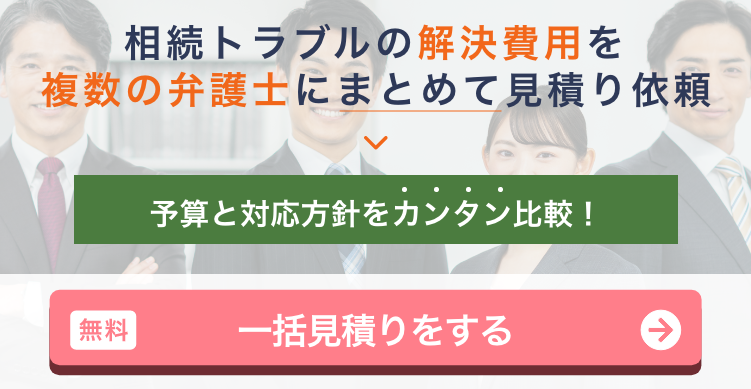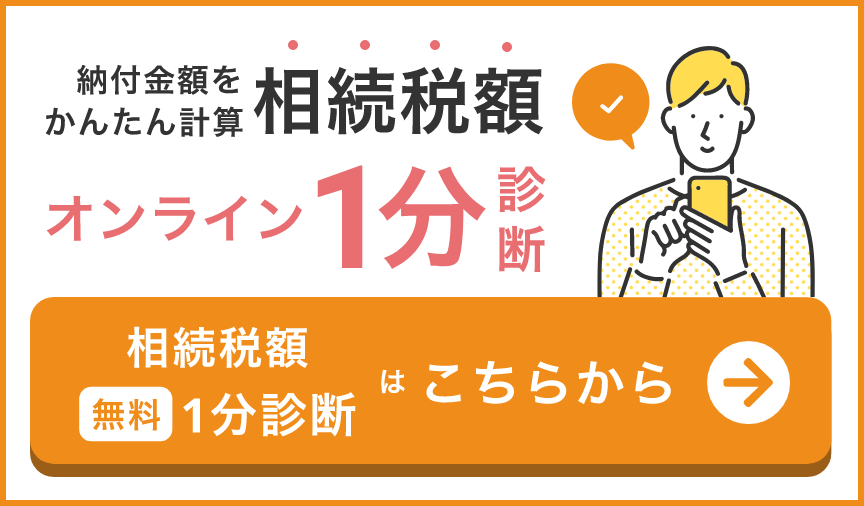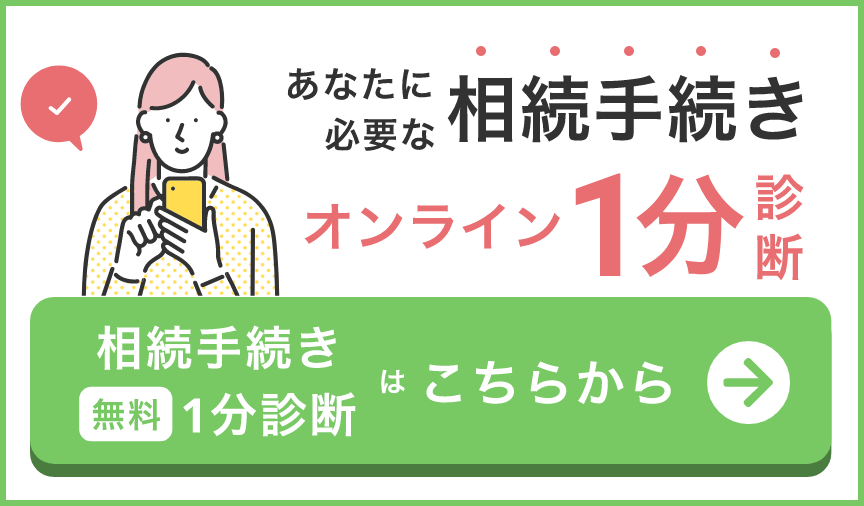遺留分減殺請求(侵害額請求)の弁護士費用相場。請求されたときも

亡くなった親が残した遺言によって遺産がまったくもらえないとか、全財産が贈与済みで一切遺産がないとかで、遺産をまったく取得できなかったら、がっかりしますよね。そのような場合は、遺留分侵害額請求によって、一定割合の遺産を取り戻すことができます。
この記事では、遺留分侵害額請求の弁護士費用について、わかりやすく説明します。また、反対に、遺留分侵害額請求を受けた人も弁護士に相談することによって、請求を退けたり、額を減らすことができる場合があります。このような請求を受けた側の人の弁護士費用についても、併せて説明します。
[ご注意]
記事は、公開日(2020年4月17日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
相続問題でお悩みの方は
まずは弁護士にご相談ください
遺留分侵害額請求とは?遺留分減殺請求との違いは?
遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった人)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。
被相続人が財産を遺留分権利者以外の人に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することできます。
これを遺留分侵害額の請求といいます。
そして、遺留分侵害額を請求する権利のことを、遺留分侵害額請求権といいます。
2019年の法改正までは、遺留分権利者は、遺留分侵害額請求権ではなく、遺留分減殺請求権を有するものとされていました。
遺留分減殺請求権とは、旧法下の規定で、遺留分を侵害された人が、贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分侵害の限度で贈与や遺贈された財産の返還を請求する権利のことをいいます。
旧法下では、遺留分権利者が減殺請求すると、請求された人は、遺贈や贈与で取得した財産の遺留分に相当する分の財産を返還しなければなりませんでした。
ただし、遺留分権利者は、返還される財産を選択することはでません。
例えば、減殺対象の財産に現金と不動産があった場合に、遺留分権利者の方から、現金での返還を指定したり、不動産での返還を指定することはできません。
基本的には、それぞれの財産に対して、遺留分に応じた持分を取得することになります。
例えば、遺留分が4分の1で、減殺されるべき財産が現金1000万円と不動産であった場合は、現金250万円と不動産の4分の1の共有持分を取得することになります。
ただし、請求された人には価額弁償の抗弁権があり、上記のように現物を返還するのではなく、お金で清算することを提案することができます。
例えば、先ほどの例で、不動産の価格が7000万円であったとすると、現金1000万円と併せて、遺留分算定の基礎となる財産の価額は8000万円になり、遺留分が4分の1であれば、2000万円を弁償することで、現物の返還に代えることができます。
まとめると、旧法下の遺留分減殺請求では、贈与や遺贈を受けた財産そのものを返還するという「現物返還」が原則であり、金銭での支払いは例外という位置づけでしたが、改正後の遺留分侵害額請求は、金銭請求に一本化されたということです。
遺留分侵害額請求の弁護士費用の相場
弁護士費用は、以前(2004年3月まで)は、日本弁護士連合会(日弁連)の報酬等基準規定(旧規定)に定められていましたが、現在は、このような基準はなく、各事務所が自由に報酬を決められるようになっています。
しかし、現在でも、日弁連の旧規定を参考に報酬を決める事務所が多いため、旧規定が実質的に弁護士費用の相場となっていますので、この記事でも、旧規定を基に説明します。
遺留分侵害額請求に関する弁護士費用には、次のようなものがあります。
- 法律相談料
- 着手金、報酬金
- 日当
- 実費
以下、それぞれについて説明します。
法律相談料
法律相談料は、旧規定では、30分ごとに5千~1万円となっていましたが、現在では、無料相談を実施している弁護士も増えています。
当サイトにも初回の法律相談を無料としている事務所が多数掲載されています。弁護士による無料相談を希望する方は、以下のリンク先ページから、無料相談を行っている弁護士事務所を確認するとよいでしょう。
着手金、報酬金
着手金は、弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。
報酬金は、事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。
成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功(裁判でいえば全面敗訴)の場合は支払う必要はありません。
着手金と報酬金は、経済的利益の額に応じて変動するのが一般的で相場は次の表のとおりです。
表中の「%」は、経済的利益の額に対する割合です。
| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下の場合 | 8% ※ただし最低10万円 | 16% |
| 300万円超3000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
| 3000万円超3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
| 3億円超の場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
例えば、2000万円の遺留分侵害額を請求し、1800万円で和解した場合の経済的利益の額は、依頼時(着手金の計算時)においては請求額である2000万円となり、事件終了時(報酬金の計算時)においては請求が認められた1800万円になります。
そうすると、着手金は「2000万円×5%+9万円=109万円」、報酬金は「1800万円×10%+18万円=198万円」になります。
反対に、請求を受けた方も弁護士に依頼していたとして、そちらの弁護士費用についても計算してみましょう。
依頼時(着手金の計算時)においては、減額を求める金額である2000万円が経済的利益となり、事件終了時(報酬金の計算時)においては「2000万円-1800万円=200万円」の減額に成功しているので、200万円です。
そうすると、着手金は「2000万円×5%+9万円=109万円」、報酬金は「200万円×16%=32万円」となります。
日当
日当は、弁護士が、裁判所に出廷する等、事務所以外の場所で執務する必要が生じた場合に生じる費用です。
日当を設定していない事務所もあります。
日当が設定されている場合は、どのような場合に日当が必要になるのか、依頼前に確認しておくとよいでしょう。
日当が設定されている場合の相場は下の表のとおりです。
| 半日(2時間超4時間以内) | 3万~5万円 |
|---|---|
| 一日(4時間超) | 5万~10万円 |
実費
実費は文字どおり事件処理のため実際に出費されるもので、裁判を起こす場合でいえば、裁判所に納める印紙代と切手代、記録謄写費用、場合によっては保証金、鑑定料などがかかり、また、出張する場合は、交通費、宿泊費がかかります。
まとめ
以上、遺留分侵害額請求の弁護士費用について説明しました。
前述のとおり、旧規定はあくまで相場を知るためのものであり、旧規定よりも安価になる独自の報酬規定を設定している事務所も多く存在します。
しかしながら、相手方との交渉の優劣によって、獲得できる金額が変わってきますから、費用だけで弁護士を選ぶことはおすすめしません。
初回相談時に費用の計算方法を丁寧に説明してくれて、かつ、信頼のおける事務所に依頼することをお勧めします。
この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
ご希望の地域の専門家を探す