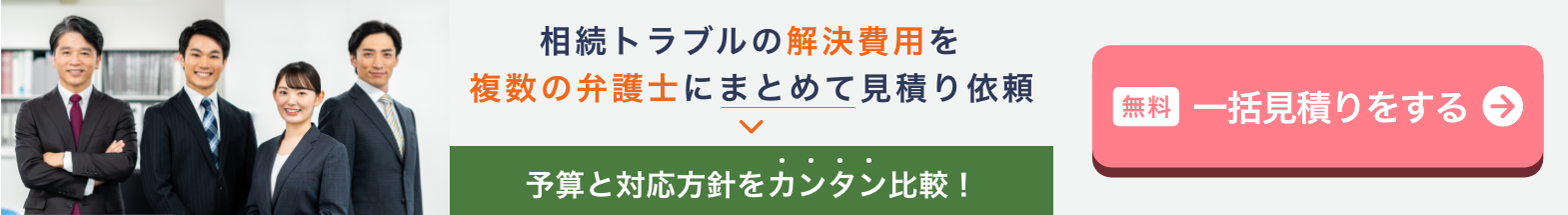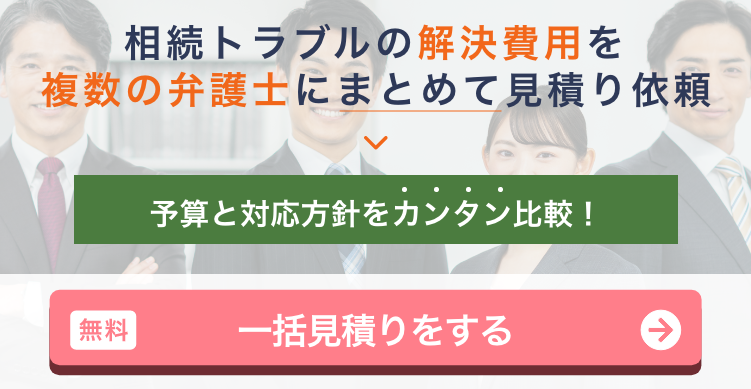相続放棄をしても生命保険金は受け取れる!入院給付金や県民共済は?

[ご注意]
記事は、公開日(2019年4月2日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
目次
相続放棄をしても基本的には生命保険金は受け取れる
相続放棄をしても、基本的には、生命保険金を受け取ることができます。 被相続人(亡くなった人)を被保険者(保険が掛けられている人)とする生命保険金の受取人については、次の3つのパターンがありえます。- 特定人(名指し)
- 相続人
- 被相続人
生命保険金にかかる税金
生命保険金を受け取った場合には、相続税が課せられる場合、贈与税が課せられる場合、所得税と住民税が課せられる場合の3つのパターンがあります。 被保険者、保険料の負担者および保険金受取人がそれぞれ誰かによって、課せられる税金の種類が異なる仕組みになっているのです。 詳しくは、下表をご参照ください。| 被保険者 | 保険料の負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
|---|---|---|---|
| A | B | B | 所得税、住民税 |
| A | A | B | 相続税(満期の場合は贈与税) |
| A | B | C | 贈与税 |
生命保険金にかかる相続税の非課税限度額は相続放棄をすると不適用に
生命保険金にかかる相続税の計算方法は、保険金の受取人が相続人なのか相続人でないのかによって異なります。 受取人が相続人の場合は、保険金のうち一定額までは非課税とされますが、受取人が相続人でない場合は非課税とされる金額はありませんので、全額が課税対象となります。 受取人が相続放棄をした場合は、相続人ではなくなるため、非課税限度額の適用を受けることができなくなります。 なお、非課税限度額は、次の式で計算することができます。| 500万円×法定相続人の数 |
相続放棄をしても受け取れるもの、相続放棄をすると受け取れないもの
相続放棄をしても受け取れるものと、相続放棄をすると受け取れないものの違いは、相続財産に含まれる(=被相続人の財産)かどうかです。 相続財産に含まれるものは、相続放棄をすると受け取れませんし、含まれないものは、相続放棄をしても受け取れることができます。 よく質問を受ける給付金の類について、相続放棄をしても受け取れるものと、相続放棄すると受け取れないものに分類して紹介します。 なお、以下の紹介する分類は、通常このように解されているものではありますが、事情によってはこの通りにならないこともありえます。 ついては、相続放棄をする前に、弁護士等の専門家に相談することをお勧めします。 当サイトでも相続放棄に精通した弁護士や司法書士を掲載しています。 上のリンク先のページから専門家を選んで相談してみるとよいでしょう。 前置きが長くなりました、まず、相続放棄をしても受け取れるものから紹介します。- 生命保険金 ※受取人が被相続人の場合を除きます。
- 葬祭費、埋葬料、埋葬費
- 遺族年金、死亡一時金
- 未支給年金
- 死亡退職金 ※受取人が被相続人の場合や定められていない場合を除きます。
- 高額医療費の還付金 ※世帯主が被相続人の場合を除きます。
- 被相続人が受取人となっている保険金全般(入院保険、傷病保険、生命保険金等)
- 税金、保険料、年金等の還付金
まとめ
以上、相続放棄と生命保険金の関係について説明しました。 相続放棄をした場合に受け取れるかどうかについて不明なものは、受け取る前に、弁護士等の専門家に相談するとよいでしょう。 また、生命保険金にかかる税については、税理士に相談しましょう。この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
ご希望の地域の専門家を探す