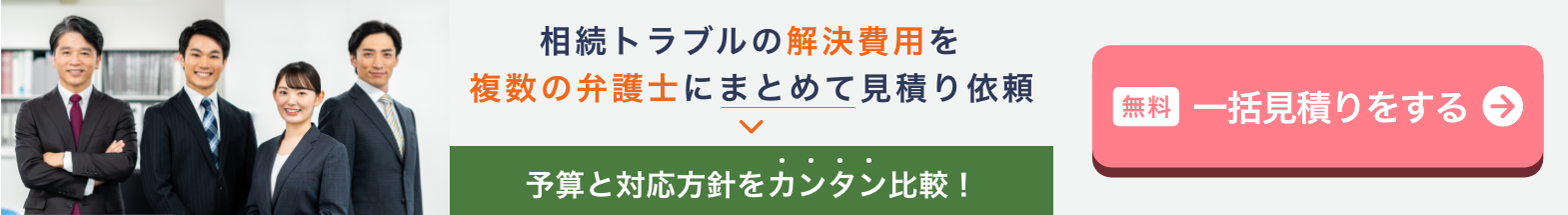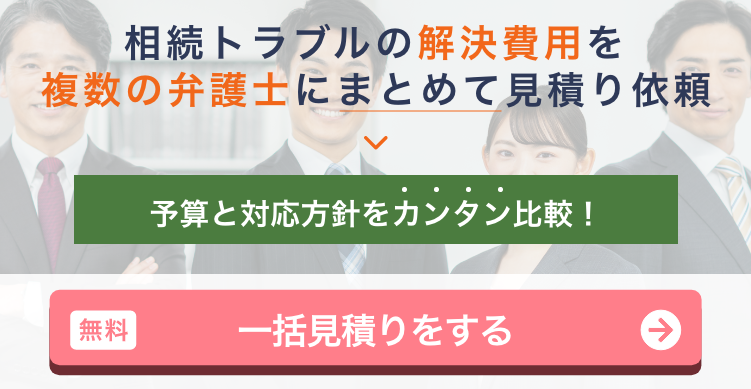寄与分と遺留分侵害額請求(旧遺留分減殺請求)の関係

故人の生前に介護などで尽くしたとして、その分多く財産を相続できることを「寄与分」と言います。
一方、一定の相続人に最低限の取り分を保障する「遺留分」があります。例えば、配偶者と子が相続人でいた場合、1/4ずつもらうことができます。この申立て(遺留分侵害額請求)を行えば他の人に財産を独占されることはありません。
このとき、寄与分があるとして遺留分の金額を引き上げることはできるのでしょうか?もしくは、遺留分を侵害するような寄与分の主張は通るのでしょうか?
今回はこの関係について詳しく解説していきます。是非、参考にしてください。
[ご注意]
記事は、公開日(2021年1月4日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
寄与分とは?
被相続人の生前に、相続人が、被相続人の財産の増加や維持に寄与した程度のことです。寄与分がある相続人は、その分多くの財産を相続することができます。
遺留分とは?
遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈(遺言によって財産を取得させること)によっても奪われることのないものです。
被相続人が財産を遺留分権利者以外の人に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することできます。これを「遺留分侵害額請求」といいます。
なお、遺留分に関しては、2019年7月1日に改正法が施行され、改正前は、遺留分侵害額に相当する「金銭」ではなく、遺留分侵害の限度で贈与や遺贈された「財産そのもの」の返還を請求できることになっており、これを「遺留分減殺請求」とよんでいました。
もっとも、寄与分との関係においては、法改正によって特段変更になった点はありません。
寄与分と遺留分の関係
寄与分と遺留分の関係について、「遺留分の算定において寄与分は考慮されるか」、「遺留分を侵害する寄与分の主張は認められるか」、「遺留分侵害額請求に対して、寄与分を主張することによって、請求を拒んだり、減額を求めたりできるのか」というような点から説明します。
遺留分の算定において寄与分は考慮されるか
結論としては、遺留分の算定において寄与分は考慮されません。
つまり、遺留分を侵害する遺贈又は贈与を受けた人に寄与分があったとしても、請求できる遺留分侵害額に違いはなく、また、反対に、遺留分権利者に寄与分があったとしても請求できる遺留分侵害額に積み増しはないということになります。
参考として、遺留分侵害額の計算方法について説明します。
遺留分侵害額は以下の式で計算します。
| 遺留分侵害額 = 遺留分算定の基礎となる財産の価額 × 総体的遺留分 × 法定相続分 - (遺留分権利者が相続によって得た財産額 - 相続債務分担額)-(特別受益額 + 遺贈を受けた額) |
そして、「遺留分算定の基礎となる財産の価額」は、以下の式で計算します。
| 遺留分算定の基礎となる財産の価額 = 被相続人が相続開始の時において有した財産の価額 + 贈与した財産(一定の要件を満たすもの)の価額 - 相続債務 |
上の式のとおり、「遺留分算定の基礎となる財産の価額」の算定において、寄与分は控除されません。
このように、計算式から見ても、遺贈又は贈与を受けた人の寄与分の有無は遺留分侵害額の算定において影響しないことがわかります。
遺留分を侵害する寄与分の主張は認められるか
寄与分を巡って相続人間で争いが生じた場合は、まずは相続人間で協議し、協議が調わない場合は調停で、調停も調わない場合は審判で、審判での決定に不服がある場合は即時抗告で争うことになります。
民法上は、遺留分を侵害するような寄与分を定めることが禁止されているわけではないため、寄与分の主張が遺留分を侵害していても、遺留分を侵害された人がその主張内容に同意する場合は、寄与分が認められます。
しかし、協議・調停が調わず審判になった場合において、遺留分を侵害する寄与分の主張を裁判所が認めてくれることは実際上ほとんどありません。
例外として認められる可能性があるとすれば、例えば、被相続人の財産のほとんどが寄与分を主張する相続人からの贈与による場合等のように、寄与の割合が特別大きい場合のみでしょう。
遺留分侵害額請求に対して、寄与分を主張することによって、請求を拒んだり、減額を求めたりできるのか
上記のとおり、寄与分は遺留分侵害額の算定にあたって考慮されていないことから、遺留分侵害額請求に対して寄与分を主張しても、法的な効果はないということになります。
もっとも、法的な効果がなくても、寄与があったことを主張することによって、請求者が請求を止めたり、減額に同意すれば、弁済を一部でも免れられる可能性はあります。
この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
ご希望の地域の専門家を探す