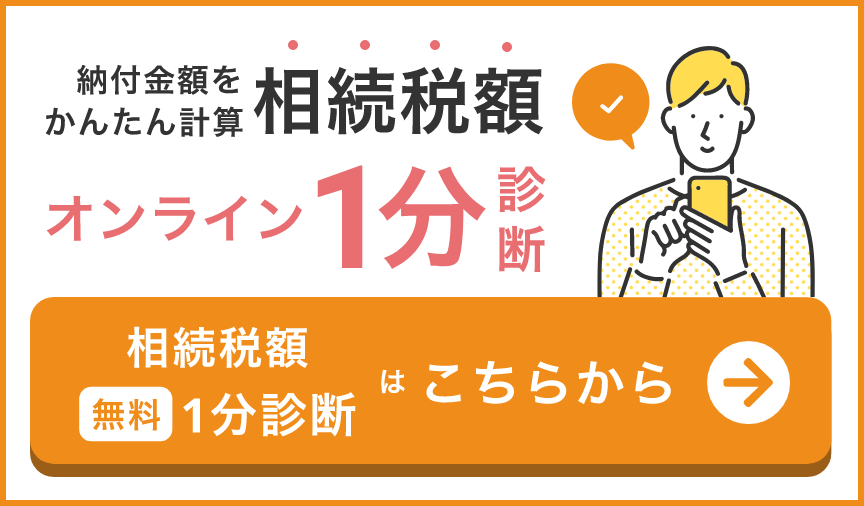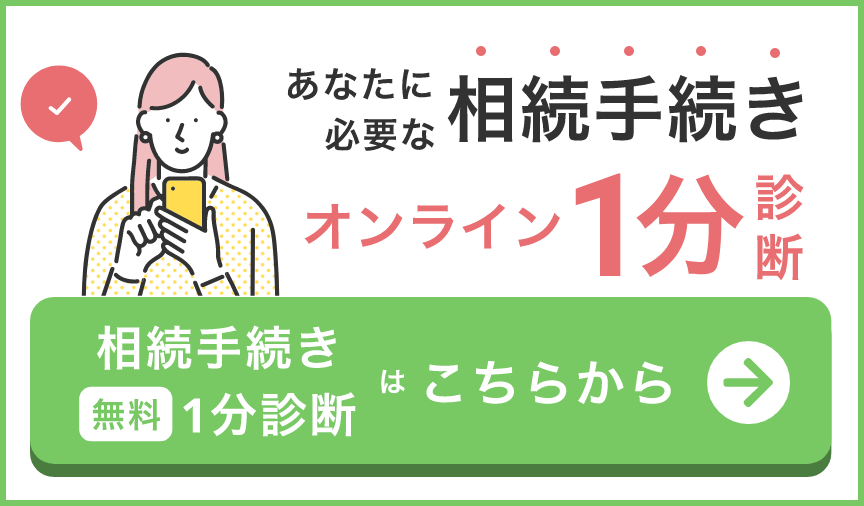死因贈与とは?遺贈との違いは?最適な継承方法を選ぶための全知識

自分の死後、自分の財産を相続人以外の特定の誰かに譲り渡したいときどんな方法があるでしょうか。
それを生前に決めておく方法には、「死因贈与」と「遺贈」という二つの方法があります。
「争族」という言葉があるように、亡くなった方の財産の相続をめぐって親族が争うことは珍しいことではありません。
特に、相続人以外の特定の誰かに譲るとしたら、争族の心配は大きくなるでしょう。
それを事前に避けるためにも、死因贈与と遺贈の内容や、その違い、メリット・デメリットなど、生前に財産の継承者を決めておきたいときに知っておくべきポイントについてご説明します。
[ご注意]
記事は、公開日(2018年7月23日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
目次
1.死因贈与とは
遺産相続における死因贈与とは、被相続人が相続人以外の人に対して、自分が死亡した場合にその人に贈与することを決めた場合、その死因贈与を受け取ることができる制度のことです。
死因贈与は、相続人が生前に自分の意志を明確に示すことで、遺産分割や相続手続きにおいて、遺産分割によるトラブルを回避することができます。ただし、死因贈与は、被相続人が遺産を全て相続人以外に贈与するわけではなく、一部の財産に対してのみ行われます。また、被相続人が生前に贈与した財産は、遺産から除外されます。
遺言等で特段の指定等ないかぎり、死後に財産を譲り受けるのは法定相続人に限られますが、死因贈与の場合は、財産を譲り受ける者に制限はありません。
2.遺贈とは
2-1 遺贈と単なる相続との違い
遺贈とは、亡くなった人(被相続人)が、相続人以外の人に対して、自分が死亡した場合にその人に対して遺産を贈与することを決めることです。つまり、被相続人が自分の死後に、相続人以外の人に対して特定の財産を贈与することを遺贈といいます。
遺贈には、遺言書に明示的に遺贈の旨を記載する必要があります。また、遺贈には一定の制限があり、相続人に対する遺贈については、相続人の持分を上回ることができません。また、遺留分という制度により、法定相続人が遺留分を請求する場合には、遺贈は先に相続分から差し引かれます。
遺贈には、金銭や不動産、株式などの財産だけでなく、自分の思い出の品や文化財など、財産以外のものを贈与することもできます。
死因贈与と同様、財産を譲る相手は、相続人や家族に限られません。
また、人だけでなく、会社等の団体に対して遺贈することもできます。
単なる相続の場合、財産を譲り受けるのは法定相続人に限られますが、遺贈の場合、財産を譲り受ける者は法定相続人に限られません。
また、通常の相続の場合、遺言がないと、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、誰がどの財産を相続するかを決めますが、遺贈は、生前に遺言を作成することによって、自分の死後に財産を譲る相手を指定できるという点に特徴があります。
2-2 包括遺贈と特定遺贈
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。
包括遺贈とは、「全財産の半分を〇〇に遺贈する」というように、特定の財産ではなく、すべての相続財産のうちの割合を示して遺贈することをいいます。
これに対し、特定遺贈とは、特定の不動産や株式等、譲る財産を指定して遺贈する方法です。
特定遺贈は、自宅は〇〇に、A社の株式は△△にというように、譲り渡す財産とその相手を遺言の中で指定する方法で行われます。
3.死因贈与と遺贈の違い
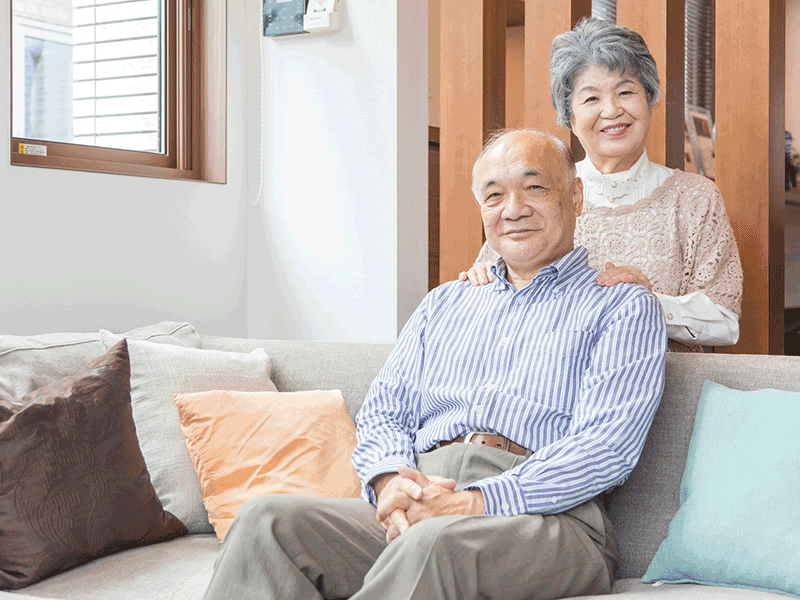
3-1 死因贈与と遺贈の共通点
死因贈与も遺贈も、自分の死後、財産を譲る相手を、生前のうちに決めておく、という点は同じです。
また、財産を譲る相手が、相続人に限られないという点も共通しています。
3-2 死因贈与と遺贈の違い
死因贈与と遺贈の違いを以下の5つに分けて説明します。
- 方式の違い
- 撤回の可否
- 放棄の可否
- 登記の可否
- 税務上の扱い
方式の違い
遺贈は、必ず遺言書を作成して行う必要があります。
また、遺言者が単独でこれを行うことができます。
これに対し、死因贈与は、遺言でこれを行うことはできません。
死因贈与は、その名称のとおり贈与の一種なので、財産を譲る人ともらう人の間で贈与契約を交わす必要があります。
一般的には贈与契約書を作成して行いますが、贈与契約書の作成は必須ではなく、口頭で約束することでも死因贈与は成立します(なお、遺贈は口頭ではできません)。
撤回の可否
一度、遺贈することを決めて遺言書を作成した場合であっても、もし、これを止めたくなった場合には、再度、遺言書を作り直すことで撤回することができます。
有効な遺言書が2通以上あって、その内容が異なっている場合は、後から作成された方の内容が有効になるからです。
民法1022条
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができる。
また、死因贈与についても、契約ではあるものの、その契約の効果がまだ生じていないかぎり、これを相手方の同意なく撤回することは可能です。
この点については、上記の遺贈の規定(民法1022条)が準用されるからです(民法554条)。
民法554条
贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与については、その性質に反しない限り、遺贈に関する規定を準用する。
ただ、死因贈与の中の負担付贈与(例えば、自分の介護をしてもらうかわりに、死後に財産を贈与する場合のように、贈与を受ける側に一定の義務を課す死因贈与)の場合に、既に贈与を受ける側が一定の義務を果たしている場合など一定の場合には、贈与する側が一方的に撤回できない場合があります。
放棄の可否
財産を譲られた側が、これを放棄できるかどうかについては、遺贈と死因贈与で結論が異なります。
遺贈は、通常の相続と同様に、財産を譲り受ける側が一方的にこれを放棄することができます。
しかし、死因贈与は、贈与を受けることを契約で約束していますから、相手の同意なく放棄(契約を破棄)することはできません。
登記の可否
死因贈与の契約において不動産の贈与を受けた場合、不動産の所有者(財産を譲る側)が生きている間に、所有権移転の仮登記を行うことができます(所有者が亡くなった時点で本登記に変更することができます)。
つまり、将来、その不動産の所有権を譲り受ける約束をしていることを登記によって示すことができるのです。
これに対し、遺贈の場合は、不動産の所有者が生きている間に、所有者が亡くなった後に不動産を譲り受ける予定であることを登記で示すことはできません。
あくまで、所有者が亡くなった後に所有権移転登記ができるだけとなります(そのため、所有者が生前にその不動産を売却したり、他の第三者に譲ってしまっていたりした場合は、たとえ遺言があってもその不動産を譲り受けることができない場合があることになります)。
税務上の扱い
死因贈与も遺贈も、所有者が亡くなり、財産を譲り受ける際に相続税が発生するという点に違いはありません。
しかし、不動産取得税と登録免許税については違いが生じます。
遺贈の場合は、遺贈を受ける者が法定相続人である場合は不動産所得税がかからず、法定相続人以外の者が遺贈を受ける場合のみ不動産取得税が発生します(但し、法定相続人以外の者であっても包括遺贈の場合には不動産取得税はかかりません)。
他方、死因贈与の場合は、贈与を受ける側が法定相続人かどうかに関係なく常に不動産取得税がかかります。
また、登録免許税は、法定相続人以外の者が不動産を譲り受ける場合、遺贈であっても死因贈与であっても同じ(固定資産評価額の2.0%)ですが、法定相続人が譲り受ける場合、死因贈与の場合は固定資産評価額の2.0%、遺贈の場合は固定資産税評価額0.4%というような違いが生じます。
| 遺贈 | 死因贈与 | |
|---|---|---|
| 不動産取得税 | 法定相続人または包括受遺者が譲り受ける場合
⇒非課税 法定相続人以外が譲り受ける場合(包括遺贈を除く) ⇒4.0%(標準税率)※ |
常に4.0%
(標準税率)※ |
| 登録免許税 |
法定相続人が譲り受ける場合 ⇒0.4% 法定相続人以外が譲り受ける場合 ⇒2.0% |
常に2.0% |
※2021年3月31日までに取得した土地、住宅については、3%
4.死因贈与のメリット・デメリット
4-1 死因贈与のメリット
死因贈与の最大のメリットは、自分の死後に財産を譲り渡したい相手に、確実に財産を譲ることができるという点です。
また、負担付贈与という形をとることで、財産を譲り渡したい相手に一定の義務を果たしてもらうかわりに財産を譲る、ということが可能になります。
例えば、生前に自分の介護をしてもらうとか、自分の死後、配偶者の面倒をみてもらうとか、自分の死後、ペットの世話をしてもらうといったようなことを、財産を譲り受ける側に約束してもらうことができるのです。
4-2 死因贈与のデメリット
死因贈与は、遺贈に比べて不動産取得税や登録免許税といった税金の点で不利な点があることや、きちんと契約書を残しておかないと後でトラブルになってしまうという点がデメリットといえるでしょう。
5.遺贈のメリット・デメリット
5-1 遺贈のメリット
遺贈の最大のメリットは、死因贈与と同様、自分の死後、誰にどの財産を譲るかということを指定することができるという点です。
ただ、死因贈与と異なり、遺贈は、遺贈を受けた側が放棄することもでき、必ずしも遺贈した方の意思どおりになるとは限らない点に注意が必要です。
また、自分が死ぬまで、誰に財産を譲るかを秘密にしておきたいときは、死因贈与より遺贈の方が適しているといえるでしょう。
5-2 遺贈のデメリット
遺贈は、遺言という形でしか行えないというように、その方法が限定されているという点がデメリットでしょう。
特に、遺言は、作成日付が欠けていたり、署名・押印が欠けていたりするだけで無効になってしまう可能性があるという点に注意が必要です。
6.死因贈与の注意点

6-1 契約が成立しているか
死因贈与をする場合に注意しなければならないのは、死因贈与が契約の一種であるということです。
契約である以上、財産を譲り受ける側の同意がないと成立しないという点に注意が必要です。
なお、契約は口頭の約束でも有効に成立しますが、財産の所有者が亡くなった後に、契約が成立していることをきちんと証明するためにも契約書を作成しておいた方がよいといえます。
6-2 遺留分を侵害していないか
法定相続人には、法定相続分の2分の1については、常に相続をする権利(これを遺留分といいます)があります。
この遺留分を侵害してしまうと、法定相続人から財産を譲り受けた者に対して、遺留分の請求がなされる可能性があるので注意が必要です。
例えば、配偶者と子供が2人いる方が、死後、自分の兄に全財産を譲るという死因贈与契約をした場合、配偶者には4分の1、子供には8分の1(法定相続分は配偶者が2分の1、子供がそれぞれ4分の1)の遺留分が認められるので、全財産を譲り受けた兄は、亡くなった方の配偶者や子らから遺留分を請求される可能性があるのです。
7.遺贈の注意点

7-1 受贈者の承諾
遺贈は、遺言によって単独で行うことができるので、遺贈を受ける側(受遺者といいます)の承諾は必要ありません。
ただ、法定相続人でない方に遺贈をしたり、法定相続人であっても法定相続分を超える遺贈をする場合は、他の相続人とトラブルにならないよう、事前に遺贈を受ける側(受遺者)に伝えてその承諾を得ておいた方が良い場合があります。
7-2 遺言執行者の指定
不動産を遺贈した場合、遺贈を受けた側は、所有者の死後に所有権移転登記をする必要がありますが、所有者が遺言によって遺言執行者を指定していないと、法定相続人全員の協力が必要になります。
遺言執行者の指定は必須ではありませんが、指定しておいた方が、遺贈を受けた側がスムーズに登記手続することができるといえます。
7-3 遺留分への配慮
死因贈与の場合と同様、遺贈においても、法定相続人の遺留分に配慮する必要があります。
遺贈によって、法定相続人の遺留分を侵害してしまうと、遺贈によって財産を譲り受けた者に対し、法定相続人から遺留分の請求がなされる可能性があるからです。
8.死因贈与や遺贈について専門家に相談したいときは
死因贈与も遺贈も、生前に、自分の死後に財産を譲る相手を決めておく方法です。
ただ、死因贈与では、契約が成立しているかどうか問題になったり、遺贈では遺言が有効に成立しているかどうか問題になったりする可能性があり、せっかく自分の死後の相続トラブルを回避するために死因贈与や遺贈を行ったのに、かえってトラブルが生じてしまう可能性も否定できません。
また、死因贈与と遺贈にはそれぞれメリットとデメリットがあるので、財産の状況等によっていずれを選択した方がよいか微妙な場合もあります。
ですから、自分の死後の相続トラブルを確実に回避するとともに、財産を譲る側にとっても、譲り受ける側にとっても最適な継承方法を選択するためには、専門家のアドバイスを受けたうえで死因贈与や遺贈を行った方がよい場合が多いでしょう。
まとめ
自分の死後に財産を譲り渡す方法としては、遺言書を作成するという方法が最も知られている方法ですが、場合によっては、遺言書による遺贈ではなく、死因贈与を選択した方がよい場合も少なくありません。
死因贈与と遺贈のいずれが適しているかは、その方の財産の状況等によって異なってきますが、遺言による遺贈以外にも死因贈与という方法があることを知っておくだけでも、自分の財産の継承方法を検討する際にプラスになるのではないでしょうか。
この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
ご希望の地域の専門家を探す