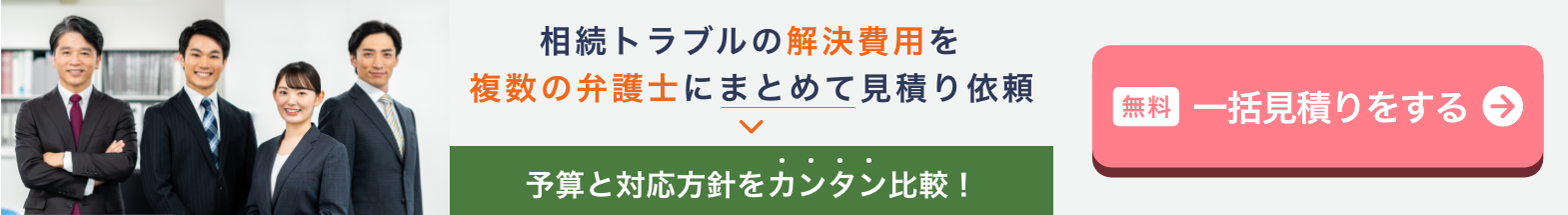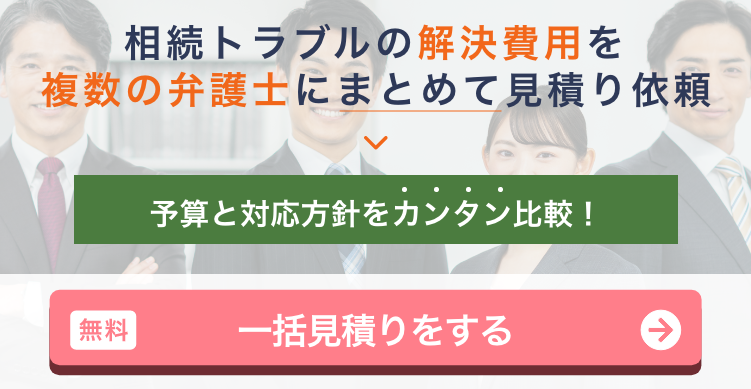相続放棄後の取り立ての撃退法をわかりやすく伝授!

[ご注意]
記事は、公開日(2020年7月22日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
相続放棄後の取り立てには相続放棄の証明書を提出しよう
相続放棄が受理されたのにもかかわらず、亡くなった人の債権者から取り立てがあった場合は、相続放棄申述受理通知書のコピー又は相続放棄申述受理証明書を債権者に提出しましょう。 相続放棄申述受理通知書は、相続放棄が受理された時に家庭裁判所から送付されているはずです。 相続放棄申述受理通知書は再発行ができないので、原本ではなくコピーを提出しましょう。 原本の提出を求められた場合は、相続放棄申述受理証明書を提出しましょう。 相続放棄申述受理証明書は、相続放棄の申述をした本人が、相続放棄の手続きを行った家庭裁判所にその発行を求めることができます。 家庭裁判所に相続放棄申述受理証明書の発行を求めるときは、「相続放棄申述受理証明申請書」に必要事項を記載して、家庭裁判所に提出します。 申請書の書式はこちらから、記入例はこちらから、閲覧、ダウンロードすることができます。 なお、1通あたり150円の費用がかかります(収入印紙で家庭裁判所に納めます)。 相続放棄申述受理証明書の申請は、本人による申請が原則のため、本人確認書類(運転免許証や住民票等)の提示(郵送の場合はコピーの同封)を求められます。 証明書を窓口で受け取るのではなく郵送して欲しいときには、返信用の切手も併せて裁判所に提出する必要があります。 相続放棄申述受理証明書は、何通でも発行を求めることが可能です。 最初から複数枚発行を申請することもできますし、紛失した場合等に再度発行を求めることもできます。それでも取り立てが続く場合の対処法
相続放棄申述受理通知書のコピー又は相続放棄申述受理証明書を提出しても取り立てが続く場合、その取り立ては違法なものであり、無視しても構いません。 取り立てが止まない場合や、不安な場合は、警察署に相談するとよいでしょう。 警察が応じてくれない場合は、弁護士に相談することをお勧めします。 相続放棄の手続きを弁護士に依頼した場合は、その弁護士に相談するとよいでしょう。 相続放棄を弁護士に依頼していない場合は、当サイト等を利用して弁護士を探して相談するとよいでしょう。 多くの事務所が無料相談に応じています。債権者が相続放棄の無効を主張してきた場合
債権者が相続放棄の無効を主張してくることがありますが、債権者は裁判をして相続放棄の無効を確認する判決等を得なければ、正当に取り立てることはできません。 債権者が相続放棄の無効を主張してきた場合は、裁判になった場合に備えて、早めに弁護士に相談することをおすすめします。この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
ご希望の地域の専門家を探す