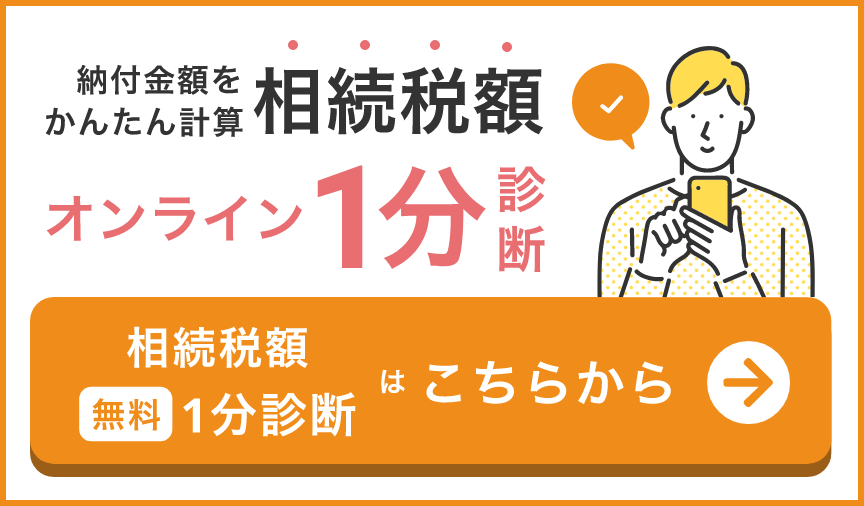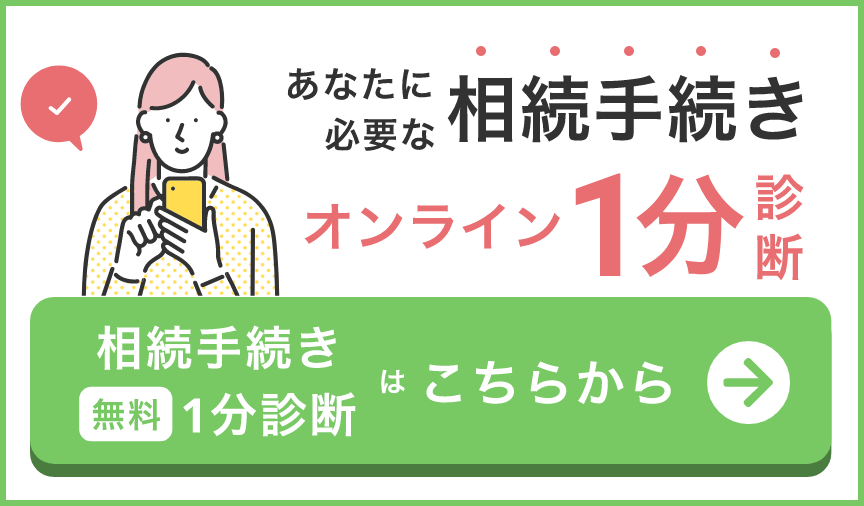特別受益で相続分を減らされないための重要知識

生前贈与や、遺贈で相続人の中の特定の人が財産を譲り受けたとしても、他の相続人から特別受益を主張され相続分を減らされてしまうことがあります。
また反対に、他の相続人が生前贈与や、遺贈で特定の人が財産を譲り受けていたら、特別受益を主張することによって相続分を増やすこともできます。
この記事では、生前贈与や遺贈を考えている人も、受贈する人も、それに関係する相続人も、どの立場の人でも知っておいた方がよい特別受益について分かりやすく説明します。
是非参考にしてください。
相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください
[ご注意]
記事は、公開日(2018年9月4日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
特別受益とは?
特別受益とは、相続人が複数いる場合に、一部の相続人が、被相続人からの遺贈や贈与によって特別に受けた利益のことです。
特別受益があった場合は、特別受益の価額を相続財産の価額に加えて相続分を算定し、その相続分から特別受益の価額を控除して特別受益者の相続分は算定されます。
このようにして相続分を算定することを特別受益の持戻しといいます。
特別受益持ち戻しの計算例
例えば、被相続人には配偶者はおらず、AとBの2人の子がいたとします。
Aには1000万円の生前贈与を行っており、また、相続財産の価額は2000万円であったとします。
この場合における特別受益の持戻し後のA、Bそれぞれの相続分は1/2なので次の式で計算することができます。
- Bの相続分:(2000万円+1000万円)÷2=1500万円
- Aの相続分:(2000万円+1000万円)÷2-1000万円=500万円
なお、相続分以上に特別受益があったとしても返金する必要はありません。相続分がゼロになるだけです。
例えば、先ほどの例で、Aの特別受益が3000万円であったとします。
そうすると、Aの相続分が以下のようにマイナスになってしまいます。
(2000万円+3000万円)÷2-3000万円=-500万円
このような場合、Aは相続分はなくなってしまいますが、500万円を返す必要はないということです。
特別受益の範囲は?
特別受益の概要はおわかりいただけたかと思いますが、次に、特別受益の範囲はどこからどこまでなのかという疑問が生じるでしょう。
この点について、民法903条1項には次のように定められています。
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
特別受益の範囲については、「遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた」と定められています。
遺贈については、条件が付けられていませんから、遺贈によって取得した財産は、すべて特別受益に含まれます。
死因贈与も遺贈と同様にすべて特別受益に当たると考えて差し支えありません。
生前贈与については、すべての贈与が特別受益となるわけではなく、次の3つの目的で行われた贈与が特別受益に当たるとされています。
- 婚姻のための贈与
- 養子縁組のための贈与
- 生計の資本としての贈与
以下、それぞれについて説明します。
相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください
1.婚姻のための贈与
婚姻のための贈与は額面通りすべて特別受益に当たるのかというと、そういうわけではありません。
婚姻のための贈与であっても特別受益に当たらないとされているものもあります。
そもそも、特別受益の制度趣旨は、遺産の前渡しによる不公平を是正することにあります。
婚姻のための贈与であっても、遺産の前渡しとは言えないようなものであれば、特別受益には当たらないとされます。
また、生計の資本としての贈与と並列関係になっていることからも、生計の資本としての贈与と比べても遜色がないくらいのまとまった金額であることが、特別受益に当たるとするためには必要であると考えられます。
ですので、挙式費用については特別受益に当たらず、結婚後の生活をサポートするための贈与は特別受益に当たるという解釈が可能です。とはいっても、贈与の名目だけで、一概に特別受益に当たるかどうかを判断することはできまません。判断に迷うときは税理士などの専門家に相談しましょう。
主催者である親が挙式費用を負担するのは当然であり、特別受益には当たらないと考えられてきました。しかし、時代は変わり、今では、本人が主催する結婚式の方が多いでしょう。また、挙式にかかる費用も人それぞれになってきました。
そうすると、兄の時はあまり挙式費用がかからず親からの援助も少額であったのに、弟の時は本人が豪華な結婚式を行ったため親も多額の援助をしたというケースもあり得ます。
そのような場合にまで、挙式費用は特別受益には当たらないと言い切ってよいかは疑問の余地があるように思われます。
挙式費用が伝統的に特別受益に当たらないとされてきた背景には、従前は、結婚式は、親が主催し、親が客を招待するものであったことが関係しています。
主催者である親が挙式費用を負担するのは当然であり、特別受益には当たらないと考えられてきました。しかし、時代は変わり、今では、本人が主催する結婚式の方が多いでしょう。また、挙式にかかる費用も人それぞれになってきました。
そうすると、兄の時はあまり挙式費用がかからず親からの援助も少額であったのに、弟の時は本人が豪華な結婚式を行ったため親も多額の援助をしたというケースもあり得ます。
そのような場合にまで、挙式費用は特別受益には当たらないと言い切ってよいかは疑問の余地があるように思われます。

2.養子縁組のための贈与
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組がありますが、普通養子縁組の場合は、実親と養親の両方の相続人となることができ、特別養子縁組の場合は、実親の相続人となることはできず、養親に対してのみ相続人となることができます。
普通養子縁組に出す際に、実親が持参金として贈与することがありますが、この贈与は特別受益に当たります。
また、養子と特別受益に関する論点として、養子縁組前の養親からの贈与が特別受益に当たるかという点があります。
この点について、養子縁組前であっても、相続人間の公平の観点から、特別受益に当たるとされる余地は十分にあります。
3.生計の資本としての贈与
生計の資本というぐらいですから、お小遣いや交遊費程度の金額の贈与は含まれないでしょう。
扶養の範囲内の生活費の援助も特別受益には当たりません。
扶養の範囲を超える援助は特別受益に当たります。
学費についても一般的な私立大学の学費ぐらいまでは、通常、特別受益に当たらず、私立の医学部や長期留学費用となると、特別受益に当たる可能性があります。
しかし、これもケースによりけりで、例えば、他の兄弟が自分のお金で定時制高校に通ったのに、一人だけ私立大学に行かせてもらったとしたら、医学部でなくてもその学費は特別受益に含まれる余地はありそうです。
このほか、開業資金やマイホームの取得資金の贈与も特別受益に含まれる可能性があるでしょう。
また、金銭だけでなく、土地や建物の贈与も特別受益に当たりえます。
贈与でなくても、土地や建物を無償で貸してあげた場合も特別受益に当たる可能性があります。

特別受益に時効はある?
贈与の期間については、特に定められていません。
被相続人が亡くなる10年前の行われた贈与でも、50年前でも特別受益に当たる可能性があります。
「特別受益に時効はありますか?」という質問を受けることがありますが、特別受益に時効はありません。
ただし、2019年7月1日に法改正があり、遺留分の算定において価額を算入できるのは特別受益に当たる贈与であっても相続開始前10年以内のものに制限されることになりました(改正前に開始された相続には適用されません)。
相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください
持戻しの免除とは?
被相続人が特別受益の持戻しを免除する意思を表示した場合は、持戻しは免除されます。
特別受益の持戻しの免除とは、特別受益の持戻しをさせないことです。
特別受益の持戻しがあると、贈与財産の価額が控除されますが、持戻しが免除されると、控除されません。
冒頭のAに1000万円の生前贈与を行った例でいうと、Aの相続分が500万円、Bの相続分が1500万円でしたが、持戻しが免除されると、相続分はAもBも1000万円ずつになります。
持ち戻しの伝え方にきまりはある?
持戻し免除の意思表示の形式に指定はありません。
ですが、遺贈による特別受益の持戻しの免除は、同じく遺言によるべきとする見解もあるので、念のため、遺言によって行うべきでしょう。
贈与による特別受益の持戻しの免除は、遺言で行う必要はありません。
明示の意思表示は勿論、黙示の意思表示も認められます。
ですが、黙示の意思表示は、しばしば相続人間におけるトラブルを引き起こします。
黙示の意思表示の有無で相続人同士が揉めることがあるのです。
黙示の意思表示が有無については、総合的に判断されますが、次のような事情があれば、意思表示があったと認められやすいでしょう。
- 受贈者(贈与を受ける人)により多くの財産を与えようという被相続人の意図がある場合
- 贈与の代わりに被相続人も利益を得ている場合
しかし、被相続人の立場としては、死後に相続人間でトラブルにならないように、明示の意思表示をしておいた方がよいでしょう。
持ち戻し免除、取り消せる?
なお、被相続人は免除の意思を表示した後でも自由にこれを撤回することができます。
また、免除があったとしても贈与や遺贈が遺留分を侵害する場合は、遺留分を侵害された相続人は遺留分減殺請求を行うことができます。
相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください
特別受益者と寄与者が同一人の場合
寄与分とは?
前述の通り、特別受益者は相続分から特別受益分を控除されます。
特別受益の分、相続財産が減ってしまっているので、その分を控除することによって、相続人間の公平が保たれるのです。
しかし、反対に、相続財産が増えるような寄与や、相続財産が減らないような寄与をした場合は、その寄与分を相続分に加えて取得することができます。
例えば、被相続人に配偶者はおらず、AとBの2人の相続人がいて、Aは被相続人の生前に長年に渡って被相続人の介護を行ってきたとします。
もしAが介護を行わずに、被相続人が老人福祉施設に入居していたら、入居費用等によって相続財産が減っていたと考えられます。
仮に相続財産が2000万円でAの寄与分が1000万円であった場合は、AとBの最終的な相続分は次の式で計算することができます。
- Aの相続分:(2000万円-1000万円)÷2+1000万円=1500万円
- Bの相続分:(2000万円-1000万円)÷2=500万円
特別受益者と寄与者が同一人の場合の計算方法
特別受益者と寄与者が同一人であることもあります。
その場合は、まず、特別受益の価額を控除し、それから寄与分の価額を加えます。
この計算順序は、特別受益の価額が、現実の相続財産による相続分の価額を上回る場合に生きてきます。
特別受益の価額が現実の相続財産による相続分の価額を上回っても、マイナスにならないためです。
どういうことか、例を基に説明します。
特別受益者と寄与者が同一の場合の計算例
先ほどの例で、Aの特別受益が2000万円の場合の最終的な相続分は次のように計算することができます。
- 配偶者なし、子ども2人(AとB)
- 相続財産2000万円
- Aは特別受益2000万円有り、寄与分1000万円
まず、現実の相続財産2000万円に特別受益の2000万円を加え、寄与分の1000万円を差し引きます。
そうすると、みなし相続財産は、3000万円になります。
3000万円をAとBの2人の相続人で分けると、1500万円ずつになります。
Aは特別受益が2000万円あるので、1500万円から2000万円を差し引きます。
そうすると、マイナス500万円になりますが、いくら特別受益があってもマイナスにはならない決まりなので、この時点では、Aの相続分はゼロになります。
Bの相続分は1500万円のはずでしたが、実際に分配することができる相続財産は、現実の相続財産2000万円から寄与分1000万円を差し引いて1000万円なので、Bの相続分は1000万円になります。
そして、Aには1000万円の寄与分があるので、Aの相続額も1000万円になります。
寄与分を遺言で決められる?

どこまでの贈与が特別受益に含まれるかという点で、相続人間で揉めることがあることは前述の通りですが、寄与分についても同様です。
相続人の行為が、相続財産の増加や維持に寄与しているのかどうか、また、寄与があったことは認められたとして、その寄与分の価額はいくらが相当なのか、寄与分を主張する相続人と、寄与分の主張を退けたい他の相続人で揉めることがあります。
そこで、寄与分を遺言で決められないかという疑問が生じます。
この点について、結論としては、遺言で決めることはできません。
優先して財産を渡したい相続人がいる場合は、遺言で寄与分を定めるのではなく、遺贈や贈与によるべきですが、遺贈や贈与に対しては遺留分減殺請求が認められますが、寄与分に対しては、遺留分減殺請求は認められないという違いがあります。
▼遺留分について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼
▼寄与分について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼
特別受益があった場合の流れ
特別受益に当たる遺贈や贈与があったとしても、それを他の相続人が主張しなければ、特別受益は考慮されません。
遺贈の場合は明白ですから、他の相続人は特別受益を主張しやすいのですが、贈与の場合は、前述の通り、揉めることが結構多いです。
まず、他の相続人に対して贈与があったことを、預貯金口座の履歴等から洗い出さなければなりません。
そして、その贈与が特別受益に当たることを主張し、贈与を受けた相続人がその主張を認めない場合は、特別受益に当たることを立証しなければなりません。
特別受益で揉めると裁判に
協議で解決できない場合は、遺産分割調停を被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に申立て、調停でもまとまらない場合は、遺産分割審判に移行し、審判が下されます。
審判の結果に不服がある場合は、審判の告知を受けた日の翌日から2週間以内に、審判を下した家庭裁判所を管轄する高等裁判所に対して、即時抗告の申立てを行うことができます。
即時抗告に対する決定に不服がある場合は、最高裁判所に対して特別抗告や許可抗告を行うことができますが、これが認められるのは、決定の内容に憲法違反があったり、決定の内容が過去の最高裁判所の判例と異なる見解に基づいているような、極めて限られたケースに留まります。
相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください
特別受益証明書とは
最後に特別受益証明書について説明します。
特別受益証明書は相続分不存在証明書とも呼ばれ、相続登記の際に、相続人が登記しようとしている不動産を相続したことを法務局に対して証明するために用いられる書類です。
不動産を遺贈によって取得した場合は、登記の際に遺言書を証明書として用います。
相続によって取得した場合は、遺産分割協議書を証明書として用いることが多いですが、他の相続人が遺産を欲しない場合等、遺産分割協議自体を行わないこともあります。
そのような場合は、遺産分割協議書は当然ながら作成されないため、登記のための証明書に困ることになります。
他の相続人が全員相続放棄していれば、相続放棄受理証明書か相続放棄受理通知書によって登記を行うことができます。
しかし、相続放棄の手続きも手間ではあるので、相続放棄をしていないケースもあります。
そのような場合に用いられるのが、特別受益証明書です。
これは、特別受益があるために相続分がないことを証する書面です。
この特別受益証明書と特別受益者の印鑑証明書があれば、登記手続きを行うことができます。
まとめ
以上、特別受益によって相続分を減らされないための全知識について説明しました。
わからないことは税理士などの専門家に相談するなどして、特別受益で損しないようにしましょう。
相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください
この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
ご希望の地域の専門家を探す