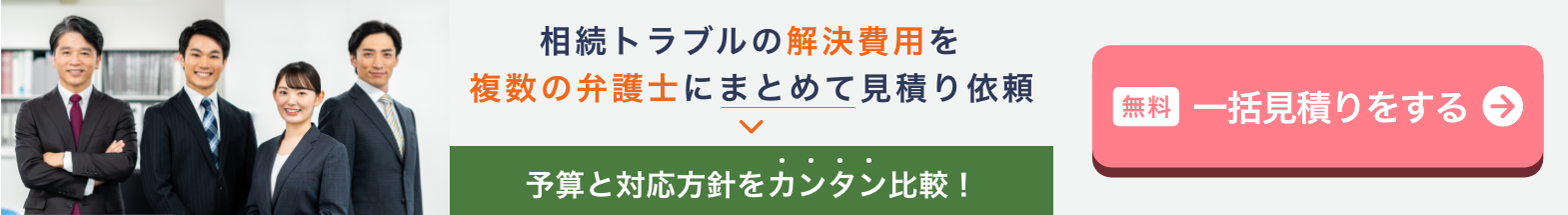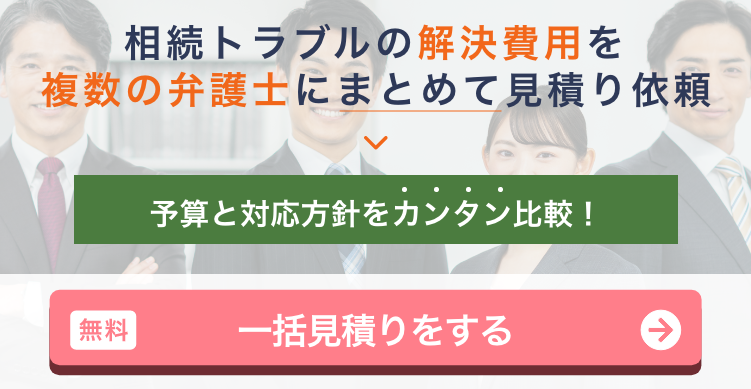限定承認の手続きの流れと方法・費用について説明!

[ご注意]
記事は、公開日(2020年7月31日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
限定承認の手続きの流れ
限定承認の手続きは、およそ次のような流れで進みます。- 申述書および財産目録の作成
- 添付書類(戸籍謄本等)の準備
- 限定承認の申述
- 必要に応じて照会への回答や資料の補完
- 限定承認受理通知書の受領
- 官報公告
- 請求申出の催告
- 必要に応じて鑑定人選任申立て、先買権の行使
- 相続財産の換価
- 相続債権者および受遺者への弁済
- 残余財産があれば遺産分割および相続財産の取得
限定承認の申述
申述書(申立書)、目録、添付書類が用意出来たら、被相続人の最終住所地を管轄する家庭裁判所に限定承認の申述を行います。 全国の家庭裁判所の所在地と電話番号は、裁判所のこちらのページから確認することができます。 費用は、伸長申立てと同様、800円(相続人1人につき)の収入印紙と切手代(1000円程度)です。 なお、申述が受理されたら、相続人が複数名いる場合は、相続財産管理人を家庭裁判所が選定することになりますが、申述時に誰々を相続財産管理人に選んでくださいという上申書を併せて提出することもできます。必要に応じて照会への回答や資料の補完
裁判所から照会があることがあるので、対応します。 相続財産管理人についての上申書を提出していない場合は、裁判所から相続財産管理人を誰にしますかという照会があることもあります。限定承認受理通知書の受領
限定承認が受理されると通知書が送られてくるので、受領します。 その後の清算手続きは、相続人が限定承認申述人だけの場合は限定承認申述人が、相続人が複数いる場合は家庭裁判所が選任した相続財産管理人が進めることになります。官報公告
限定承認したことと、債権者や受遺者に対して弁済の請求を一定期間内に申出るべきことを官報に公告します。請求申出の催告
連絡先が分かっている相続債権者には、内容証明郵便で直接催告します。 配達証明付きの内容証明郵便を利用するとよいでしょう。必要に応じて鑑定人選任申立て、先買権の行使
この後、債務の弁済に充てるために相続財産の換価手続きを進めますが、その前に、相続人が欲しい相続財産は、相続人が買い受けることができます。 希望する場合は、家庭裁判所に鑑定人の選任を申立てて、鑑定された金額でその相続財産を買い受けることができます。相続財産の換価
相続財産を競売にかけて、お金に換えていきます。相続債権者および受遺者への弁済
換価した相続財産から請求を申し出た相続債権者や受遺者に弁済していきます。 受遺者よりも相続債権者が優先です。 相続財産が足りない場合は、債権者ごとに債権額の割合に応じて案分して弁済します。残余財産があれば遺産分割および相続財産の取得
債権者と受遺者への弁済後、残った財産があれば、相続人が取得します。 相続人が複数いる場合は、遺産分割します。 なお、期間中に請求を申し出なかった債権者や受遺者が、後から請求を申し出てくることがありますが、その場合は、残余財産から弁済しなければなりません。限定承認の必要書類
限定承認の必要書類は次のとおりです。- 申述書
- 目録
- 戸籍謄本等
申述書
申述書の用紙はこちらのページからダウンロードできます。 また、記入の際は、こちらの記入例を参考にしてください(以下の目録の記入例を兼ねています。)。目録
目録は、4つの種類の書式があるので、以下のリンクからそれぞれダウンロードして使用してください。戸籍謄本等
必要な戸籍謄本等は、申述人が誰かによって異なります。 以下、ケースごとに紹介します。共通
- 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
- 申述人全員の戸籍謄本
- 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
(配偶者と)父母・祖父母等(直系尊属)の場合
被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人と同じ代及び下の代の直系尊属に限る(例:相続人祖母の場合、父母と祖父))がいらっしゃる場合、その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本配偶者のみの場合、又は被相続人の(配偶者と)兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合
- 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
- 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合、そのおい又はめいの死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
限定承認の手続きはすべての相続人が共同で行わなければならない
限定承認の手続きはすべての相続人が共同で行わなければなりません。 単純承認した人や相続放棄をした人がいる場合は、限定承認の手続きをとることはできません。限定承認の手続きは弁護士又は司法書士に依頼できる
限定承認と手続きは相続放棄と比べて複雑です。 一般の方が専門家の力を借りずに進めることは大きな負担になるでしょう。 弁護士又は司法書士に依頼することをお勧めします。 専門家に依頼した場合は、遺産額にもよりますが、最低50万円ほどの料金がかかるでしょう。 それなりの金額ではありますが、限定承認の手続きは一般の方が独力で臨むには極めてハードルが高いので、まずは、一度、専門家に相談してみるとよいでしょう。 相談したからといって必ず依頼しなければならないわけではありません。 無料相談に応じている専門家も多いので、気軽に相談してみるとよいでしょう。まとめ
以上、限定承認の手続きについて説明しました。 上記のとおり、限定承認の手続きは、一般の方が独力で行うには無理があります。 まずは専門家に相談してみることをお勧めします。 限定承認にはデメリットもあるため、相続放棄とどちらがよいかも含めて専門家に相談するとよいでしょう。この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
ご希望の地域の専門家を探す