株の贈与税はいくら?株式の評価方法と贈与税額の計算方法を説明

相続税対策のひとつとして、生前贈与を検討することもあるでしょう。生前贈与は現金や不動産だけでなく、株式もできるのをご存知ですか?
ですが生前贈与をする前に、どのようにすれば節税できるのかを十分に検討する必要があります。なぜなら生前贈与の金額によっては、多額の贈与税がかかるからです。
この記事では、生前贈与の税率や相続との違い、株式の評価方法について、詳しく解説していきます。
ちなみに、株式は上場株式か非上場株式かで評価方法が異なります。そちらも解説しますが、株式の評価は難しいので、税理士に依頼したほうが無難かもしれません。
目次
[ご注意]
記事は、公開日(2019年12月9日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
贈与税の課税方式
贈与税の課税方式には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、贈与を受けた人が、どちらの方式で贈与税を計算するかを贈与者ごとに贈与税の申告時に選択することができます(ただし、一度、相続時精算課税を選択した贈与者からの贈与については翌年以降暦年課税を選択することはできません)。
暦年課税方式では、贈与税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。
相続時精算課税方式では、2,500万円まで贈与税が非課税になります。
贈与税はかかりませんが、相続時には、この制度により取得した贈与財産とその他の相続財産とを合わせた遺産総額に相続税が課税されるので、注意が必要です。
なお、2,500万円を超える部分については、一律20%の贈与税が課せられます。
この記事では、暦年課税方式による贈与税の計算方法について説明します。
相続問題でお悩みの方は
まずは弁護士にご相談ください
贈与税の計算方法
暦年課税方式では、贈与税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に譲り受けた財産の合計額に対して課税されます。1年間に譲り受けた財産の合計額から基礎控除額である110万円を引いた額(これを課税価格といいます)に、税率をかけて、さらに一定の金額を控除するという方法で計算されます。贈与税の計算式は以下のとおりになります。
暦年課税方式による贈与税の税率は、特例贈与財産と一般贈与財産とで異なり、特例贈与財産の方が税率が低く設定されています。
特例贈与財産とは、直系尊属(親や祖父母等)から、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の直系卑属(子や孫等)への贈与財産のことで、一般贈与財産とは、特例贈与財産に該当しない財産のことです。
一般贈与財産用の税率(一般税率)の速算表
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | - |
| 200万円超300万円以下 | 15% | 10万円 |
| 300万円超400万円以下 | 20% | 25万円 |
| 400万円超600万円以下 | 30% | 65万円 |
| 600万円超1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
| 1,000万円超1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
特例贈与財産用の税率(特例税率)の速算表
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | – |
| 200万円超400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 400万円超600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 600万円超1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,000万円超1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 1,500万円超3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 3,000万円超4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
計算事例
例えば、30歳のAさんが、ある年の1年間に父母や祖父母といった直系尊属から受けた贈与の総額が1,000万円であったとします。
Aさんは、どの贈与者からの贈与についても暦年課税を選択したとします。
1,000万円から暦年課税の基礎控除額110万円を控除すると、「1,000万円-110万円=890万円」となります。
贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上の人が直系尊属から贈与された財産は特例贈与財産に該当するので、特例税率の速算表に沿って贈与税額を計算します。
890万円は、「600万円超1,000万以下」に該当するので、税率30%と控除額90万円を適用します。
そうすると、「890万円×30%-90万円=177万円」が贈与税額となります。
計算事例(特例贈与財産と一般贈与財産の両方がある場合)
Aさんは、ある年の1年間に、直系尊属から600万円、直系尊属以外の人から400万円、合計1,000万円の贈与を受けたとします。
この場合は、特例贈与財産と一般贈与財産の両方があることになります。
その場合は、次の手順で計算します。
- すべての財産を「一般税率」で計算した税額に占める「一般贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。
- すべての財産を「特例税率」で計算した税額に占める「特例贈与財産」の割合に応じた税額を計算します。
- 1で算出した税額と、2で算出した税額を合計して、贈与税額を計算します。
※1と2はどちらを先に計算しても構いません。
上記の事例をこの計算手順に当てはめて計算してみましょう。
まず、1の税額を計算します。
最初に、すべての財産を一般税率で計算します。
基礎控除後の課税価格890万円(=1,000万円-110万円)を一般税率の速算表に当てはめると、600万円超1,000万円以下の行を見ればよいので、税率が40%で、控除額が125万円であることが分かります。
そうすると、すべての財産を一般税率で計算した税額は、「890万円×40%-125万円=231万円」となります。
そして、この231万円に占める一般贈与財産の割合に応じた税額を計算します。
Aさんがその年に贈与を受けた1,000万円のうち、一般贈与財産は、直系尊属以外の人から受けた400万円なので、1の税額は、「231万円×400万円/1,000万円=92万4千円」となります。
続いて、2の税額も同様に計算すると、「177万円×600万円/1,000万円=106万2千円」となります(177万円は、特例税率の速算表に沿って「890万円×30%-90万円=177万円」と計算できます)。
3に進んで、Aさんがその年に納めるべき贈与税額は、「92万4千円+106万2千円=198万6千円」となります。
贈与税計算シミュレーションツール(贈与税計算機)
贈与税の計算方法を理解しなくても、贈与税計算シミュレーションツール(贈与税計算機)を利用することで、贈与税の税額を簡単に算出することができます。
以下のリンクからご利用ください。
株の評価方法
各相続財産の価額が分からなければ贈与税額を計算することはできません。相続税の計算には、相続税評価額を用います。
株の相続税評価額の評価方法は、上場株式と非上場株式とで異なります。以下、それぞれについて説明します。
上場株式の評価方法
上場株式の評価は、原則として終値(おわりね)によって行います。終値とは、大引け(おおびけ。その日の最後の取引)でついた株価のことです。
次の4つのうち、最も低い株価で評価します。
- 贈与日の終値
- 贈与日の当月のすべての営業日の終値の平均
- 贈与日の前月のすべての営業日の終値の平均
- 贈与日の前々月のすべての営業日の終値の平均
これらの終値(および終値の平均)は、取引を行っていた証券会社の発行する残高証明書の参考資料で確認することができます。
なお、上場株式の生前贈与は相続税対策として有効な場合がありますが、この点については後述します。
非上場株式の評価方法
非上場株式の評価方法は、経営権を支配する場合と支配しない場合によって異なります。
経営権を支配する場合
経営権を支配する場合は、さらに会社の規模によって異なります。
大会社の場合
大会社の場合は、類似業種比準方式といって、事業内容が類似する複数の上場会社の株価の平均値等の各種数値を基準に計算されます。
小会社の場合
小会社の場合は、純資産価額方式といって、相続開始日に会社を清算したと仮定して株主一人当たりの分配額で計算されます。
具体的には、会社の総資産や負債を、原則として相続税の評価に洗い替えて、その評価した総資産の価額から負債等の金額を差し引いた残りの金額により評価します。
中会社の場合
中会社の場合は、併用方式といって、類似業種比準方式で計算した株価と純資産価額方式で計算した株価を一定割合で折衷して計算します。
会社規模が大会社に近づくほど類似業比準価額方式で算定する割合が大きくなります(純資産価額方式で算定する割合が小さくなります)。
各方式による具体的な計算方式については、税理士にご相談ください。
なお、事業承継税制によって、贈与税の納税猶予・免除を受けることができますが、この点については後述します。
経営権を支配しない場合
経営権を支配しない場合は、配当還元方式といって、次の式で計算されます。
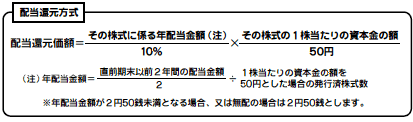
事業承継税制によって贈与税の納税猶予・免除を受けるための要件
事業承継税制によって贈与税の納税猶予・免除を受けるための主な要件について説明します。
会社に関する要件
次の会社のいずれにも該当しないことが事業承継税制の適用を受けるための要件です。
- 上場会社
- 中小企業者に該当しない会社
- 風俗営業会社
- 資産管理会社(一定の要件を満たすものを除きます。)
中小企業者に該当するのは、業種分類に応じて次のとおりです。
| 業種分類 | 中小企業者に該当する者 |
|---|---|
| 製造業その他 | 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が300人以下の会社 |
| 卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社 |
| 小売業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が50人以下の会社 |
| サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社又は 常時使用する従業員の数が100人以下の会社 |
資本金の額がこの要件に該当しない場合(超えている場合)でも、事前に減資することによって、中小企業者となり、事業承継税制の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、事業承継税制に精通した税理士に確認するとよいでしょう。
また、資産管理会社とは、有価証券、自ら使用していない不動産、現金・預金等の特定の資産の保有割合が総資産の総額の70%以上の会社やこれらの特定の資産からの運用収入が総収入金額の75%以上の会社をいいます(ただし一定の事業実態のある会社は除かれます)。
後継者に関する要件
事業承継税制による贈与税の納税猶予・免除の適用を受けるためには、贈与時において、後継者が次のすべての要件を満たさなければなりません。
- 会社の代表権を有していること
- 20歳以上であること
- 役員の就任から3年以上を経過していること
- 後継者および後継者と特別の関係がある者(後継者の親族等)で総議決権数の50%超の議決権数を保有することとなること
- (後継者が1人の場合)後継者と特別の関係がある者の中で、後継者が最も多くの議決権数を保有することとなること
- (後継者が2人または3人の場合)総議決権数の10%以上の議決権数を保有し、かつ、後継者と特別の関係がある者の中で、最も多くの議決権数を保有することとなること
先代経営者に関する要件
以下のすべての要件を満たしていなければなりません。
- 会社の代表権を有していたこと
- 贈与の直前において、贈与者(先代経営者)および贈与者と特別の関係がある者で総議決権数の50%超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと
- 贈与時において、会社の代表権を有していないこと
ただし、贈与の直前において、既に法人版事業承継税制の適用を受けている者がいる場合等には、上2つの要件は不要です。
担保に関する要件
納税が猶予される税額および利子税の額に見合う担保を税務署に提供しなければなりません。
上場株式の生前贈与が相続税対策になる理由
上場株式の生前贈与が相続税対策になる仕組みには、次のものがあります。
- 配当がある場合や、値上がりが予想される場合は、早めの贈与が相続税対策になる
- 値上がりしている場合は、贈与時の取引価格よりも低く評価できる
以下、それぞれの点について説明します。
配当がある場合や、値上がりが予想される場合は、早めの贈与が相続税対策になる
相続税対策の基本は、なるべく税金がかからないかたちで、上の世代から下の世代に財産を引き継ぐことです。
贈与対象の株に配当が生じている場合等は、贈与することによって、贈与時以降の配当金が贈与税や相続税がかからずに、下の世代ものになるというメリットがあります。
また、値上がりが予想される場合もまた、相続税対策になります。
評価額が低い時に贈与することで課税価格を抑えることができるためです。
値上がりしている場合は、贈与時の取引価格よりも低く評価できる
前述のとおり、株の評価は次の4つのうち、最も低い株価で評価します。
- 贈与日の終値
- 贈与日の当月のすべての営業日の終値の平均
- 贈与日の前月のすべての営業日の終値の平均
- 贈与日の前々月のすべての営業日の終値の平均
つまり、株価が値上がりしている場合でも低い時の株価で評価することができ、その分、節税効果が高まることになります。
まとめ
以上、株の贈与税について説明しました。
贈与の仕方によって税額が大きく異なることがあるため、事前に、贈与税に精通した税理士に相談することをお勧めします。
この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
ご希望の地域の専門家を探す





















