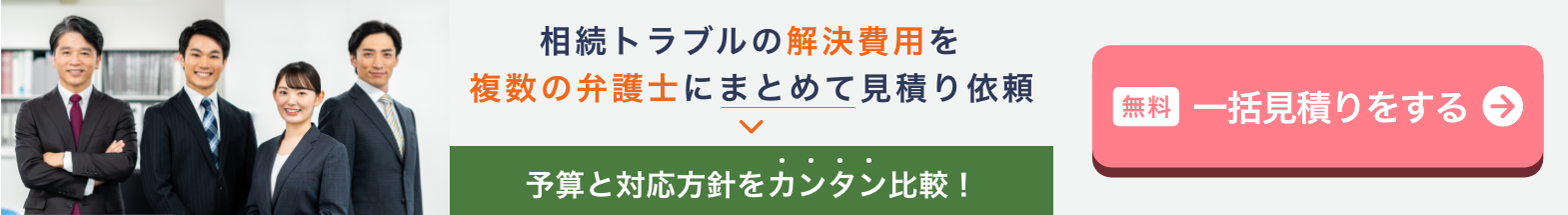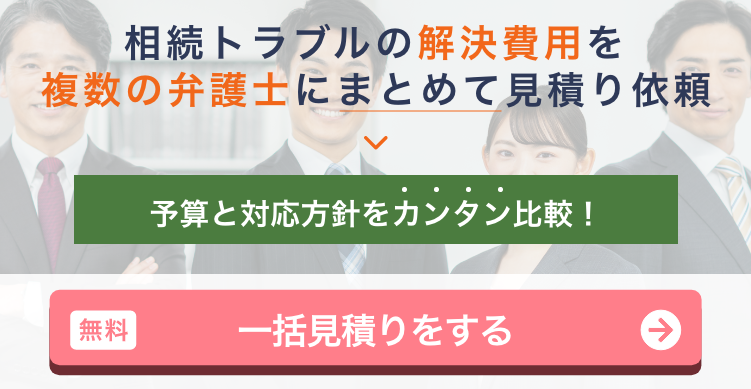妻の方が受給額が多い?!遺族年金はいくらもらえる?計算方法をご紹介

[ご注意]
記事は、公開日(2020年1月13日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
遺族年金は、遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類
遺族年金とは、国民年金や厚生年金保険の被保険者等が死亡して一定の要件を満たす場合に、その人によって生計を維持されていた一定の要件を満たす遺族が受けることができる年金のことです。 死亡した人の年金の加入状況などによって、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」のいずれか、または両方が給付されます。 子供が18歳になった年度の3月31日までの間は遺族基礎年金を受給できる可能性があり、亡くなった人がサラリーマン等で厚生年金か共済年金の加入者だった場合は遺族厚生年金が受給できる可能性があります。 遺族基礎年金、遺族厚生年金については以下の記事で詳しくご紹介しています。 ▼遺族基礎年金▼ ▼遺族厚生年金▼ 以降では、遺族年金の金額について、遺族基礎年金と遺族厚生年金とに分けてそれぞれ説明します。遺族基礎年金はいくらもらえる?
 遺族基礎年金の金額の計算方法について、配偶者が受け取る場合と子が受け取る場合とを、それぞれ説明します。
遺族基礎年金の金額の計算方法について、配偶者が受け取る場合と子が受け取る場合とを、それぞれ説明します。
配偶者が受け取る場合
配偶者が受け取る遺族基礎年金の金額(年額)は、「779,300円+子の加算額」で計算することができます。 子の加算額は、1人目と2人目が1人につき224,300円、3人目以降が1人につき74,800円です。 例えば、対象となる子が4人いる場合の支給額は、- 18歳になった年度の3月31日までの間にあること ※死亡当時に胎児であった子も出生以降に対象となります。
- 20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること
- 婚姻していないこと
子が受け取る場合
子が受け取る遺族基礎年金の金額(年額)は、「779,300円+2人目以降の子の加算額」で計算することができます。 加算額は、配偶者が受け取る場合と同じです。 この金額を子の数で割った額が、1人あたりの支給額となります。 例えば、対象となる子が4人いる場合の1人当たりの支給額は、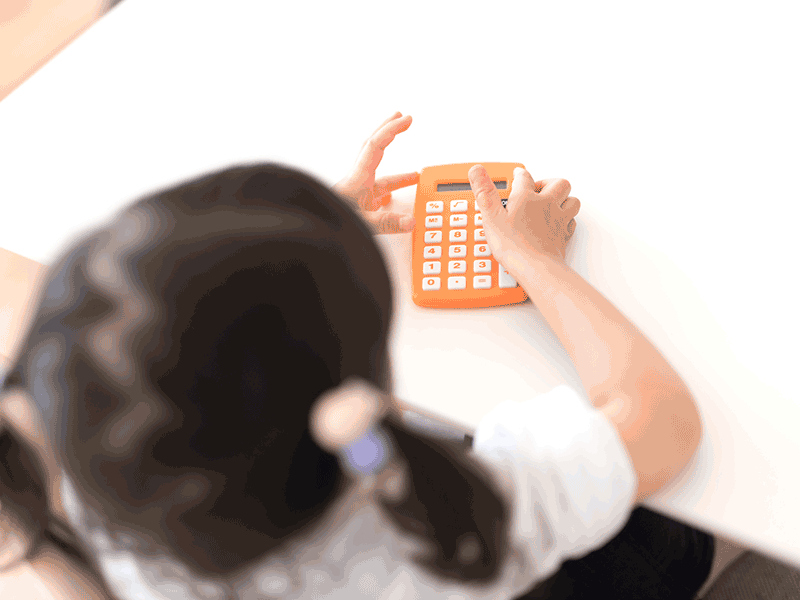
寡婦年金と死亡一時金
遺族基礎年金は、要件を満たす子がいる場合でなければ受けられませんが、要件を満たす子がいなくても受けられる、「寡婦年金」と「死亡一時金」という制度があります。 寡婦年金、死亡一時金については以下の記事で詳しくご紹介しています。 ▼寡婦年金▼ ▼死亡一時金▼遺族厚生年金はいくらもらえる?
基本的な計算方法
遺族厚生年金の金額は、老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。 老齢厚生年金とは、公的年金制度のひとつで、厚生年金に加入していて受給要件を満たした人が、原則65歳に達してから老齢基礎年金に上乗せしてもらえる年金のことです。 老齢厚生年金には、報酬比例部分と定額部分とがあり、報酬比例部分とは、年金額が厚生年金保険加入期間中の報酬及び加入期間に基づいて計算される部分です。 老齢厚生年金の報酬比例部分は、平成15年3月以前の加入期間におけるもの(A)と、平成15年4月以降の加入期間におけるもの(B)とを足し算して計算します。 Aは、次の計算式で求めることができます。65歳以上で老齢厚生(退職共済)年金を受ける権利がある人が配偶者の死亡による遺族厚生年金を受け取るとき
老齢厚生(退職共済)年金と遺族厚生年金の両方を受け取ることができる場合、平成19年4月1日までは、原則、どちらを受けるか選択することとなっていましたが、平成16年の年金制度改正により、平成19年4月1日からは、自分自身が納めた保険料を年金額に反映させるため、65歳以上で遺族厚生年金と老齢厚生年金を受ける権利がある方は、老齢厚生年金は全額支給となり、遺族厚生年金は老齢厚生年金に相当する額の支給が停止となります。 遺族厚生年金の受給権者が死亡した方の配偶者である場合、その遺族厚生年金は、- 亡くなられた方の老齢厚生年金額の3/4
- 亡くなられた方の老齢厚生年金額の1/2 + ご自身の老齢厚生年金額の1/2
中高齢寡婦加算
中高齢寡婦加算とは、遺族厚生年金の加算給付の一つで、「ちゅうこうれい かふ かさん」と読みます。「寡婦」とは、夫と死別した女性のことです。 中高齢寡婦加算は、遺族厚生年金を受ける妻(夫と死別した妻)が、40歳~65歳までの間、遺族厚生年金にお金を加算してもらえる制度です。妻が65歳になると自分の老齢基礎年金が受けられるため、中高齢の寡婦加算はなくなります。 中高齢寡婦加算の金額は、年間令和3年現在は年間585,700円です(老齢基礎年金満額の4分の3相当)。この金額が、遺族厚生年金の金額に加算されます。 中高齢寡婦加算については、以下の記事で詳しくご紹介しています。経過的寡婦加算
経過的寡婦加算とは、遺族厚生年金の加算給付の1つで、遺族厚生年金を受けている妻が65歳になり、自分の老齢基礎年金を受けるようになったときに、65歳までの中高齢寡婦加算に代わり加算される一定額のことをいいます。 これは、老齢基礎年金の額が中高齢寡婦加算の額に満たない場合が生ずるときに、65歳到達前後における年金額の低下を防止するため設けられたものです。 その額は、昭和61(1986)年4月1日において30歳以上の人(昭和31(1956)年4月1日以前生まれ)の人が、60歳までの国民年金に加入可能な期間をすべて加入した場合の老齢基礎年金の額に相当する額と合算して、ちょうど中高齢寡婦加算の額となるよう、生年月日に応じて設定されています。 65歳以降に初めて遺族厚生年金(長期の遺族厚生年金では死亡した夫の被保険者期間が20年(中高齢の期間短縮の特例などによって20年未満の被保険者期間で老齢厚生年金の受給資格期間を満たした人はその期間)以上)を受け始めた妻にも加算されます。 経過的寡婦加算については、以下の記事で詳しくご紹介しています。まとめ
以上、遺族年金の金額について説明しました。 家族が亡くなると、年金関係に限らず、様々な相続手続きが必要となることが多いです。専門家にまとめて依頼することで、手間が省けますし、申請漏れで損することもなくなります。一度、相談してみるとよいでしょう。この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
ご希望の地域の専門家を探す