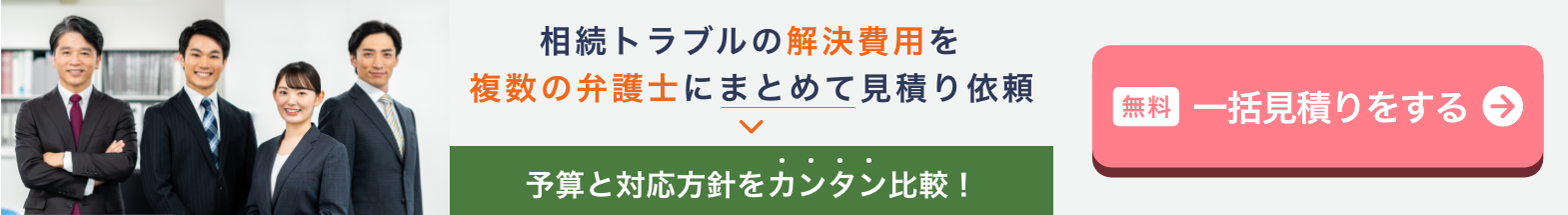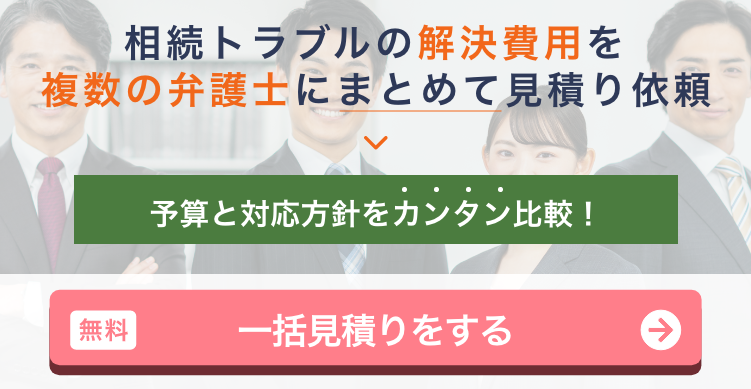相続放棄を弁護士に頼むメリットと費用、弁護士の選び方と流れ

- 弁護士に依頼すると、どのようなメリットがある?司法書士との違いは?
- 費用はどのくらいかかる?誰が払う?払えない場合はどうする?
- 相続放棄に強い弁護士の選び方は?
- 弁護士を選んでから家庭裁判所に相続放棄の申述が受理されるまでの流れは?
[ご注意]
記事は、公開日(2021年4月8日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
相続放棄を弁護士に依頼するメリット
弁護士に相続放棄を依頼すると、次のようなメリットがあります。- 相続放棄の申述が家庭裁判所に受理される可能性が高まる
- 手間がかからない
- 相続放棄をするに当たって、「してもよいこと」と「してはいけないこと」が確認できるので、安心できる
- 債権者から請求があった場合にも対応してもらえる(ただし、別途費用が必要となることが多い)
相続放棄の申述が家庭裁判所に受理される可能性が高まる
相続放棄の申述人が、既に相続を承認した場合(承認したとみなされる場合を含む)は、相続放棄の申述は受理されません。 相続人が遺産の一部でも処分した場合や、期間内に相続放棄をしなかった場合は、相続を承認したとみなされる可能性があります。 家庭裁判所は、提出された書類の記載内容等から、相続を承認したと認めるべき事由がないかを判断します。 受理されない可能性がある事情がある場合でも、弁護士が家庭裁判所への提出書類の記載内容を工夫することによって、受理される可能性を高めることができる場合があります。手間がかからない
相続放棄の手続きは、まず、家庭裁判所に申述書と添付書類等を提出します。 そうすると、家庭裁判所から照会書が郵送されてくるので、照会書に記入して返送します。 稀に、家庭裁判所から出頭要請があることもあります。 弁護士に依頼すると、申述書の作成や添付書類を収集する手間が省けますし、照会書も弁護士の方に送られてくるので(本人に送られてくる場合もあるので、その場合は弁護士に転送します)、弁護士が記入して返送してくれます。 また、出頭要請がある場合も、家庭裁判所から弁護士に直接連絡がいき、弁護士が出頭してくれるので、取り次ぐ手間すらかかりません。 自分で手続きすると、手間がかかるため期限内に手続きができず相続放棄ができなくなってしまうおそれがあるので、ご注意ください。相続放棄をするに当たって、「してもよいこと」と「してはいけないこと」が確認できるので、安心できる
自分で手続きをすると、遺産から支払ってはいけないお金を支払ってしまい相続放棄できなくなってしまったり、反対に、相続放棄をする場合でも受け取ってよいお金を知らずに自重して受け取らなかったりといったリスクが生じます。 弁護士に依頼すると、「してもよいこと」と「してはいけないこと」が事前に確認でき、後から分からないことが生じた場合も、都度、相談できるので安心です。債権者から請求があった場合にも対応してもらえる
相続放棄が受理された後、相続債権者(亡くなった人の債権者)が、相続放棄の無効を主張して、相続債務の弁済を求めてくることがあります。 そのような場合にも、弁護士に対応を依頼することができます(ただし、別途費用が必要となることが多い)。弁護士と司法書士との違い
司法書士は弁護士と比べて、相続放棄の手続きに関してできることの範囲について、次のような制限が設けられています。- 司法書士には、弁護士の項目で挙げたような相続放棄に関する法律相談をできないので、遺産から支払ってはいけないお金を支払ってしまい相続放棄できなくなってしまったり、反対に、相続放棄をする場合でも受け取ってよいお金を知らずに自重して受け取らなかったりといったリスクが生じる。
- 司法書士の場合は、相続放棄照会書・回答書が本人に送られてくるので、司法書士に転送しなければならないが、弁護士の場合は、弁護士に送られてくるので手間がかからない。
- 司法書士の場合は、相続放棄照会書・回答書は本人が記入しなければない(文案は司法書士が作成してくれます)が、弁護士の場合は、弁護士が代理で記入することができるので、手間がかからない。
- 家庭裁判所から出頭要請があった場合、司法書士の場合は本人が出頭しなければならないが、弁護士の場合は代わりに出頭できるため、手間がかからない。
相続放棄の弁護士費用
相続放棄の弁護士費用について説明します。相続放棄の弁護士費用は誰が払う?
相続放棄の手続きを弁護士に依頼した場合、弁護士費用は誰が払うのでしょうか? この点、基本的には依頼者本人(相続放棄する人)が払わなければなりません。 しかし、相続放棄の目的が、他の相続人に遺産を譲ることである場合、遺産を取得する相続人が弁護士費用を含めた手続費用を負担してくれることがあるでしょう。決まりはないので、当事者間の話し合いで決めるとよいでしょう。 また、複数の相続人が相続放棄をする場合は、まとめて同じ弁護士に依頼した方が、一人当たりの費用が安くなることが多いですが、複数人で依頼した場合、弁護士の費用は誰が払うべきでしょうか? この点、決まりは特になく、誰かが他の人の分を負担しても構いませんが、割り勘が平等でよいのではないかと思います。相続放棄の弁護士費用の相場
相続放棄の弁護士費用の相場は、5万~13万円くらいです。 この金額がベースで、次のような特殊事情がある場合は、一定額が加算されることがあります。- 期限まで日にちがない場合、期限の伸長(延長)が必要な場合
- 期限を過ぎている場合
- 海外在住の場合
- 遺産に手を付けている等の単純承認が疑われる事情がある場合
相続放棄の弁護士費用は安い方がいい?
相続放棄の弁護士費用は安いに越したことはないと思われるかもしれませんが、必ずしもそうとは限りません。 相続放棄に関する注意点について丁寧にわかりやすく説明をしてくれない弁護士に依頼すると、遺産から支払ってはいけないお金を支払ってしまい相続放棄できなくなってしまったり、反対に、相続放棄をする場合でも受け取ってよいお金を知らずに自重して受け取らなかったりといったリスクが生じてしまいます。 とはいえ、必ずしも、安ければダメ、高ければ安心というわけではありません。 要は、費用の多寡だけで決めるのではなく、依頼前の面談時に、説明がわかりやすいかどうかや、面倒臭がらずに根気強く丁寧に説明してくれるかといった点をチェックし、信頼のおける弁護士に依頼することが重要です。相続放棄の弁護士費用を払えない場合はどうする?
相続放棄の弁護士費用が払えない場合の対処法として、次の4つが考えられます。- 複数の事務所で見積もりを取り、費用を比較する
- 添付書類は自分で収集する
- 法テラスを利用する
- 弁護士ではなく司法書士に依頼する
複数の事務所で見積もりを取り、費用を比較する
複数の事務所で見積もりを取り費用を比較することは有効な方法ですが、相続放棄の費用の事務所ごとの差は、そこほど大きくはないでしょう。 また、前述のとおり、費用が安い弁護士がよい弁護士とは限りません。添付書類は自分で収集する
戸籍謄本等の添付書類については、弁護士に収集を依頼することもできますが、自分で収集することで、弁護士費用を下げられる場合があります。法テラスを利用する
「法テラス」は、正式には「日本司法支援センター」という名称で、国によって設立された法的トラブル解決のための「総合案内所」です。 法テラスを利用すると、法テラスと契約している弁護士の紹介を受けることができ、相場よりも費用が安くなることが多いです。法テラスの相続放棄の費用・料金は決まっているわけではありませんが、目安としては、1名が相続放棄する場合、実費として10,000円、着手金として33,000円、合計43,000円程度が必要となり、複数名が同時に相続放棄をする場合には、追加の費用がかかります。 また、一括での支払いが難しい場合は、月額5,000~10,000円程度の分割払いにすることもできます。 ただし、法テラスは、収入や資産が多い方は利用できません。利用基準については、法テラスのウェブサイトのこちらのページでご確認ください。 利用基準を満たす場合は、法テラスを利用できますが、以下のような注意点を考慮のうえ、利用するかどうかを決めるとよいでしょう。- 審査が通るまでに時間がかかる
- 弁護士を自由に選べない
- 経験の浅い専門家が多い
弁護士ではなく司法書士に依頼する
相続放棄の手続きは、司法書士に依頼することもできます。 司法書士の費用の相場は4万~5万円と、弁護士よりも若干低めに設定されていることが多いので、その場合は費用を節約できます。 ただし、司法書士は、弁護士と比べて、相続放棄の手続きに関してできることの範囲に前述のとおり制限が設けられているので、ご注意ください。相続放棄に強い弁護士の選び方
弁護士の選び方のポイントとして、次のような点が挙げられます。- 相続放棄に精通していることが客観的に判断できる
- コミュニケーションがとりやすく、信頼できる
- 費用が不合理に高くない
相続放棄に精通していることが客観的に判断できる
この点は、基本的には相続放棄が受理されない可能性がある事由が存在するような場合にのみ気にすればよいでしょう。 相続放棄が受理されない可能性がある事由とは、例えば、前掲のような、期間内に相続放棄をしなかった場合や、遺産の一部を処分してしまったような場合がこれに当たります。 このような事由がなければ、この点はそれほど重視なくても問題ないでしょう。 判断の指標としては、例えば、次のような点が挙げられます。- 相続放棄に関する弁護士向けの著書出版、論文執筆やセミナー講師等の実績がある
- 相続放棄に関する有名な裁判例の担当実績がある
コミュニケーションがとりやすく、信頼できる
コミュニケーションがとりやすく、信頼できる弁護士に依頼した方がストレスがないでしょう。 依頼前の面談時に、これらの点から弁護士を評価してみてください。 インターネット等の情報を基にある程度絞り込んだ上で、複数の弁護士の話を聞き比較してみるのもよいでしょう。 相談したからといって、依頼しなければならないわけでないので、まずは気軽に電話してみるとよいでしょう。 ポイントとしては、説明がわかりやすいか、質問に丁寧に答えてくれるか、費用についても事前に明確にしてくれるか、契約を急かさないか、等が挙げられます。費用が不合理に高くない
前述のとおり、費用の多寡だけで弁護士選びをすることはお勧めできませんが、不合理に高額な事務所は避けた方がよいでしょう。 相場よりも多少高いと感じられる場合でも、納得のいく説明が得られる場合や、その他の点で優れているのであれば問題ないでしょう。弁護士への相談から相続放棄が受理されるまでの流れ
弁護士への相談から相続放棄が受理されるまでの流れは、概ね次のようになります。- 面談予約
- 面談・見積もり
- 契約
- 必要書類の用意、申立て(弁護士)
- 照会書・回答書への記入・返信(弁護士)
- 相続放棄申述受理通知書(又は不受理通知書)の受領
面談予約
弁護士を選んで面談を予約します。 弁護士選びには、当サイトのこちらのページをご利用ください。選びやすいように、都道府県で絞り込んだり、初回面談料が無料の事務所や土日・夜間に面談できる事務所といった検索条件を設定して絞り込むことができるようになっています。 営業時間内であれば電話(当サイトに掲載されている弁護士の電話番号はすべてフリーダイヤルで通話無料)、営業時間外であればメールフォームから連絡します。 なお、連絡する前の事前準備は不要ですので、気軽に連絡して大丈夫です。 メールフォームで連絡した場合は、事務所の営業時間に折り返しの連絡があるでしょう。 電話がつながったら、当サイトを見て連絡した旨と、相続放棄したい旨を伝えましょう。 そうすると、面談の候補日時をいくつかピックアップしてくれるでしょう。 初回面談料が無料かどうかはサイトにも記載されていますが(当サイトの場合)、念のため、電話等でも確認しておきましょう。 コロナ禍以降、ビデオ会議システムを利用した遠隔面談に対応している事務所も増えており、そのような事務所の場合は対面か遠隔かの希望を尋ねられるでしょう。 初回面談までに用意すべき書類等がある場合は、予約時に事務所から指示がありますが、初回面談は書類等の用意は不要な事務所が多いです。 なお、「依頼しないかもしれないのに、無料で相談するのは申し訳ない」と感じる方もいらっしゃるようですが、その点はあまり気にしなくてもよいでしょう。 弁護士は、相談がすべて依頼につながるとは考えていません。 したがって、相続放棄について不明な点や不安な点を弁護士に相談しつつ依頼するかどうかを検討し、結果として依頼しなかったとしても気にする必要はまったくありません。面談・見積もり
初回面談が無料の場合は、相談料は不要です。 契約に必要な印鑑等の持参物は事前に事務所から指示があります。 相続放棄をすべきかどうか迷っている場合は、面談時に弁護士に相談しましょう。 面談中又は面談の終わりに見積もりを提示されます。 気になる点がなければ、その場で契約することもできまし、持ち帰って検討することも可能です。 特に急ぐ理由もないのにその場で契約を急かすような弁護士は基本的にはいないはずですが、万が一、そのような弁護士に当たった場合は依頼を避けた方がよいでしょう。契約
相続放棄をすること及び依頼する弁護士を決めたら事務所の指示に従って契約手続きをします(このタイミングで弁護士費用を支払う場合が多いでしょう)。必要書類の用意、申立て(弁護士)
基本的には弁護士にすべてお任せすることができますが、戸籍謄本等の取得を求められる場合があります。照会書・回答書への記入・返信(弁護士)
申立後、概ね1~2週間で、相続放棄照会書・回答書が届きます。 相続放棄の申述の代理を弁護士に委任した場合は、相続放棄照会書・回答書はその弁護士に直接届くことが多いのですが、本人に届くこともあります。 弁護士に届いた場合は、弁護士が対応するので、本人は何もすることはありません。 本人に届いた場合は、弁護士に転送すれば、後は弁護士が対応してくれます。相続放棄申述受理通知書(又は不受理通知書)の受領
照会書を返送し、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されると、相続放棄申述受理通知書が家庭裁判所から送付されます。 これは、相続人が相続放棄の申述を行い、これを裁判所が受理したということを通知する書類です。 家庭裁判所に相続放棄申述書等の必要書類を提出してから、相続放棄申述受理通知書が届くまでは、提出した書類に問題がない場合で、通常1~2か月くらいです。 この通知書が届けば、相続放棄の手続きは完了です。 なお、相続放棄の申述が受理されなかった場合は、相続放棄不受理通知書が届きます。まとめ
以上、相続放棄を弁護士に依頼する前に知っておくべきことについて説明しました。 相続放棄の申述は、一度しかできません。申述書や照会書の書き方が悪く不受理になったとしても、もう一度、再度申述することはできないのです。 相続開始から3か月以上が過ぎている場合や遺産に一部を処分したかもしれない場合は特に、弁護士に相談・依頼した方がよいでしょう。この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
ご希望の地域の専門家を探す