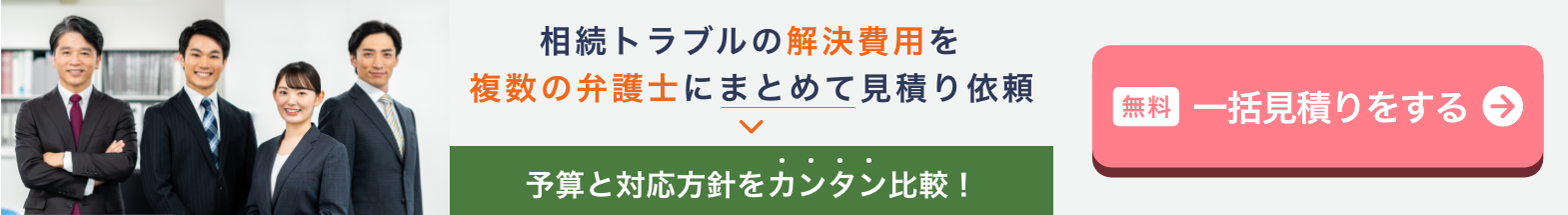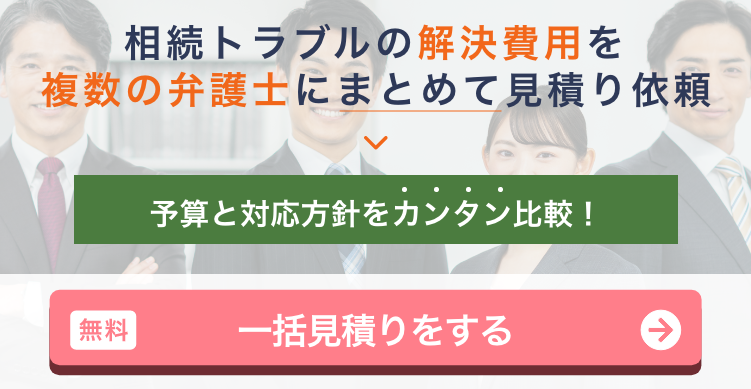遺留分減殺請求権の消滅時効の起算点や判例、遺留分減殺請求後の時効

[ご注意]
記事は、公開日(2018年12月21日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
遺留分減殺請求とは?
遺留分とは、一定の相続人のために、相続に際して、法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことで、被相続人(亡くなった人)の贈与や遺贈によっても奪われることのないものです。 そして、遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された人が、贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分侵害の限度で贈与や遺贈された財産の返還を請求することです。 例えば、被相続人が亡くなって妻と子が相続人だったとします。 その場合に、全財産を妻に相続させる旨の遺言が残されていたり全財産が妻に生前贈与されている場合は、子は一切の財産を相続できないことになりかねません。 しかし、まったく相続できなかったり、あまりに少ない割合しか相続できないとかわいそうなので、被相続人と近しい間柄の一定の相続人には、相続財産の一定の割合を取得することが保障されているのです。 その保障を実現するための手段が遺留分減殺請求です。消滅時効とは?
消滅時効とは、一定期間行使されない権利を消滅させる制度のことです。 また、消滅時効によって権利が消滅することを時効消滅と言います。遺留分減殺請求権の消滅時効
遺留分減殺請求権が時効によって消滅する場合と時効の起算点
遺留分減殺請求権は、次のいずれかに該当するときは、時効によって消滅します。- 遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないとき
- 相続開始の時から十年を経過したとき
遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないとき
「相続の開始」と、「減殺すべき贈与又は遺贈があったこと」の両方について遺留分権利者が知った時が、遺留分減殺請求権の消滅時効の起算点です。 遺留分権利者が、相続の開始を知っていても、減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知らなければ、消滅時効は進行しません。 また、遺留分権利者が、減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知っていても、相続の開始を知らなければ、消滅時効は進行しません。 なお、遺贈とは遺言によって財産を贈ることであり、遺贈があったこと知っている場合は相続の開始も知っているでしょう。 ところで、「減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時」とは、具体的にいつなのでしょうか? 贈与や遺贈が有効かどうか争っている間に時効が完成してしまうことはあるのでしょうか? この点について、最高裁判所昭和57年11月12日判決では、次のように判示されています。民法一〇四二条にいう「減殺すべき贈与があったことを知った時」とは、贈与の事実及びこれが減殺できるものであることを知った時と解すべきであるから、遺留分権利者が贈与の無効を信じて訴訟上抗争しているような場合は、贈与の事実を知っただけで直ちに減殺できる贈与があったことまでを知っていたものと断定することはできないというべきである。しかしながら、民法が遺留分減殺請求権につき特別の短期消滅時効を規定した趣旨に鑑みれば、遺留分権利者が訴訟上無効の主張をしさえすれば、それが根拠のない言いがかりにすぎない場合であっても時効は進行を始めないとするのは相当でないから、被相続人の財産のほとんど全部が贈与されていて遺留分権利者が右事実を認識しているという場合においては、無効の主張について、一応、事実上及び法律上の根拠があって、遺留分権利者が右無効を信じているため遺留分減殺請求権を行使しなかったことがもっともと首肯しうる特段の事情が認められない限り、右贈与が減殺することのできるものであることを知っていたものと推認するのが相当というべきである。
相続開始の時から十年を経過したとき
遺留分権利者が、相続の開始を知らなかったり、減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知らない場合は、いつまでも経っても時効は完成しないのかというと、そういうわけではありません。 相続開始の時から10年を経過したときは、遺留分権利者が相続の開始を知っていまいが、減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知っていまいが、時効は完成します。 つまり、相続開始の時から10年を経過した後の遺留分減殺請求は、基本的には認められません。遺留分減殺請求権が時効消滅しないようにする方法
遺留分減殺請求権が時効消滅しないようにするためには、時効が完成する前に、遺留分減殺請求しなければなりません。 請求さえしてしまえば、履行されなくても、その先、遺留分減殺請求権が時効消滅することはありません。 請求の方法に決まりはなく、口頭でも構いませんし、メールやファクシミリでも構いません。 相手方との関係が悪くなければ、まずは口頭で打診するのも悪くないでしょう。 しかし、請求の事実を後から証明できなければ、請求されていないとして時効を援用(時効の成立を主張すること)されてしまうおそれがあります。 そのような事態を避けるために、遺留分減殺請求は、配達証明付き内容証明郵便によって通知すべきです。 遺留分減殺請求通知書の文例を下記します。| 遺留分減殺請求通知書
被相続人○○○○(平成〇年〇月〇日死亡)の相続につき、通知人は相続財産の〇分の1の遺留分を有するところ、平成〇年〇月〇日付遺言書による被通知人の受遺分が、通知人の遺留分を侵害しており、通知人は、被通知人に対し、本書面をもって、遺留分減殺を請求します。 平成〇年〇月〇日(作成日日付) 通知人 ○○○○(自分の氏名) ○○県○○市○○町〇丁目〇番〇号(自分の住所) 被通知人 ○○○○(相手方氏名)殿 ○○県○○市○○町〇丁目〇番〇号(相手方住所) |
遺留分減殺請求後の時効
受贈者(贈与を受けた人)や受遺者(遺贈を受けた人)に対して遺留分減殺請求をすると、法律上、減殺の効力が生じます。 その結果、受贈者や受遺者は、遺贈や贈与によって取得した財産のうち、遺留分に相当する分の財産を返還しなければなりません。 財産が返還されない間に、遺留分減殺請求権が時効消滅することはありません。 請求した時点で既に減殺の効力は生じているからです。 したがって、遺留分減殺請求権は、行使すると(請求すると)、財産の返還請求権という別の権利になるのです。 遺留分減殺請求権を行使すると、基本的には、それぞれの財産に対して、遺留分に応じた持分を取得することになります。 例えば、遺留分が4分の1で、減殺されるべき財産が現金1000万円と不動産であった場合は、現金250万円と不動産の4分の1の共有持分を取得することになります。 ただし、請求された人には価額弁償の抗弁権があり、上記のように現物を返還するのではなく、お金で清算することを提案することができます。 例えば、先ほどの例で、不動産の価格が7000万円であったとすると、現金1000万円と併せて、遺留分算定の基礎となる財産の価額は8000万円になり、遺留分が4分の1であれば、2000万円を弁償することで、現物の返還に代えることができます。 このように、遺留分減殺請求権行使の結果、請求者は、財産の所有権や金銭債権を取得し、所有権に基づいて財産の返還を求めたり、金銭の支払いを求めることができるようになります。 所有権に基づく請求権は時効消滅しませんが、金銭債権は10年で時効消滅します。 この点に関する判例(最高裁判所平成7年6月9日判決)を紹介します。遺留分権利者が特定の不動産の贈与につき減殺請求をした場合には、受贈者が取得した所有権は遺留分を侵害する限度で当然に右遺留分権利者に帰属することになるから、遺留分権利者が減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記手続請求権は、時効によって消滅することはないものと解すべきである。
遺留分減殺請求に対して、生前贈与された財産の時効取得は主張できない
被相続人が亡くなるよりも随分前に生前贈与を受けて、長年、自分のものとして使用していた財産も、遺留分減殺請求によって返還しなければならないのでしょうか? この点、民法には、取得時効という制度があります。第162条この取得時効を主張して、遺留分減殺請求を受ける前に、贈与を受けてから善意無過失で10年または20年以上が経っていた場合に、遺留分減殺請求を退けることはできないのでしょうか? この点について、最高裁判所平成11年6月24日判決では、次のように判示しています。
- 二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
- 十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
被相続人がした贈与が遺留分減殺の対象としての要件を満たす場合には、遺留分権利者の減殺請求により、贈与は遺留分を侵害する限度において失効し、受贈者が取得した権利は右の限度で当然に右遺留分権利者に帰属するに至るものであり、受贈者が、右贈与に基づいて目的物の占有を取得し、民法162条所定の期間、平穏かつ公然にこれを継続し、取得時効を援用したとしても、それによって、遺留分権利者への権利の帰属が妨げられるものではないと解するのが相当である。つまり、遺留分減殺請求に対して、生前贈与された財産の時効取得を主張することはできないということになります。
この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
ご希望の地域の専門家を探す