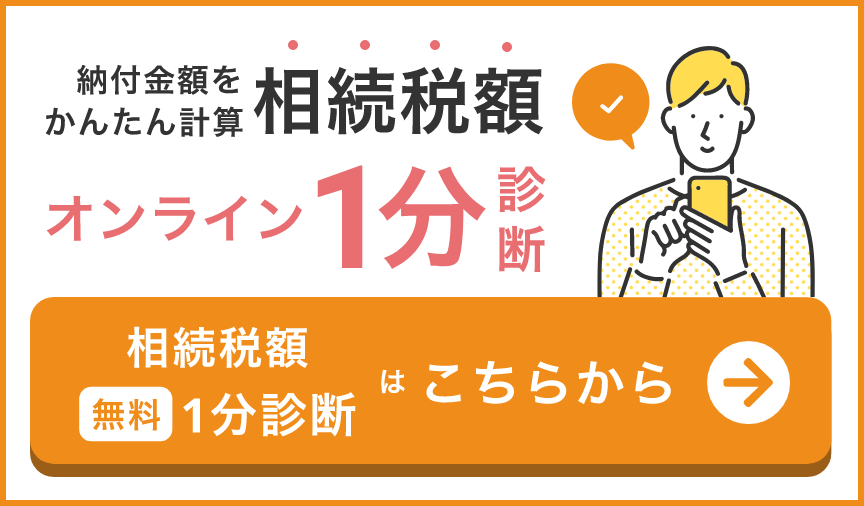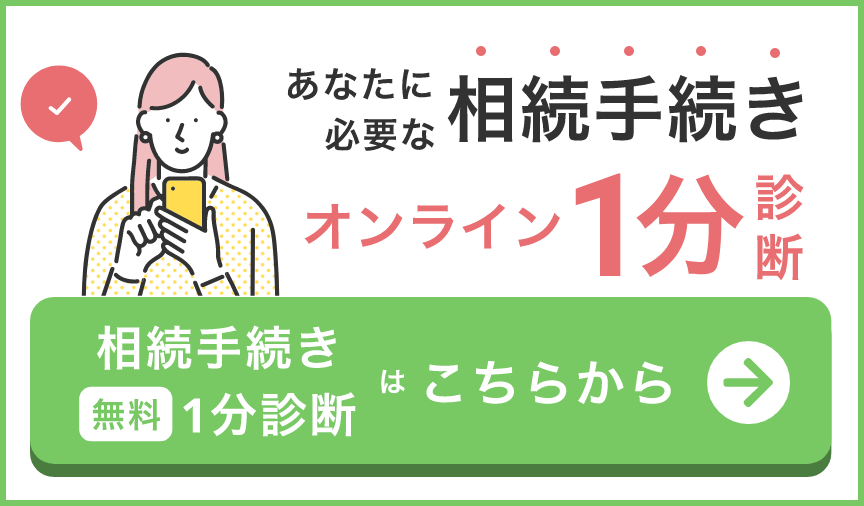遺贈で寄付を行うときの3つの注意

[ご注意]
記事は、公開日(2019年6月26日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
遺贈とは?
遺贈とは、遺言者が死後に財産を人に無償で譲与することです。 遺贈は、相続人に対してだけでなく、誰に対してでもすることができます。法人に遺贈することもできます(なお、遺贈を受ける人を「受遺者」といいます)。遺贈する場合は、遺贈する旨を遺言に残します。遺贈によって寄付するときの注意点
遺贈によって寄付をするときには、次の3つの点に注意します。- 遺留分を侵害する遺贈は避ける
- 包括遺贈より特定遺贈が望ましい
- 清算型遺贈が望ましい
遺留分を侵害する遺贈は避ける
遺留分とは、故人(被相続人)の配偶者や子など一定の範囲の相続人に留保された相続財産の割合のことです。 遺贈(遺言者が死後に財産を人に無償で譲与すること)や贈与が行われると、遺贈や贈与を受けられなかった相続人が、遺産をあまり取得できないことがあります。 そのような場合に、民法では、一定の範囲の相続人に対して、法定相続分の一定割合を遺留分として相続できるようにしているのです。 そして、遺留分を侵害された人は、贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分侵害の限度で贈与や遺贈された財産の返還を請求することができます(なお、2019年7月1日以降に開始された相続については、贈与や遺贈された財産そのものの返還ではなく、遺留分侵害額に相当する金額を請求できるように、相続法が改正されます)。 遺留分をもつ相続人は、配偶者、子、子の代襲相続人(孫など)、直系尊属(父母など)です。 これらの相続人がいる場合は、遺贈によって遺留分を侵害しないようにした方がよいでしょう。 遺留分を侵害する遺贈がなされた場合は、遺留分権利から受遺者に対して、遺留分侵害額請求(2019年7月1日以降に開始された相続について遺留分侵害額請求)がされる可能性があります。 遺留分は、直系尊属のみが相続人の場合は、法定相続分の3分の1で、それ以外の場合は2分の1です。 法定相続分に対する割合を示されても分かりにくいでしょうから、相続財産に対する割合を示すと下表のようになります。| 相続人の組み合わせ | それぞれの遺留分 |
|---|---|
| 配偶者と子 |
|
| 子のみ | 子:1/2(複数いる場合は均等割り) |
| 配偶者と直系尊属 |
|
| 直系尊属のみ | 直系尊属:1/3(複数いる場合は均等割り) |
| 配偶者と兄弟姉妹 |
|
| 兄弟姉妹のみ | 兄弟姉妹:なし |
| 配偶者のみ | 配偶者:1/2 |
包括遺贈より特定遺贈が望ましい
包括遺贈とは、財産の全部又は一部を包括的に遺贈するもので、財産に対する一定の割合を示してする遺贈をいいます。 例えば、「全財産の3分の2を○○に、3分の1を××に遺贈する。」というような遺贈がこれに当たります。 包括遺贈を受ける人を包括受遺者といいますが、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有します。 つまり、被相続人の権利義務を包括的に承継することから、包括受遺者は、相続財産に対して相続人とともに遺産共有の状態となり、債務も承継し、遺産分割に参加し、さらに、被相続人に対する所得税の納税義務を承継するとともに、所得税の準確定申告(納税者が亡くなった年の確定申告)及びその納税を行う必要があります。 受遺者である寄付先の元に遺言者の債権者から取り立てにあったり、寄付先が他の包括受遺者や相続人と共に遺産分割協議に参加しなければなくなったり、準確定申告や納税の義務を負わせてしまうと、寄付先に迷惑をかけてしまうことにもなりかねません。 この点、特定遺贈とは、特定の物や権利、あるいは一定額の金銭を与えるというように、財産を特定してする遺贈(割合で示されていない遺贈)をいい、受遺者は、その特定された財産を取得することができますが、それ以外の財産を取得するものではなく、また、遺言にない債務を承継することもありません。 遺贈による寄付をする場合は、包括遺贈よりも特定遺贈が望ましいでしょう。清算型遺贈が望ましい
清算型遺贈とは遺産を処分した処分金を受遺者に分配するものをいいます。- 寄付先に財産管理や換価についての事務負担をかけずに済む
- みなし譲渡所得にかかる税の納付の原資を作ることができる
- 遺留分に配慮した分配が可能
寄付先に財産管理や換価についての事務負担をかけずに済む
遺言者がもっている財産を寄付先が有効に活用できるとは限りません。 寄付先にとっては、使用しない不動産を持っていても仕方がないので、売却することになり、不動産の専門家ではない寄付先に不動産の売却事務という負担をかけることになってしまいます。 また、買い手が中々見つからないこともあるでしょう。 そうすると、買い手がつくまでの間、寄付先が不動産の管理をしなければならず、この点についても負担になる可能性があるでしょう。遺留分に配慮した分配が可能
現金や可分債権以外の財産が遺産の大部分を占める場合にも、清算型遺贈によれば、遺留分に配慮した分配が可能です。みなし譲渡所得にかかる所得税の納税原資を作ることができる
この点は、相続人に兄弟姉妹が含まれていて、かつ、後述のみなし譲渡にかかる所得税の非課税の適用を受けられないケースにおいて重要となります。 寄付先は、通常、個人ではなく法人のケースが多いでしょう。 個人が、土地、建物などの財産(事業所得の基因となるものを除きます。)を法人に寄付した場合には、これらの財産は寄付時の時価により譲渡があったものとみなされ、これらの財産の取得時から寄付時までの値上がり益に対して所得税が課税されます。 ただし、土地、建物などの財産を公益法人等に寄付した場合に、その寄付が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することなど一定の要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたときは、この所得税について非課税とする制度が設けられています。 この承認を受けて所得税が非課税となった場合は問題ありませんが、承認を受けられないケースでは、相続人は、被相続人に対するみなし譲渡所得課税に係る所得税の納税義務を承継するとともに、所得税の準確定申告及びその納税を行う必要があります。 そして、前述のとおり、遺贈の形態には包括遺贈と特定遺贈があり、国税通則法及び所得税法において、包括受遺者については相続人と同様に取り扱う旨を規定しているものの、特定受遺者についてはそのような規定はされていません。 そのため、被相続人の相続財産の大部分が不動産であり、当該不動産全てを法人に対し遺贈した場合において、当該遺贈が特定遺贈であるときには、当該法人は被相続人に対するみなし譲渡所得課税に係る所得税を負担せず、原則的には、不動産を取得しない相続人が、当該所得税を全額負担することになります。 この場合、例えば、相続人が被相続人の配偶者、子又は父母の場合は、法人に対して遺留分侵害額請求をすることにより財産の取戻し、あるいは価額弁償を受け、それらを元に所得税の納税義務を果たすことが可能となりますが、相続人が被相続人の兄弟姉妹である場合には遺留分侵害額請求権がないことから納税義務のみを承継することとなります。 この点、遺贈の一部を清算型遺贈とした場合は、みなし譲渡所得課税がなされる場合であっても、遺言執行者(遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人)が執行費用として売却代金から譲渡所得税を支払うことができるため、問題となりません。この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
ご希望の地域の専門家を探す