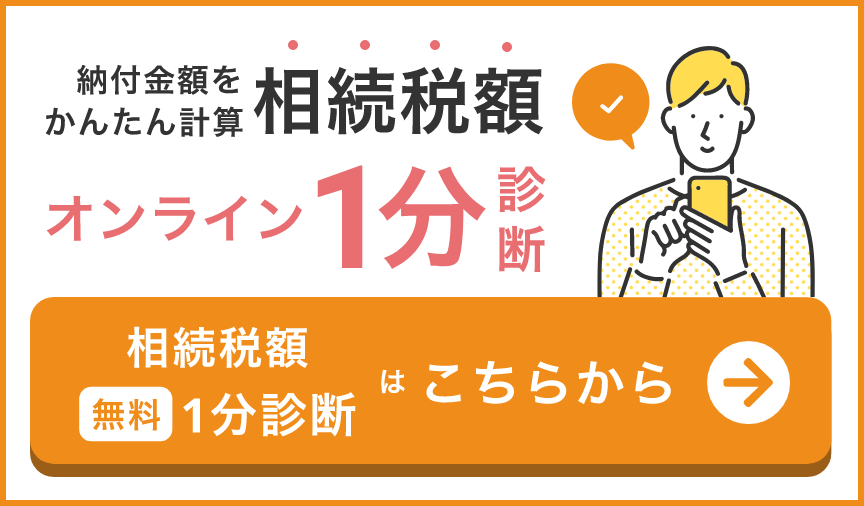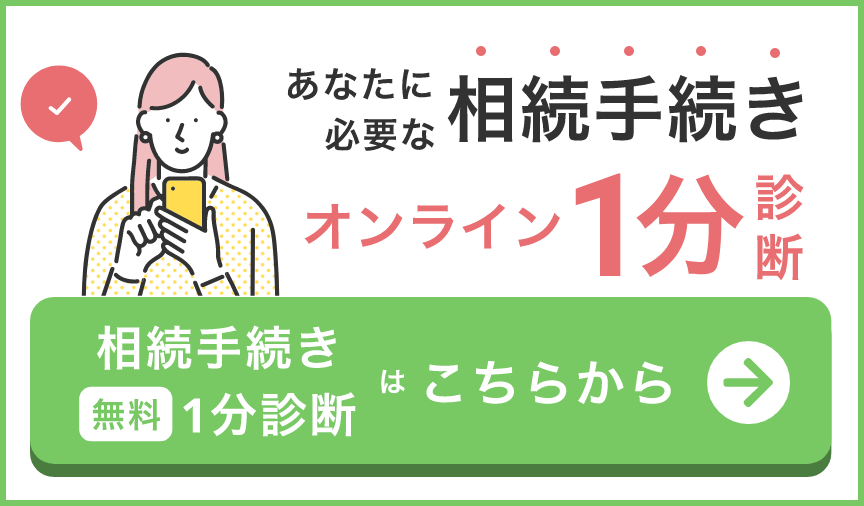遺贈とは?相続や贈与との違いは?最適な継承方法を選ぶための全知識

[ご注意]
記事は、公開日(2018年8月1日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
相続とは?
相続人
亡くなった人を「被相続人」と言い、その人の死亡により相続を受ける人のことを「相続人」といいます。 相続人の範囲は、下記のように法律で決まっています。配偶者
被相続人の配偶者は、必ず相続人になります。配偶者以外の法定相続人の順位
子及びその代襲者
子が先に死亡している場合には、さらにその子(被相続人の孫)が代襲相続します。孫が先に死亡していて、さらにその子(被相続人の曽孫)がいれば、曽孫が代襲相続します。直系尊属
「直系尊属」とは、家系図をさかのぼっていくイメージで、父母、祖父母、曽祖父母等のことをいいます。 直系尊属への相続では、まずは、父母が相続人になります。 父母がいなくて、祖父母(父方でも母方でも)のうち、一人でも生存していれば、祖父母が相続します。祖父母もいなくて、曽祖父母(ひいおじいさん、ひいおばあさん)がいる場合は、曽祖父母が相続します。 以降も延々と上の世代に遡ります。兄弟姉妹
子も直系尊属もいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。 兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その子(被相続人の甥や姪)は代襲相続します。その後(甥や姪の子)は代襲相続できません。相続分
続いて法定相続分について説明します。 配偶者と同順位の相続人のみの場合と、配偶者と血族相続人(子、親など)の場合とに分けて説明します。同順位の相続人のみの場合
配偶者が既に亡くなっており、相続人が同順位の相続人のみの場合は、相続財産を相続人間で案分します。 例えば、子が3人いる場合は、3分の1ずつになります。3人いる子のうちの1人が既に亡くなっており、その子の子が1人いて代襲相続人となる場合も同様に3分の1ずつです。 代襲相続人が複数いる場合は、その代襲相続人間でさらに案分します。配偶者と子及び子の代襲相続人
配偶者と子が相続人の場合には、配偶者が2分の1、子は、残りの2分の1が相続分となります。案分 子が複数いる場合は、2分の1の相続分を、子の間で人数分で案分します。配偶者と直系尊属
配偶者と父母が相続人の場合、配偶者が3分の2、父母が3分の1の相続分となります。 父母共に相続人となる場合は、3分の1の相続分を父母で折半します。配偶者と兄弟姉妹及び兄弟姉妹の代襲相続人
配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合には、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の相続分となります。遺贈とは?
上記のとおり、相続人や相続分は民法で決められていますが、自分の死後の財産の処分については、被相続人の意思を最大限尊重することも必要です。 そのために、「遺言」の制度があります。 遺言をすることができるようになるのは、15歳からです。 遺言によって、無償で自分の財産を他人に与える処分行為を「遺贈」といいます。 遺言によって財産を受け取る人のことを「受遺者」といいます。 相続が開始した後、遺贈を履行する義務を負う「遺贈義務者」は、原則として、相続人全員ですが、遺言執行者がいる場合には、遺言執行者になります(詳しくは後述)。 被相続人は、遺言によって自分の相続人のうちの誰かに遺贈をすることもできますし、相続人以外の人に遺贈をすることもできます。 また、法人も受遺者になれます。包括遺贈と特定遺贈
包括遺贈とは、相続財産の全部または一定割合を受遺者に与える行為をいいます。 例えば、「Aに自分の有する財産の全部を包括して遺贈する」とか「Bに自分の有する財産のうち5分の1を遺贈する」というような場合です。 特定遺贈とは、相続財産のうちの特定の財産を受遺者に与える行為をいいます。 例えば「自分の財産のうち、自宅不動産をAに遺贈する」というような場合です。包括受遺者になったら?
包括受遺者になったら、積極財産(プラスの財産)を受け取る権利だけでなく、相続債務(借金などのマイナスの財産)も引き継ぐことになります。 遺産分割が必要な場合には、包括受遺者は、相続人と一緒に遺産分割協議に参加します。 包括受遺者は、遺贈を放棄することができます。包括遺贈の放棄は、相続放棄の場合と同様に遺贈を知ったときから、3ヶ月以内に家庭裁判所で放棄の手続きを行う必要があります。特定遺贈の受遺者になったら?
特定遺贈の受遺者は、遺産分割協議を経ずに、指定された遺産だけをもらうことができます。 特定遺贈の受遺者も、遺贈を放棄することができます。特定遺贈の放棄は、相続人(遺贈義務者)または、遺言執行者に対する意思表示によって行います。 期間の制限はありません。 しかし、特定遺贈の受遺者が、遺贈を受けるのか放棄するのかがいつまでも分からなかった場合、相続人などの利害関係人がいつまでも不安定な立場におかれることになりかねません。 そこで、遺贈義務者その他の利害関係人は、相当の期間を定めて、その期間内に遺贈を承認するか放棄するかを決めるよう催告することができます。受遺者がその期間内に意思を表示しなければ、遺贈を承認したとみなされます。遺言執行者
遺言執行者とは
遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために必要な手続きを行う権利を有し、また、義務を負っている人のことです。 未成年者及び破産者以外であれば、だれでも遺言執行者になることができ、相続人の一人や受遺者も遺言執行者になることができます。 また、弁護士などの専門職や信託銀行が遺言執行者になることもあります。遺言執行者はいてもいなくても、遺言の効力に変わりはありません。遺言執行者を選任するメリット
遺言執行者がいる場合には、相続人は、相続財産を処分したり、遺言の執行を妨げたりすることができませんから、確実に遺言を執行してもらえます。 また、遺言による認知や相続人の廃除、廃除の取消しは、遺言執行者が執行する必要があります。 認知とは、結婚していない男女の間に生まれた子について、実の親が自分の子であることを法的に認めることです。 認知された子は、認知した親から財産を相続する権利などを得られます。 相続廃除とは、相続人に著しい非行の事実がある場合に、その者の遺留分を含む相続権を剥奪する手続きのことです。遺言執行者の選任
遺言者は、遺言によって、遺言執行者を指定することができます(遺言執行者に指定された人は、相続開始後に断ることもできます)。 また、相続開始後には、家庭裁判所に対して相続人が遺言執行者の選任の申立を行うことができます。遺贈と贈与との共通点と違い
まず、贈与について簡単に説明し、遺贈との共通点と違いについて説明します。贈与について
まず、贈与について、生前贈与と死因贈与に分けて説明します。生前贈与とは?
生前贈与とは、生きているうちに自分の財産を贈与することです。 「贈与」とは、贈与契約のことで、贈与者と受贈者の合意によって成立します。死因贈与とは?
死因贈与とは、贈与者の死亡によって、効果が生じる贈与契約のことです。 死因贈与では、贈与契約は生前に行われていますが、実際に贈与を受けることができるのは、贈与者の死亡時になります。遺贈と贈与の共通点
財産を自由に処分できる
遺贈と贈与とは、どちらも自分が財産を渡したいと思う人に財産を渡すことができる制度です。 そして、遺贈と死因贈与は、遺贈者・贈与者の死亡によって、効果を生じるという点が共通しています。そのため、死因贈与には、その性質に反しない限り、遺贈の規定が準用されることになっています。「負担付き」にできる
贈与も遺贈も、無条件に財産を渡すだけではなく、受贈者・受遺者が一定の義務を負うことを条件に財産を渡すという方法を選ぶことができます。 例えば、「(被相続人の)妻が生きている限り、妻の面倒を見ること」とか、「住宅ローンを払うこと」、「一定の社会奉仕活動をすること」などです。 負担付き遺贈とは、受遺者に一定の義務を負担させることを条件に行う遺贈のことです。 受遺者は、遺贈の目的の価値を超えない限度においてのみ、負担した義務を履行すればよいとされています。 受遺者が負担を履行しない場合には、相続人は、相当の期間を定めて履行を催告し、その期間内に負担の履行がなされなければ、家庭裁判所に遺言の取消しを請求できることになっています。 負担付き贈与とは、受贈者に一定の義務を負担させることを条件に行う贈与のことです。この義務は、贈与するものの対価に当たらない程度の義務です。 受贈者が負担を履行しない場合は、契約の解除の問題になります。遺贈と贈与の相違点
単独行為か契約か、形式が厳格か自由か
遺贈は、相手の同意のいらない単独行為なので、自分の好きな内容で遺言を作成することができます。 ただし、遺言は民法に定められた形式に従って作成しなければならず、形式を守らずに作成されたものは無効になります。 遺贈は、受遺者があらかじめ同意していないことですので、受遺者の側が拒否する場合には、被相続人が死亡し、相続が開始されてから、放棄の手続きをすることになります。 一方、生前贈与と死因贈与は、契約です。贈与契約は、双方の同意によって成立するため、口頭でも成立します。 もっとも、特に贈与者の死亡後に効力が発生する死因贈与契約は、その契約の存在を証明するためにも、通常は契約書を作成します。 契約書の作成には、遺言のような厳格な形式はありません。撤回できるか
遺言は、被相続人の最終の意思を尊重する制度であり、相手の同意のいらない単独行為ですから、生きている間、好きなように撤回したり変更したりすることができます。 また、遺言は何通でも作成することができます。複数ある遺言で内容に矛盾がある遺言が存在する場合には、一番日付の新しい遺言が有効になります。 一方、契約は、どちらかが理由もなく一方的に解除することはできないのが原則です。贈与契約も書面によって成立した場合には、理由のない解除はできません。 しかし、死因贈与契約は、被相続人の最終の意思を尊重するべきという点において遺贈と共通しているため、その性質に反しない限り、遺贈の規定が準用されることになっています。 そこで、原則として、遺贈と同様に撤回が可能であるとされています。 ただし、負担付贈与契約は、生前に締結されるため、その負担する義務が、贈与者の生前に履行されるものである場合があります。 受贈者が、負担を履行した後では、贈与者は、負担付き死因贈与契約を撤回することが難しくなります(撤回が認められるかどうかは、個別具体的な事案によって変わります)。年齢の違い
遺言は、15歳から単独ですることができます。 これに対して、贈与契約は契約ですから、未成年者である間は、親権者の同意を得て行うか、親権者が代理して行う必要があります。税金の違い
相続には相続税が適用されます。遺贈を受けた人にも相続税が課税されます。 これに対して、生前贈与には、贈与税が適用されます。贈与税は、相続税よりも基礎控除額が低く、税率も高く設定されています。 もっとも、生前贈与については、各種の優遇制度がありますから、うまく優遇制度を利用すれば、相続税を払うよりももっと有利になります(そのために節税対策として利用されます)。 生前贈与を行う場合には、税金の優遇制度をよく調べて利用するようにしましょう。不動産の所有権移転登記手続きの違い
遺言により遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者と受遺者の協力によって所有権移転登記手続きができます。遺言執行者が指定されていない場合、遺言者の相続人全員と受遺者の協力によって所有権移転登記手続きができます。なお、上述のとおり、相続開始後には、家庭裁判所に対して相続人が遺言執行者の選任の申立を行うこともできます。 これに対して、贈与契約の場合は、贈与者と受贈者が協力して所有権移転登記手続きをすることが必要になります。 死因贈与の場合、贈与者は死亡していますので、贈与者の地位を相続した相続人全員と受贈者とが協力して所有権移転登記手続きをすることになります。遺留分に注意
遺留分とは、一定の相続人のために、相続に際して法律上取得することが保障されている遺産の一定の割合のことです。 分かりやすく言うと、「相続財産に対する最低限の取り分」ということです。 兄弟姉妹以外の法定相続人には、本来の相続分の2分の1の遺留分があります。ただし、直系尊属(親など)のみが相続人の場合には、本来の相続分の3分の1です。 遺留分を侵害する遺贈は、その侵害する限度で無効とされています。 具体的には、遺留分を侵害された相続人は、受遺者に対して、遺留分減殺請求権を行使することができるということです。遺贈に関する相談先
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類があります。 どの方式を選ぶかで優劣はありませんが、それぞれに厳格な作成上の決まりがあり、その決まりを守って作成されていないものは遺言として無効となってしまいます。 また、内容があいまいだと、その解釈をめぐり、相続人や受遺者の間で紛争を起こしてしまう可能性もあります。 そのため、遺贈をしようと考える場合には、遺言の作成の形式、内容、税金をよく検討する必要があります。 また、その人の目的や財産の状況などによっては、遺贈よりも、死因贈与、生前贈与、家族信託などの方が優れている可能性もあります。まとめ
民法に定められた相続の制度だけでは、被相続人の意思を反映することができません。 被相続人の最終の意思を尊重するために遺贈や贈与が使われます。 遺贈も贈与も自分の財産を自由に処分することができる制度です。 特に死因贈与は、遺贈の規定が多く準用されています。 一方で、遺贈が単独行為であるのに対して、死因贈与が契約であることから、違いもあります。 遺贈を選ぶべきなのか、死因贈与を選ぶべきなのかは、その人ごとの個別具体的な事情によって異なります。 そして、遺言は、相続に関する紛争を防止するために有効な対策の一つですが、財産の承継のさせ方はいろいろとあります。 贈与、遺言、民事信託(家族信託)という制度を組み合わせることによって、自分の生前から死後に至るまでのプランを考えることができます。 自分にもっとも合うプランは何かということは、相続や信託に詳しい弁護士に相談してみるべきでしょう。この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
ご希望の地域の専門家を探す