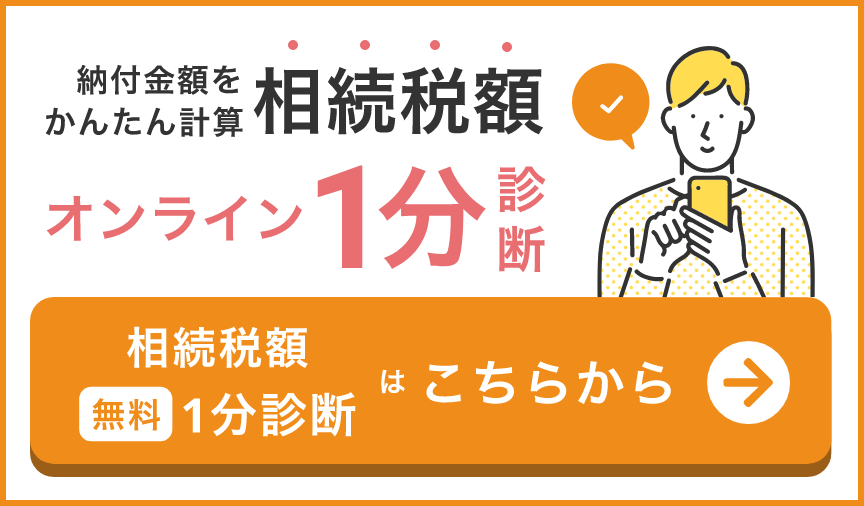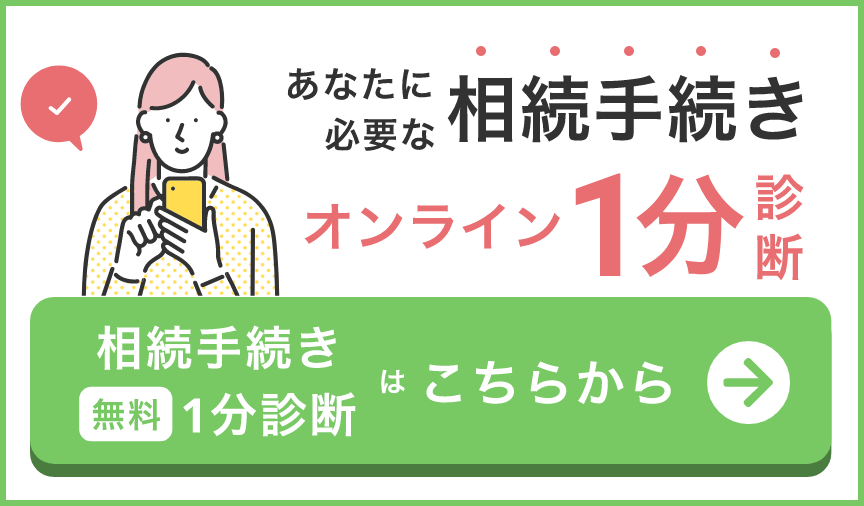【住宅取得資金贈与の非課税】要件や手続きについて徹底解説

住宅取得等資金の贈与を非課税にする特例があることは、よく知られていますが、使わない方が節税になるケースもあるのです。
また、非課税枠を超えて贈与を受けたい場合の方法も複数あり、どういう方法を選択するかによって、損得が生じます。
この記事では、住宅取得資金の贈与を賢く利用して、税金面で最も得になるような制度選択ができるように、分かりやすく説明していきます。
相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください
[ご注意]
記事は、公開日(2018年8月16日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
目次
住宅取得等資金の非課税の特例とは?
「住宅取得等資金の贈与税の非課税の特例」とは、2015年から2021年までの間に、親や祖父母等から受けた贈与を資金として住宅を取得する等した場合に、法律で定められた非課税限度額まで贈与額を非課税にするという特例です。
贈与者は、親や祖父母だけでなく、曽祖父母やさらに上の世代でも構いませんが、配偶者の親や祖父母は認められません。
相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください
非課税となる上限
特例の非課税限度額は、家屋の種類(省エネ住宅かどうか)、契約締結日、消費税率によって異なります。
なお、契約締結日とは、家屋を建築するための請負契約等の契約締結日のことです。贈与契約の締結日ではありません。
また、省エネ等住宅というのは、省エネ等基準に適合することを証明された住宅のことです。
非課税限度額は下表のとおりです。この特例と贈与税の基礎控除(年間110万円)は併用できるので、特例の非課税限度額+110万円の贈与をその年に非課税で受けることができます。
消費税が8%の期間中の非課税限度額
| 契約締結日 | 省エネ等住宅 | 省エネ等住宅以外の住宅 |
|---|---|---|
| 2015年1月1日~2015年12月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 2016年1月1日~2020年3月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
| 2020年4月1日~2021年3月31日 | 1,000万円 | 500万円 |
| 2021年4月1日~2021年12月31日 | 800万円 | 300万円 |
消費税が10%になった後の非課税限度額
| 契約締結日 | 省エネ等住宅 | 省エネ等住宅以外の住宅 |
|---|---|---|
| 2019年4月1日~2020年3月31日 | 3,000万円 | 2,500万円 |
| 2020年4月1日~2021年3月31日 | 1,500万円 | 1,000万円 |
| 2021年4月1日~2021年12月31日 | 1,200万円 | 700万円 |
特例の適用を受けられる人
特例の適用を受けられる受贈者の要件は、次の通りです。
- 贈与を受けた時に贈与者の直系卑属(子や孫)であること。
※配偶者の父母(又は祖父母)は直系尊属には該当しませんが、養子縁組をしている場合は直系尊属に該当します。 - 贈与を受けた年の1月1日において、20歳以上であること。
- 贈与を受けた年の年分の所得税に係る合計所得金額が2,000万円以下であること。
- 2009年分から2014年分までの贈与税の申告で「住宅取得等資金の非課税」の適用を受けたことがないこと。
- 自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋の取得をしたものではないこと、又はこれらの方との請負契約等により新築若しくは増改築等をしたものではないこと。
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てて住宅用の家屋の新築等をすること。
※受贈者が「住宅用の家屋」を所有する(共有持分を有する場合も含まれます。)ことにならない場合は、この特例の適用を受けることはできません。 - 贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること。
※贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることはできませんので、修正申告が必要となります。
「新築等」にはどこまで含まれる?土地の取得は大丈夫?
特例を受ける要件に、前述のとおり、「家屋の新築等をすること」とあります。
この「新築等」には、純粋な新築だけではなく、新築のための土地の取得や、増改築も含まれます。なお、対象となる住宅用の家屋は日本国内にあるものに限られます。
相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください
贈与のタイミングによっては特例が適用されない
贈与を受けるタイミングによって、特例が適用されないことがあるので、注意してください。
ポイントは、決済の直前のタイミングで贈与を受けることです。以下のような場合は、特例が適用されません。
- 贈与を受けた翌年の3月15日までに家屋が出来上がらない場合(工事が完了に準ずる状態にある場合を除く)
- 贈与を受けた翌年の12月31日にまでに住んでいない場合
- 住宅ローンの決済後に贈与を受けた場合(住宅ローンの返済に充てた場合は、特例の適用を受けられません。)
住宅を新築・取得すると小規模宅地等の特例を受けられなくなる
被相続人の自宅を相続した時に、小規模宅地等の特例が適用できるのは、配偶者、同居の親族、家を持っていない親族のいずれかです。
配偶者が相続した場合には取得者ごとの要件は無いのですが、他の親族は住宅を新築・取得してしまうと小規模宅地等の特例を受けられなくなります。
小規模宅地等の特例とは、自宅の評価額を330㎡まで8割減できる大変お得な特例です。
小規模宅地等の特例とどちらが得になるかは慎重に判断すべきですが、多くの場合は、小規模宅地等の特例の適用を受けられるのであれば、そちらを受けた方が得になります。
税額ゼロでも要申告!申告方法と必要書類
この特例の限度額以内で、住宅取得等資金の贈与を受けた場合、贈与税額はゼロになります。しかし、特例の適用を受けるためには贈与税の申告書を提出しなければなりません。
申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署に、次の書類等を提出して行います。
- 贈与税の申告書(特例の適用を受ける旨を記載のこと)
- 戸籍謄本
- 登記事項証明書
- 新築や取得の契約書の写し
贈与税、相続税の手続きは理解の難しい仕組みや制度がたくさんあります。正しく、そして不利益が出ないようにするために、ぜひ専門家に相談してみることをご検討ください。
チェックシートで適用を受けられるか確認
国税庁の発行する公式チェックシートを使うと、特例の適用を受けられるかどうか、簡単にチェックすることができます。
このチェックシートは2枚一組になっていて、一枚目は適用できるかどうかのチェックを、二枚目は申告する方の添付書類のチェックを行うことができます。
チェックシートは、新築・取得用と増改築用の2種類があり、国税庁のこちらのページからダウンロードができます。
相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください
非課税限度額以上に贈与を受けたいときはどうすればよい?
非課税限度額以上に贈与を受けたい場合の方法として、次の4つが考えられます。
- 超えた分の贈与税を納める
- あらかじめ毎年110万円ずつ贈与を受けておく
- 相続時精算課税を選択する
- 共有名義にする
以下、それぞれについて説明します。
超えた分の贈与税を納める
省エネ等住宅以外の住宅を2018年(消費税8%)に購入した場合の非課税限度額は、上表の通り、700万円です。
これに相続税の基礎控除額110万円を加えて、810万円が非課税で贈与を受けられる上限です。しかし、もっと贈与を受けたいというときもあるでしょう。
上限を超えて受けた贈与には、贈与税がかかります。一般贈与財産と特例贈与財産とで、贈与税率が異なりますが、住宅取得等資金の非課税の適用を受けるケースでは、特例贈与財産の税率が適用されます。特例贈与財産の税率は次の通りです。
| 控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万円以下 | 10% | – |
| 400万円以下 | 15% | 10万円 |
| 600万円以下 | 20% | 30万円 |
| 1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
| 1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
| 3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
| 4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
引用:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
例えば、2,000万円贈与を受ける場合では、控除後の課税価格は、2,000万円-810万円=1,190万円となり、贈与税額は、上表に当てはめて、1,190万円×40%-190万円=286万円となります。
あらかじめ毎年110万円ずつ贈与を受けておく
贈与税を支払わなくて済むようにするためには、事前に毎年贈与を受けておくことです。
11年間、毎年110万円ずつ贈与を受ければ、110万円×11年=1,210万円の贈与を非課税で受けることができます。
相続時精算課税を選択する
前述のように何年も前から準備できればそれが一番良いのですが、実際はそれほど計画にできないことも多いでしょう。そのような場合には相続時精算課税が選択肢として挙げられます。
相続時精算課税は、2,500万円までの贈与に対する贈与税を非課税にして、代わりに相続時に相続税を課税する制度です。
相続時精算課税を選択すると、選択した年以降、その贈与者からの贈与に対しては、毎年110万円の基礎控除を利用できなくなります。
なお、相続税の基礎控除は、贈与税よりも大きく、次の式で計算されます。
例えば、法定相続人の数が3人の場合は、相続税の基礎控除額は、3,000万円+600万円×3人=4,800万円となります。
相続税の基礎控除は、相続時精算課税を選択した贈与額だけでなく、課税遺産総額に対しての基礎控除です。自分の相続分だけでなく、他の相続人も含めた課税遺産総額に対する基礎控除なのです。
その課税遺産総額が、相続税の基礎控除額に収まる場合は、相続時精算課税を利用すべきですが、そうでない場合は、贈与税の基礎控除を利用して賢く節税していくべきなので、それが使えなくなる相続時精算課税の利用はおすすめできません。
共有名義にする
住宅を贈与者との共有名義にするという方法もあります。この方法だと、贈与税の基礎控除がその後もずっと使えるので、相続時精算課税の利用よりもおすすめです。
共有と言っても、実際に一緒に住む必要はありません(住んでもよい)。
共有名義とは、一つの物を複数人で一緒に所有して、登記もそのようにすることです。親が子に住宅取得資金を贈与するというケースの場合、贈与は非課税でできる810万円に留めておき、それを超える分は、贈与ではなく、親自身も住宅の取得費用を負担し、住宅の共有持ち分を得るという方法を取るのです。
例えば、住宅の価格が4,000万円だとして、資金の内訳が、自己資金がローンも含めて2,000万円、親からの資金が2,000万円だとします。親からの資金のうち、810万円は、非課税で贈与を受けられるので、贈与を受けて自己資金に組み込みます。
そうすると、自己資金が2,810万円で、親の資金が1,190万円となり、それぞれの共有持ち分の割合は、自分の持ち分が、4,000万分の2810万で、約7割となり、親の持ち分が、4,000万分の1,190万で、約3割となります。
この1,190万円は、贈与を受けたわけではないので、贈与税は課せられません。親が亡くなった時に相続することになり、その時に相続税が課税されます。
相続時精算課税制度との違い
相続税が課税されるという点では、相続時精算課税と同じですが、贈与税の基礎控除を利用できる分、共有名義の方が得になるのです。
また、相続税は相続時の評価額を基に計算されます。住宅は古くなると価値が下がってきます。
親が亡くなった時に、住宅が古くなり半分の価値しかなくなっていた場合は、親の持ち分の価値もそれに比例して半額になります。そうすると、その分、相続税は安くなります。
相続時精算課税を選択した場合は、贈与額にそのまま相続税が課されますので、この点でも共有名義が有利といえます。
共有名義の注意点としては、他にも相続人がいる場合、遺言がないと、親の持ち分を相続人全員で相続してしまい、権利関係が複雑になってしまうということがあります。
ですので、共有名義にした場合は、共有持ち分をその住宅の所有者である子に相続させるように、親が遺言を残しておくとよいでしょう。
相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください
この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
ご希望の地域の専門家を探す