無道路地の評価方法を事例付きでわかりやすく解説

相続税の計算上、無道路地はどのように評価すべきでしょうか?
評価額から一定の割合を控除を認められるケースと認められないケースには、どのようなものがあるのでしょうか?
道路に接しているものの接道義務を満たしていない場合はどうでしょうか?接道義務とは何でしょうか?私道に接している場合は無道路地となるのでしょうか?
無道路地の評価と不整形地の評価は併用できるのでしょうか?その場合の想定整形地の取り方はどのようにすればよいのでしょうか?
無道路地を相続した人が前面の隣接地を所有している場合はどのように評価すればよいでしょうか?隣接地の所有者が親族の場合はどうでしょうか?
不動産の相続をすると次々に細かい疑問点が出てきます。
この記事では、以上のような無道路地の評価に関する疑問点について、事例を元にできる限りわかりやすく丁寧に説明します。
是非、参考にしてください。
[ご注意]
記事は、公開日(2020年8月20日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
相続問題でお悩みの方は
まずは弁護士にご相談ください
無道路地とは?無道路地の評価の適用要件は?
無道路地とは一般に道路に接していない土地のことをいいますが、無道路地の評価の適用要件としての無道路地の定義は、一般的な定義とは異なります。
都市計画域外の土地は無道路地の評価を受けられない
まず、都市計画区域又は準都市計画区域の外にある土地には、通常、接道義務がないため、道路に接していなくても無道路地の評価は適用できません(ただし、条例等で接道義務が設定されている可能性があるので、税理士又は役所に確認することをお勧めします)。
通行の用に供する権利を設定している場合も無道路地の評価を受けられない
そして、他人の土地に囲まれており道路に接していなくても、その他人の土地に通行の用に供する権利を設定している場合は、無道路地の評価は適用できません。
接道義務を満たしていない場合は無道路地の評価を受けられる
反対に、道路に接していてもその接する間口距離が接道義務(建築基準法その他の法令において規定されている建築物を建築するために必要な道路に接すべき最小限の間口距離の要件)を満たしていない宅地については、無道路地と同様に評価します。
都市計画区域又は準都市計画区域にある土地については、原則として、建築基準法上の道路と2メートル以上接していなければ、接道義務を満たせません。
したがって、道路に接していても、接道距離が2メートル未満である場合や、建築基準法上の道路でない場合は、接道義務を満たしていないため、無道路地と同様に評価します。
なお、建築基準法上の道路に該当するかどうかは、原則として、道路の幅員が4メートル以上かどうかによって決まります。
ただし、幅員が4メートル未満の道路であっても、建築基準法施行前から使用されている道路は建築基準法上の道路に該当することがあります。
なお、公道か私道かは関係ありません。
すなわち、公道に接していない土地でも幅員が4メートル以上ある私道に接している場合は、無道路地に該当しません。
東京都の場合、路地状部分の長さが20メートルを超える土地については、接道距離が3メートル以上なければなりません。
このように、接道義務は条例により強化されている場合があるため、税理士や役所に確認することをお勧めします。
無道路地を相続した人が前面の隣接地を所有している場合は無道路地の評価を受けられない
無道路地を相続した人が前面の隣接地を所有している場合は、無道路地の評価を適用することはできません。
無道路地を相続した人の親族が前面の隣接地を所有している場合は、原則として、無道路地の評価を受けられる
無道路地を相続した人の親族が前面の隣接地を所有している場合は、原則として、無道路地の評価を適用して構いません。
ただし、贈与、遺産分割等による宅地の分割が親族間等で行われた結果として無道路地が生じた場合は、無道路地の評価を適用することができず、その分割前の画地を1画地として評価します。
このように、相続税の仕組みや計算方法には難しい点がたくさんあります。正しく、そして不利益が出ないようにするために、ぜひ専門の税理士などに相談してみることをご検討ください。
無道路地の評価方法
無道路地の価額は、実際に利用している路線の路線価に基づき不整形地の評価(若しくは間口が狭小な宅地等の評価)又は地積規模の大きな宅地の評価によって計算した価額から、その価額の40%の範囲内において相当と認める金額を控除した価額によって評価します。
この場合の40%の範囲内において相当と認める金額は、接道義務に基づいて最小限度の通路を開設する場合のその通路に相当する部分の価額とされています。この通路部分の価額は、実際に利用している路線の路線価に、通路に相当する部分の地積を乗じた価額とし、奥行価格補正等の画地補正は行いません。
評価手順
評価手順を箇条書きにすると、次のようになります。
- 無道路地の奥行価格補正後の価額を計算
(1) 無道路地と前面宅地を合わせた土地の奥行価格補正後の価額を計算
(2) 前面宅地の奥行価格補正後の価額を計算
(3) (1)の価額から(2)の価額を控除して無道路地の奥行価格補正後の価額を計算 - 不整形地補正、又は、間口狭小・奥行長大補正
- (地積規模の大きな宅地に該当する場合のみ)地積規模補正
- 通路部分の価額の控除(控除上限40%)
次の図の事例を元に実際に計算してみます。
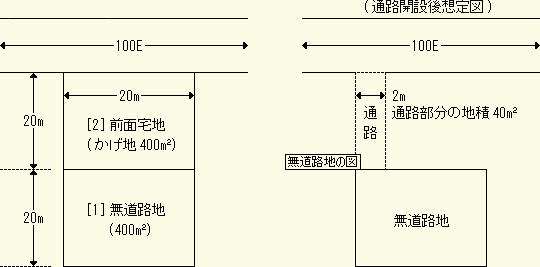
引用:国税庁「No.4620 無道路地の評価」
1.無道路地の奥行価格補正後の価額を計算
(1) 無道路地と前面宅地を合わせた土地の奥行価格補正後の価額を計算
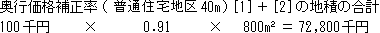
(2) 前面宅地の奥行価格補正後の価額を計算
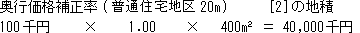
(3) (1)の価額から(2)の価額を控除して無道路地の奥行価格補正後の価額を計算
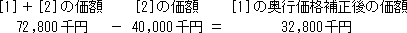
2.不整形地補正、又は、間口狭小・奥行長大補正
- 不整形地補正率:0.79(普通住宅地区・地積区分A・かげ地割合 50%)
※かげ地割合:(800㎡-400㎡)÷800㎡=50% - 間口狭小補正率:0.90(間口距離2m)
- 奥行長大補正率:0.90(間口距離2m・奥行距離40m)
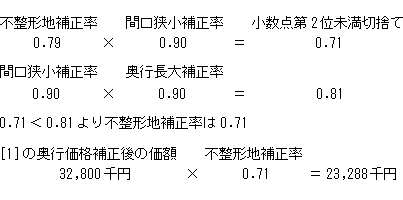
※1~2は国税庁ウェブサイトの「No.4620 無道路地の評価」を加工して遺産相続弁護士ガイド作成
▼不整形地補正について詳しく知りたい方におすすめの記事▼
▼間口狭小について詳しく知りたい方におすすめの記事▼
▼奥行長大補正について詳しく知りたい方におすすめの記事▼
3.(地積規模の大きな宅地に該当する場合のみ)地積規模補正
このケースでは地積規模の大きな宅地に該当しないので、そのまま次の項目へ。
地積規模の大きな宅地の評価については以下の記事で詳しく説明しています。
4.通路部分の価額の控除

通路部分の価額は、控除限度額(控除前の価額の40%)よりも小さいので、通路部分の価額を控除します。
![]()
※国税庁ウェブサイトの「No.4620 無道路地の評価」を加工して遺産相続弁護士ガイド作成
道路に接していても接道義務が満たしていない場合の評価方法
道路に接していてもその接する間口距離が接道義務を満たしていない宅地については、建物の建築に著しい制限を受けるなどの点で、無道路地と同様にその利用価値が低くなることから、無道路地と同様に評価します。
この場合の無道路地としての控除額は接道義務に基づいて最小限度の通路に拡幅する場合の、その拡幅する部分に相当する価額(正面路線価に通路拡幅部分の地積を乗じた価額)とされています。
まとめ
以上、無道路地の評価について説明しました。
土地の評価に関しては様々なルールがあり、一般の方が抜け漏れなくすべてのルールを適用させることは極めて難しいものです。
一般の方がご自分で土地の評価をしたがために、土地の評価方法を間違ってしまい税務調査によって過少申告が指摘され追徴課税がなされたり、反対に高く評価してしまい税額も高くなってしまったり(この場合、税務署は「もっと安くなりますよ」とは言ってくれません)といったケースが多数生じています。
また、税理士でも、土地の評価に精通した税理士と、そうでない税理士では、評価額に大きな差が生じます。
土地の評価に精通した税理士なら、あらゆる評価減の制度を駆使して、評価額を目一杯下げることが可能です。
土地や土地の上に存する権利を相続や贈与によって取得した場合、税の申告は、土地の評価に精通した税理士に相談して進めることをお勧めします。
この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
ご希望の地域の専門家を探す


























