不整形地とは?奥行・間口の取り方と補正率表の見方、評価方法

[ご注意]
記事は、公開日(2020年8月21日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
目次
不整形地とは?不整形地の評価の適用要件は?
不整形地とは、整形地(長方形(正方形も含む)の土地)ではない土地のことをいいます。 ただし、次のいずれかに該当する場合は、不整形地としての評価が行えません。- 倍率地域にある場合
- かげ地割合が10%未満の場合(かげ地割合については後述)
- 次の図のような帯状部分を有する場合
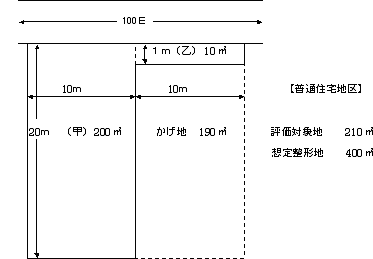
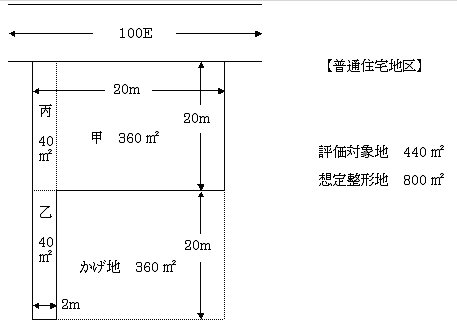 2及び3の場合の評価方法については後述します。ここでは1について説明します。
土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、不整形地補正を行うのは路線価方式によって評価する場合のみです。評価対象の土地が倍率地域にある場合は、倍率方式によって評価しますが、倍率方式の場合は不整形地補正を行いません。しがたって、倍率地域にある場合は、この記事をこれ以上読み進める必要はありません。
具体的な方法については、関連記事をご覧ください。
2及び3の場合の評価方法については後述します。ここでは1について説明します。
土地の評価方法には、路線価方式と倍率方式があり、不整形地補正を行うのは路線価方式によって評価する場合のみです。評価対象の土地が倍率地域にある場合は、倍率方式によって評価しますが、倍率方式の場合は不整形地補正を行いません。しがたって、倍率地域にある場合は、この記事をこれ以上読み進める必要はありません。
具体的な方法については、関連記事をご覧ください。
不整形地の評価方法
不整形地の価額は、後述の4つのいずれかの方法により、奥行価格補正などによって計算した価額に、その不整形の程度、位置及び地積の大小に応じ、地区区分及び地積区分に応じた「不整形地補正率表」に定める補正率を乗じて計算した価額により評価します。奥行価格補正
奥行価格補正は、正面路線からの奥行距離が短い又は長い土地の価額を低く補正する制度です。不整形地の奥行距離の取り方
奥行価格補正を行うためには奥行距離の算定が必要ですが、不整形地の奥行距離の算定ルールについて説明します。 次の図のような不整形地の奥行距離はどのようにして求めるのでしょうか。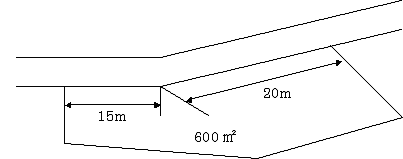 奥行距離が一様でないものは平均的な奥行距離によります。具体的には、不整形地にかかる想定整形地の奥行距離を限度として、その不整形地の面積をその間口距離で除して得た数値とします。
上の図のような不整形地にかかる想定整形地は次のとおりとなります。したがって、この不整形地の奥行距離は17.1m(600 ÷35m=17.1<20)となります。
奥行距離が一様でないものは平均的な奥行距離によります。具体的には、不整形地にかかる想定整形地の奥行距離を限度として、その不整形地の面積をその間口距離で除して得た数値とします。
上の図のような不整形地にかかる想定整形地は次のとおりとなります。したがって、この不整形地の奥行距離は17.1m(600 ÷35m=17.1<20)となります。
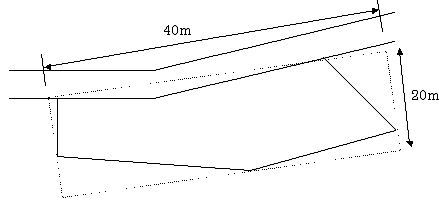 一般に不整形地について、その奥行距離を図示すれば次のようになります。
一般に不整形地について、その奥行距離を図示すれば次のようになります。
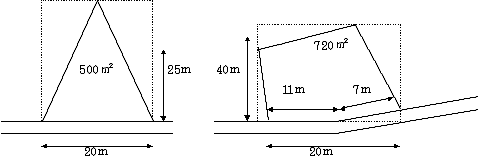
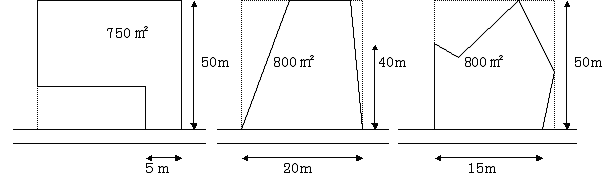
不整形地の想定整形地の取り方
想定整形地とは、評価対象地の画地全域を囲む、正面路線に面する最小面積の長方形となっているものをいいます。 例えば、下の図の画地(実線で囲った部分)の想定整形地は、破線で囲った部分になります。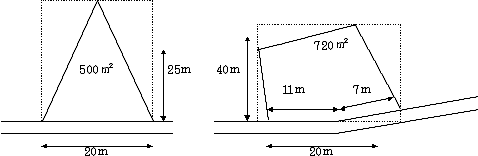
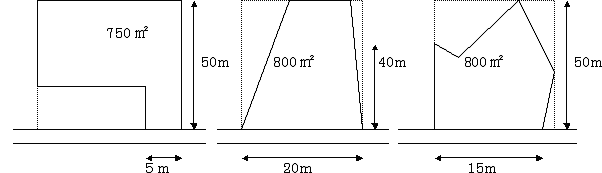
不整形地の間口距離の取り方
次の図のような形状の宅地の間口距離はいずれによるのでしょうか。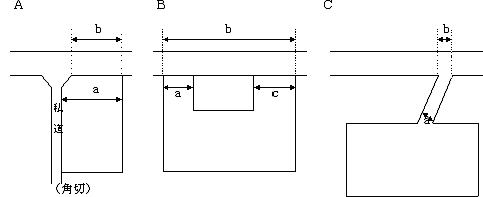 間口距離は、原則として道路と接する部分の距離によります。したがって、Aの場合はa、Bの場合はa+cによります。Cの場合はbによりますが、aによっても差し支えありません。
また、Aの場合で私道部分を評価する際には、角切で広がった部分は間口距離に含めません。
宅地が屈折路に面している場合の間口距離はどのようにして求めるのでしょうか。
屈折路に面する不整形地の間口距離は、その不整形地に係る想定整形地の間口に相当する距離と、屈折路に実際に面している距離とのいずれか短い距離となります。
このことから、Aの場合にはa(<「b+c」)が、Bの場合には「b+c」(<a)がそれぞれ間口距離となります。
間口距離は、原則として道路と接する部分の距離によります。したがって、Aの場合はa、Bの場合はa+cによります。Cの場合はbによりますが、aによっても差し支えありません。
また、Aの場合で私道部分を評価する際には、角切で広がった部分は間口距離に含めません。
宅地が屈折路に面している場合の間口距離はどのようにして求めるのでしょうか。
屈折路に面する不整形地の間口距離は、その不整形地に係る想定整形地の間口に相当する距離と、屈折路に実際に面している距離とのいずれか短い距離となります。
このことから、Aの場合にはa(<「b+c」)が、Bの場合には「b+c」(<a)がそれぞれ間口距離となります。
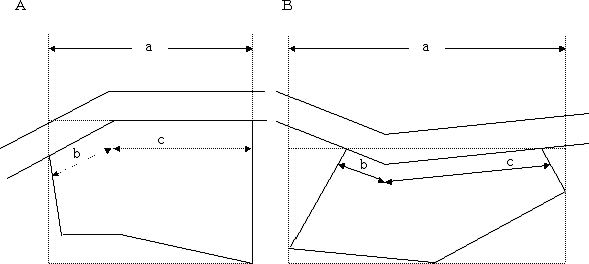 なお、屈折路に面する不整形地に係る想定整形地は、いずれかの路線からの垂線によって又は路線に接する両端を結ぶ直線によって、評価しようとする宅地の全域を囲むく形又は正方形のうち最も面積の小さいものとします。
このように、相続手続きには理解の難しい仕組みや制度がたくさんあります。正しく、そして不利益が出ないようにするために、ぜひ専門家に相談してみることをご検討ください。
なお、屈折路に面する不整形地に係る想定整形地は、いずれかの路線からの垂線によって又は路線に接する両端を結ぶ直線によって、評価しようとする宅地の全域を囲むく形又は正方形のうち最も面積の小さいものとします。
このように、相続手続きには理解の難しい仕組みや制度がたくさんあります。正しく、そして不利益が出ないようにするために、ぜひ専門家に相談してみることをご検討ください。
不整形地補正率表
不整形地補正率表は以下のとおりです。| 地区区分 | 高度商業地区、繁華街地区、普通商業・併用住宅地区、中小工場地区 | 普通住宅地区 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地積区分 | A | B | C | A | B | C |
| かげ地割合 | ||||||
| 10%以上 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| 15%以上 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 0.96 | 0.98 | 0.99 |
| 20%以上 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.94 | 0.97 | 0.98 |
| 25%以上 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.92 | 0.95 | 0.97 |
| 30%以上 | 0.94 | 0.97 | 0.98 | 0.90 | 0.93 | 0.96 |
| 35%以上 | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 0.88 | 0.91 | 0.94 |
| 40%以上 | 0.90 | 0.93 | 0.97 | 0.85 | 0.88 | 0.92 |
| 45%以上 | 0.87 | 0.91 | 0.95 | 0.82 | 0.85 | 0.90 |
| 50%以上 | 0.84 | 0.89 | 0.93 | 0.79 | 0.82 | 0.87 |
| 55%以上 | 0.80 | 0.87 | 0.90 | 0.75 | 0.78 | 0.83 |
| 60%以上 | 0.76 | 0.84 | 0.86 | 0.70 | 0.73 | 0.78 |
| 65%以上 | 0.70 | 0.75 | 0.80 | 0.60 | 0.65 | 0.70 |
| 地積区分 \ 地区区分 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 高度商業地区 | 1,000㎡未満 | 1,000㎡以上 1,500㎡未満 | 1,500㎡以上 |
| 繁華街地区 | 450㎡未満 | 450㎡以上 700㎡未満 | 700㎡以上 |
| 普通商業・併用住宅地区 | 650㎡未満 | 650㎡以上 1,000㎡未満 | 1,000㎡以上 |
| 普通住宅地区 | 500㎡未満 | 500㎡以上 750㎡未満 | 750㎡以上 |
| 中小工場地区 | 3,500㎡未満 | 3,500㎡以上 5,000㎡未満 | 5,000㎡以上 |
不整形地の4つの評価方法
不整形地の評価方法には以下で説明する4つがあります。 複数の方法が適用可能な場合、最も有利な(価額が低くなる)方法を採用して構いません。区分した整形地を基として評価する方法
次の図のような不整形地はどのように評価するのでしょうか。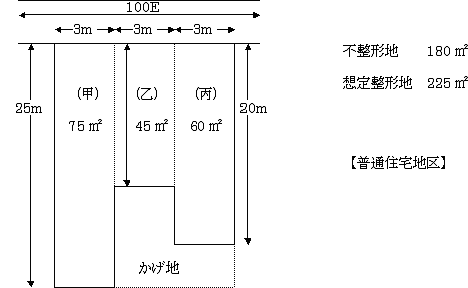 不整形地を区分して求めた整形地を基として計算した価額の合計額に、不整形地補正率を乗じて評価します。
(計算例)
1 不整形地を整形地に区分して個々に奥行価格補正を行った価額の合計額
不整形地を区分して求めた整形地を基として計算した価額の合計額に、不整形地補正率を乗じて評価します。
(計算例)
1 不整形地を整形地に区分して個々に奥行価格補正を行った価額の合計額
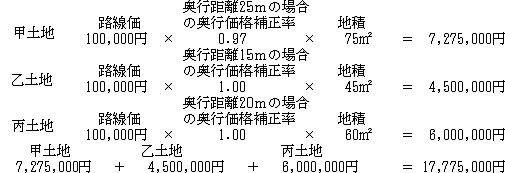 2 不整形地補正率
不整形地補正率 0.94(普通住宅地区 地積区分A かげ地割合20%)
2 不整形地補正率
不整形地補正率 0.94(普通住宅地区 地積区分A かげ地割合20%)
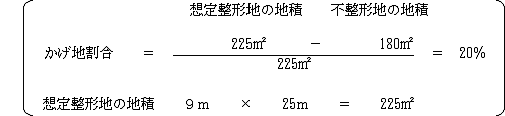 3 評価額
3 評価額
計算上の奥行距離を基として評価する方法
次の図のような不整形地はどのように評価するのでしょうか。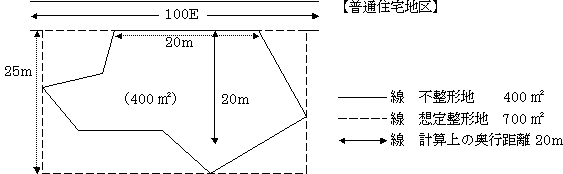 不整形地の地積を間口距離で除して算出した計算上の奥行距離を基として求めた整形地としての価額に、不整形地補正率を乗じて評価します。
不整形地の地積を間口距離で除して算出した計算上の奥行距離を基として求めた整形地としての価額に、不整形地補正率を乗じて評価します。
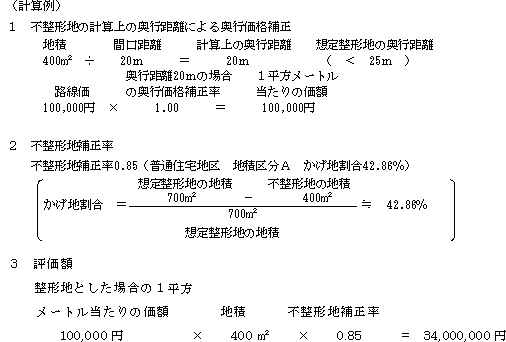
近似整形地を基として評価する方法
次の図のような不整形地はどのように評価するのでしょうか。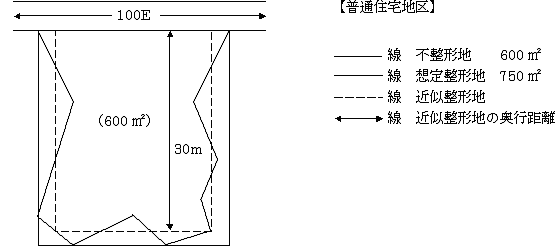 不整形地に近似する整形地を求め、その近似整形地を基として求めた価額に不整形地補正率を乗じて評価します。
(注意事項)
不整形地に近似する整形地を求め、その近似整形地を基として求めた価額に不整形地補正率を乗じて評価します。
(注意事項)
- 近似整形地は、近似整形地からはみ出す不整形地の部分の地積と近似整形地に含まれる不整形地以外の部分の地積がおおむね等しく、かつ、その合計地積ができるだけ小さくなるように求めます。
- 近似整形地の屈折角は90度とします。
- 近似整形地と想定整形地の地積は必ずしも同一ではありません。
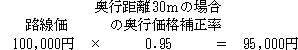 2 不整形地補正率
2 不整形地補正率
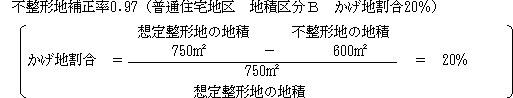 3 評価額
3 評価額
差引き計算により評価する方法
次の図のような不整形地はどのように評価するのでしょうか。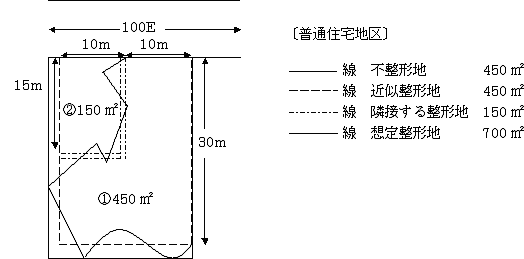 近似整形地(1)を求め、隣接する整形地(2)と合わせて全体の整形地の価額の計算をしてから隣接する整形地(2)の価額を差し引いた価額を基として計算した価額に、不整形地補正率を乗じて評価します。
(計算例)
1 近似整形地(1)と隣接する整形地(2)を合わせた全体の整形地の奥行価格補正後の価額
近似整形地(1)を求め、隣接する整形地(2)と合わせて全体の整形地の価額の計算をしてから隣接する整形地(2)の価額を差し引いた価額を基として計算した価額に、不整形地補正率を乗じて評価します。
(計算例)
1 近似整形地(1)と隣接する整形地(2)を合わせた全体の整形地の奥行価格補正後の価額
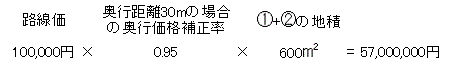 2 隣接する整形地(2)の奥行価格補正後の価額
2 隣接する整形地(2)の奥行価格補正後の価額
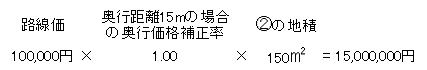 3 1の価額から2の価額を控除して求めた近似整形地(1)の奥行価格補正後の価額
3 1の価額から2の価額を控除して求めた近似整形地(1)の奥行価格補正後の価額
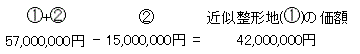 4 近似整形地の奥行価格補正後の1平方メートル当たりの価額(不整形地の奥行価格補正後の1平方メートル当たりの価額)
4 近似整形地の奥行価格補正後の1平方メートル当たりの価額(不整形地の奥行価格補正後の1平方メートル当たりの価額)
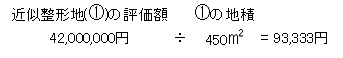 5 不整形地補正率
5 不整形地補正率
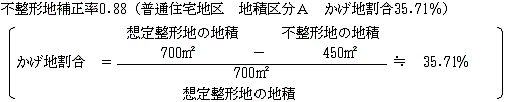 6 評価額
6 評価額
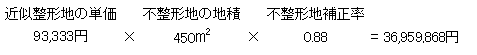 (注意事項)
(注意事項)
- 近似整形地を設定する場合、その屈折角は90度とします。
- 想定整形地の地積は、近似整形地の地積と隣接する整形地の地積との合計と必ずしも一致しません。
- 全体の整形地の価額から差し引く隣接する整形地の価額の計算に当たって、奥行距離が短いため奥行価格補正率が00未満となる場合においては、当該奥行価格補正率は1.00とします。 ただし、全体の整形地の奥行距離が短いため奥行価格補正率が1.00未満の数値となる場合には、隣接する整形地の奥行価格補正率もその数値とします。
不整形地の側方路線影響加算の計算例
側方路線影響加算とは、正面と側方の路線に接している土地(角地)を評価する際に、側方路線に接していることが土地の価値に与える影響を加味して、評価額に加算する制度です。 ここでは、不整形地の場合の側方路線影響加算の計算例について説明します。 次の図のような不整形地の評価額は、具体的にはどのようにして計算するのでしょうか。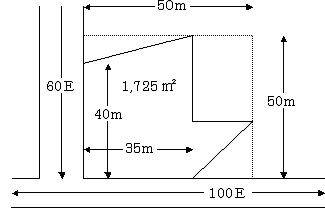 不整形地の地積を間口距離で除して算出した計算上の奥行距離を基とし、側方路線影響加算、不整形地補正を行い評価します。
(計算例)
1 不整形地の計算上の奥行距離による奥行価格補正
(1) 正面路線に対応する奥行距離………49.3m
不整形地の地積を間口距離で除して算出した計算上の奥行距離を基とし、側方路線影響加算、不整形地補正を行い評価します。
(計算例)
1 不整形地の計算上の奥行距離による奥行価格補正
(1) 正面路線に対応する奥行距離………49.3m
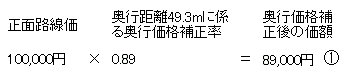 (2) 側方路線影響加算を行う場合の奥行距離………43.2m
(2) 側方路線影響加算を行う場合の奥行距離………43.2m
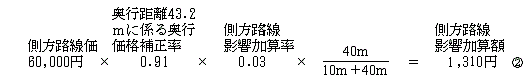 (4) 側方路線影響加算後の価額
(4) 側方路線影響加算後の価額
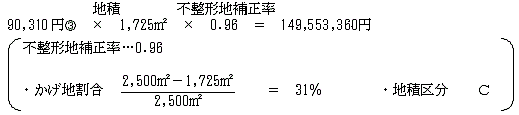 (注) 「地積規模の大きな宅地の評価」については、考慮しないこととして計算しています。
(注) 「地積規模の大きな宅地の評価」については、考慮しないこととして計算しています。
不整形地の正面路線の判定方法
次のような不整形地甲は、いずれの路線が正面路線となるのでしょうか。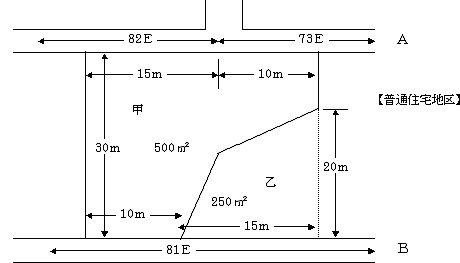 正面路線は、原則として、その宅地の接する路線の路線価(一路線に2以上の路線価が付されている場合には、路線に接する距離により加重平均した価額)に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線となります。
この場合における奥行価格補正率を適用する際の奥行距離は、不整形地の場合には、その不整形地に係る想定整形地の奥行距離を限度として、不整形地の面積を間口距離で除して得た数値とします。したがって、事例の場合には、A路線からみた場合の奥行距離は20m(500 ÷25m=20m<30m)、B路線からみた場合の奥行距離は30m(500 ÷10m=50m>30m)となります。
これらのことから、事例の場合には、次のとおりA路線を正面路線と判定することになります。
正面路線は、原則として、その宅地の接する路線の路線価(一路線に2以上の路線価が付されている場合には、路線に接する距離により加重平均した価額)に奥行価格補正率を乗じて計算した金額の高い方の路線となります。
この場合における奥行価格補正率を適用する際の奥行距離は、不整形地の場合には、その不整形地に係る想定整形地の奥行距離を限度として、不整形地の面積を間口距離で除して得た数値とします。したがって、事例の場合には、A路線からみた場合の奥行距離は20m(500 ÷25m=20m<30m)、B路線からみた場合の奥行距離は30m(500 ÷10m=50m>30m)となります。
これらのことから、事例の場合には、次のとおりA路線を正面路線と判定することになります。
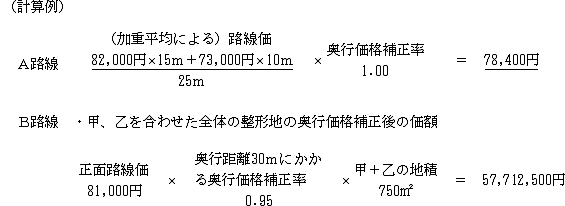
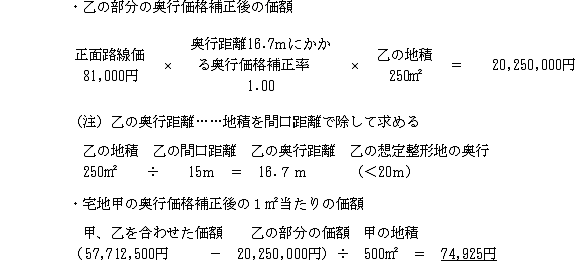
不整形地としての評価を行わない場合
事例1
次の図のような帯状部分を有する宅地はどのように評価するのでしょうか。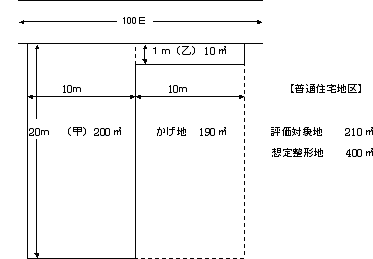 帯状部分(乙)とその他部分(甲)に分けて評価した価額の合計額により評価し、不整形地としての評価は行いません。
(計算例)
1 甲土地の評価額
帯状部分(乙)とその他部分(甲)に分けて評価した価額の合計額により評価し、不整形地としての評価は行いません。
(計算例)
1 甲土地の評価額
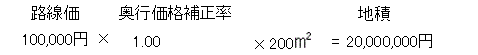 2 乙土地の評価額
2 乙土地の評価額
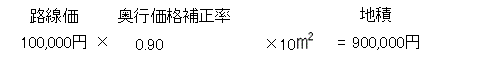 3 評価額
3 評価額
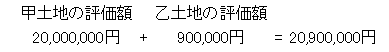 (参考)
評価対象地を不整形地として評価するとした場合
(参考)
評価対象地を不整形地として評価するとした場合
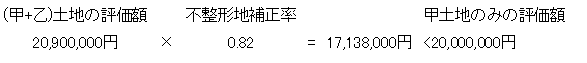
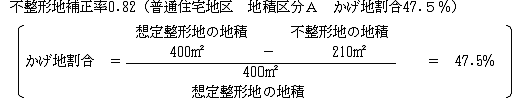 このように、帯状部分を有する土地について、形式的に不整形地補正を行うとかげ地割合が過大となり、帯状部分以外の部分を単独で評価した価額(20,000千円)より低い不合理な評価額となるため、不整形地としての評価は行いません。
このように、帯状部分を有する土地について、形式的に不整形地補正を行うとかげ地割合が過大となり、帯状部分以外の部分を単独で評価した価額(20,000千円)より低い不合理な評価額となるため、不整形地としての評価は行いません。
事例2
次の図のような帯状部分を有する宅地はどのように評価するのでしょうか。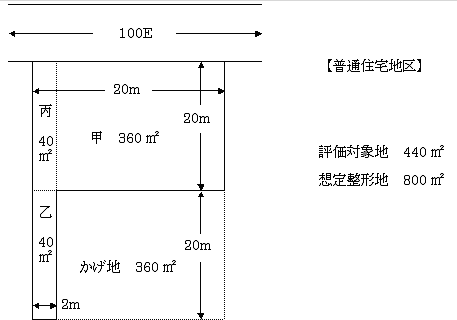 帯状部分(乙)とその他部分(甲・丙)に分けて評価した価額の合計額により評価し、不整形地としての評価は行いません。
(計算例)
1 甲、丙土地を合わせて評価した価額
帯状部分(乙)とその他部分(甲・丙)に分けて評価した価額の合計額により評価し、不整形地としての評価は行いません。
(計算例)
1 甲、丙土地を合わせて評価した価額
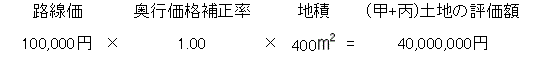 2 乙土地の評価額
(1) 乙、丙土地を合わせた土地の奥行価格補正後の価額
2 乙土地の評価額
(1) 乙、丙土地を合わせた土地の奥行価格補正後の価額
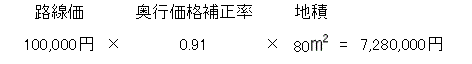 (2) 丙土地の奥行価格補正後の価額
(2) 丙土地の奥行価格補正後の価額
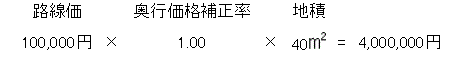 (3) (1)の価額から(2)の価額を差し引いて求めた乙土地の奥行価格補正後の価額
(3) (1)の価額から(2)の価額を差し引いて求めた乙土地の奥行価格補正後の価額
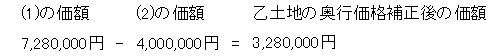 (4) 乙土地の評価額
(4) 乙土地の評価額
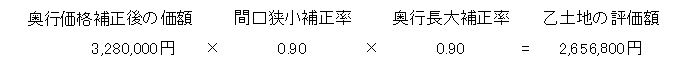 3 評価額
3 評価額
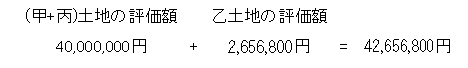 (参考)
評価対象地を不整形地として評価するとした場合
1 甲地の奥行価格補正後の価額
(参考)
評価対象地を不整形地として評価するとした場合
1 甲地の奥行価格補正後の価額
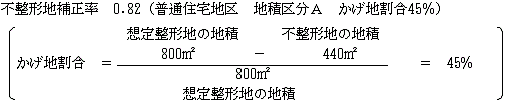 4 評価額
4 評価額
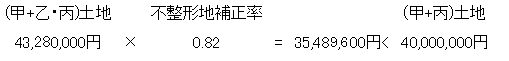 このように、帯状部分を有する土地について、形式的に不整形地補正を行うとかげ地割合が過大となり、帯状部分以外の部分を単独で評価した価額(40,000千円)より低い不合理な評価額となるため、不整形地としての評価は行いません。
このように、帯状部分を有する土地について、形式的に不整形地補正を行うとかげ地割合が過大となり、帯状部分以外の部分を単独で評価した価額(40,000千円)より低い不合理な評価額となるため、不整形地としての評価は行いません。
不整形地補正、奥行長大補正、間口狭小補正に関するルール
奥行が長大な土地に対する補正(奥行長大補正)と、不整形地補正は併用することはできず、どちらかを選択して適用することになります。 「不整形地補正率表の補正率×間口狭小補正率」の値を「不整形地補正率」とし、「不整形地補正率」は、下限を0.6とし、小数点以下2位未満を切捨てして算出します。 「不整形地補正率表の補正率」に代えて「奥行長大補正率」を適用する場合は、「奥行長大補正率×間口狭小補正率」の値を「不整形地補正率」とし、同様に小数点以下2位未満を切捨てして算出します(なお、「奥行長大補正率×間口狭小補正率」の値が0.6を下回ることはありません)。 なお、不整形地に該当しない場合は、「奥行長大補正率×間口狭小補正率」の値の小数点以下2位未満を切捨てする必要はありません。不整形地の評価を適用する場合の相続税の申告書類
かつては、不整形地の評価を適用する場合は「不整形地補正率等及びがけ地補正率の計算明細書」の作成が必要でしたが、現在は、これは廃止され、「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」の中で不整形地についても計算するようになっています。 「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」については、こちらの記事をご覧ください。不整形地の評価に利用できるフリーソフトはある?
これまでの説明を読んで、不整形地の評価は複雑で、自分で行うには荷が重いと思った方もいるでしょう。 それでは、不整形地の評価に利用できるフリーソフト(無料のソフト)はあるのでしょうか? この点、そのようなフリーソフトは見当たりません。 税理士向けの有償ソフトは存在するのですが、税理士向けに作られているので、一般の方が使いこなすのは難しいでしょう。まとめ
以上、不整形地について説明しました。 土地の評価に関しては様々なルールがあり、一般の方が抜け漏れなくすべてのルールを適用させることは極めて難しいものです(他のルールについては、関連記事をご覧ください) 一般の方がご自分で土地の評価をしたがために、土地の評価方法を間違ってしまい税務調査によって過少申告が指摘され追徴課税がなされたり、反対に高く評価してしまい税額も高くなってしまったり(この場合、税務署は「もっと安くなりますよ」とは言ってくれません)といったケースが多数生じています。 また、税理士でも、土地の評価に精通した税理士と、そうでない税理士では、評価額に大きな差が生じます。 土地の評価に精通した税理士なら、あらゆる評価減の制度を駆使して、評価額を目一杯下げることが可能です。 土地や土地の上に存する権利を相続や贈与によって取得した場合、税の申告は、土地の評価に精通した税理士に相談して進めることを強くお勧めします。この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
ご希望の地域の専門家を探す




























