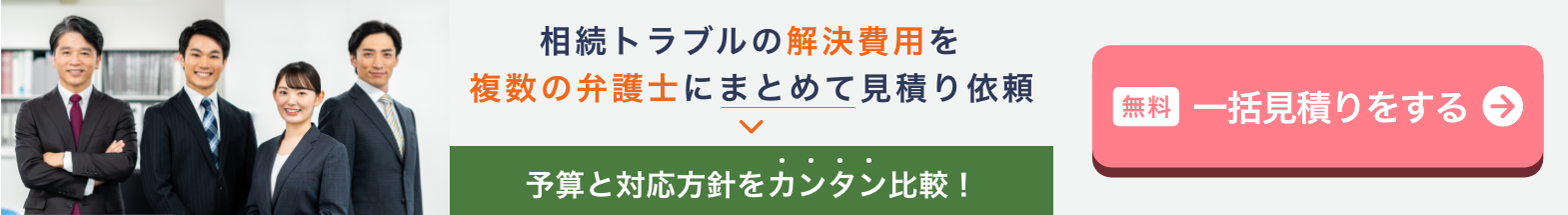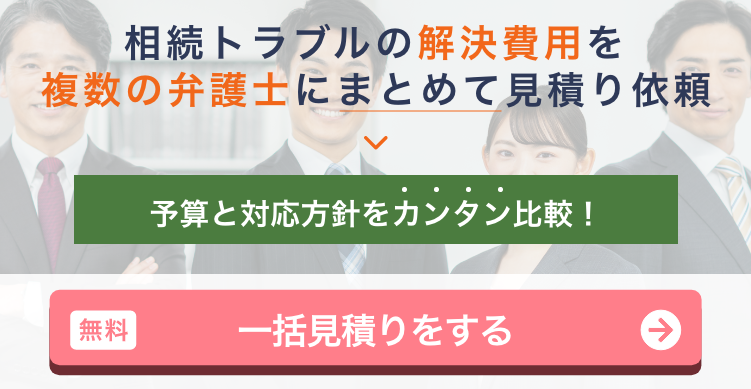失踪宣告の手続の流れと注意点、失踪者が見つかった場合の取消方法

家族や親族などの近しい人の行方がわからなくなって久しいとき、失踪宣告を受けることができます。失踪宣告とは、一定期間以上失踪していて生死がわからない状況の人に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じさせる制度のことです。実は、失踪宣告をすることによって相続などの手続きがスムーズになることがあります。逆に言うと失踪宣告をしないと死亡保険金や遺産を受け取ることができないのです。
この記事では、失踪宣告の手続きや認定死亡との違いなど、知っておきたいポイントをまとめました。是非、参考にしてください。
[ご注意]
記事は、公開日(2018年11月15日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください
目次
失踪宣告とは?
失踪宣告とは、一定期間以上失踪していて、生きているか死んでいる分からない状況の人に対して、法律上死亡したものとみなす効果を生じされる制度のことです。
失踪宣告は何のためにするの?
失踪宣告を受けると、前述のとおり、法律上死亡したものとみなす効果が生じます。
法律上死亡したものとみなされると、次のようなことが可能になります。
- 婚姻の解消
- 相続の開始
- 相続人からの除外
- 死亡保険金の請求
以下、それぞれについて説明します。
婚姻の解消
生きている配偶者との婚姻関係を解消したい場合は、離婚届を役所に提出して離婚します。
配偶者が死亡した場合は、当然に婚姻関係は解消されます。
配偶者が行方不明の場合は、婚姻関係を解消したくても、いない人と離婚協議をすることはできません。
このような場合にいつまでも婚姻関係が解消できないと、再婚することもできませんし、残された人が女性の場合は、別の人との間に子供ができた場合、法律上、行方不明の夫との間の子供だと推定されてしまいます。
失踪宣告を受ければ、婚姻を解消することができ、残された人が新たな人生を踏み出すことが可能になります。
なお、失踪宣告によらなくても、離婚訴訟によって離婚することは可能です。
3年以上生死不明の場合は離婚原因となるので、失踪宣告よりも早く(普通失踪の場合は7年以上生死不明でなければ認められない)婚姻関係を解消することができます。
相続の開始
相続の開始は、通常、被相続人が死亡した時ですが、失踪宣告を受けた場合も、同様に相続が開始されます。
相続人からの除外
共同相続人が失踪して行方が分からない場合、他の共同相続人が遺産分割について協議することができず、困ってしまいます。
なお、失踪期間が短く失踪宣告の要件を満たさない場合は、不在者財産管理人の選任によって、相続手続を進めることができます。
不在者財産管理人について詳しくは関連記事をご覧ください。
また、先順位の相続人が行方不明の場合、次順位の相続人は、自分が相続できるのかどうか分からず困ってしまいます。相続順位については、関連記事をご覧ください。
失踪者しか相続人となり得る人がいない場合でも、特別縁故者(相続人が誰もいない場合に遺産を取得できる被相続人と特別な縁故があった人が自分が遺産を取得できるかどうか分からずに困ってしまいますし、特別縁故者がいない場合でも、遺産が宙に浮いてしまって国庫に帰属させることもできずに社会経済上の損失が生じてしまいます。
このようなことにならないように、失踪宣告を受ければ、失踪者を相続人から除外することができます。
死亡保険金の請求
生命保険に加入している場合に、生死がはっきりせずに、死亡保険金を受け取ることができなければ、被保険者の収入によって生計が支えられていた遺族は困ってしまいます。
失踪宣告を受ければ、死亡したものとみなされ、死亡保険金を受け取ることができるようになります。
相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください
失踪宣告が認められるケース
失踪宣告が認められるのは、不在者が次のいずれかに該当するケースです。
- 生死が7年以上明らかでない
- 戦争、船舶の沈没、震災等の死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後、生死が1年以上明らかでない
前者を普通失踪、後者を特別失踪(または、危難失踪)といいます。
なお、不在者とは、従来の住所または居所を去り、容易に戻る見込みのない人のことを言います。
失踪宣告を受けると、いつ死亡したことになる?
失踪宣告を受けると死亡したものとみなされますが、いつ死亡したものとみなされるかは、普通失踪の場合と、特別失踪(危難失踪)の場合とで異なります。
具体的には下表の時点で死亡したものとみなされます。
| 普通失踪 | 特別失踪(危難失踪) |
|---|---|
| 失踪期間満了時(生死不明の状態が7年間継続した時) | 危難が去った時点 |
失踪宣告と認定死亡の違い
失踪宣告と似たものに認定死亡という制度があります。
両者は、死亡が未確認の場合に死亡したものと扱われるという点で共通しています。
認定死亡は、失踪宣告の中でも特別失踪と特に似ていますが、両者の違いは下表の通りです。
| 特別失踪 | 認定死亡 | |
|---|---|---|
| 認められるケース | 危難が去った後1年以上生死不明(死亡が確実でなくてもよい) | 遺体を発見できていないだけで、死亡が確実(危難が去った後すぐでも利用可能) |
| 認定機関 | 家庭裁判所 | 官公庁 |
| 取消方法 | 審判 | 生きていたことを証明するだけでよい |
失踪宣告を受けるには?
申立先
失踪宣告を受けるには、不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行います。従来の住所地も居所地も分からない場合は、東京家庭裁判所に申立てを行うことになります。
家庭裁判所の管轄は、こちらから調べられます。
申立てができる人
失踪宣告の申立てができるのは、失踪宣告を求めるについての法律上の利害関係がある人です。
例えば、次のような人です。
- 配偶者
- 相続人
- 受遺者
- 財産管理人
なお、単に事実上の利害関係があるに過ぎない次のような人は申立てることはできません。
- 配偶者の恋人
- 債権者
- 相続人や受遺者の債権者
- 相続人や受遺者の家族
- 友人
申立てに必要な書類
申立てには、次の書類が必要です。
- 家事審判申立書
- 不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 不在者の戸籍附票
- 失踪を証する資料
- 申立人の利害関係を証する資料
家事審判申立書の用紙は家庭裁判所で入手可能ですが、こちらからダウンロードして印刷し利用しても構いません。
記入に当たっては、こちらの記入例を参考にしてください。
戸籍謄本(全部事項証明書)と戸籍附票は、不在者の本籍地の市区町村役場で取得することができます。
利害関係人が失踪宣告の申立てのために取得する場合は、本人の委任状がなくても取得することができます。
失踪を証する資料とは、警察署長の発行する家出人届出受理証明書や返戻された不在者宛の手紙等が該当します。
申立人の利害関係を証する資料は、親族関係であれば戸籍謄本(全部事項証明書)です。
申立ての費用
申立てには次の費用が必要です(合計で数千円程度)。
- 収入印紙800円
- 官報公告料4298円(内訳:失踪に関する届出の催告2725円、失踪宣告1573円)
- 連絡用の郵便切手
申立費用は以上ですが、このほか、戸籍謄本、戸籍附票の交付を受けるための手数料が役場で必要になります。
戸籍謄本は1通450円、戸籍の附票は1通300円です。
相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください
申立て後の流れ
申立て後、概ね次のような流れで手続きが進められます。
- 調査
- 催告
- 失踪宣告
調査は、申立人や親族等に対して、家庭裁判所調査官が行います。
催告は、不在者は生存の届出をするように、不在者の生存を知っている人はその届出をするように、官報と裁判所の掲示板で行われなれます。
普通失踪の場合は3か月以上、危難失踪の場合は1か月以上が経過しても届出がない場合は、失踪宣告がなされます。
失踪宣告がなされたら失踪の届出が必要
失踪宣告の審判が確定したら、申立人は10日以内に、不在者の本籍地か申立人の住所地の市区町村役場に失踪の届出をしなければなりません。
届出には、審判書謄本と確定証明書が必要です。
確定証明書は、審判を行った家庭裁判所に申請します。
失踪の届出が受理されると、不在者の戸籍に失踪宣告がなされたことが記載されます。
失踪宣告にかかる期間と相続税の申告期限
失踪宣告の申立てから審判の確定までには、半年以上がかかります。
共同相続人に対する失踪宣告の場合、失踪宣告の有無によって、他の共同相続人の相続分や相続税額は変わってきます。
相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内です。
失踪宣告を待っていると、相続税の申告期限に間に合わないおそれがあります。
相続税の申告期限は、一定の条件を満たせば、2か月延長することもできますが、それではあまり猶予はありません。このような場合は、不在者財産管理人を選任し、相続税を申告してしまった方が無難でしょう。
失踪宣告確定後、相続税は修正申告することができます。
失踪宣告によって2つの相続が同時に進行することがある
失踪宣告によって2つの相続が同時に進行することがあります。
どういうことか、例を元に説明します。
事例
Aさんの祖父Bさんが亡くなりました。
Aさんの父Cさん(Bさんの子)は、本来、Bさんの相続人になるはずですが、ここ7年以上行方が分かりません。
BさんにはCさん以外に子はいません。Aさんは、Cさんの失踪宣告を申立て、Cさんの失踪が宣告されました。
失踪宣告によって、Cさんは行方不明になってから7年後に亡くなったものとみなされます。
失踪宣告によってCさんの相続が開始され、AさんはCさんの遺産の相続人となります。
また、Bさんが亡くなったのは、Cさんが行方不明になってから7年以上あとなので、法的な死亡順はCさん、Bさんの順になります。
Aさんは、CさんのBさんの相続人としての地位を代襲し、Bさんの遺産の相続人にもなります。
失踪宣告を取消すには?取り消すとどうなる?
失踪宣告を受けた人が生きていた場合や、失踪宣告による死亡時とは異なる時に死亡したことが判明した場合は、本人や利害関係人が、家庭裁判所に対して、失踪宣告の取消を請求ことによって、失踪宣告を取消すことができます。
失踪宣告は、取り消されるとはじめから失踪宣告がなかったことになります。
しかし、失踪宣告からその取消しまでの間に、本当は失踪者が生きていたことを知らずにした行為の影響を及ぼしません。
相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください
事例
例えば、Aさんが行方不明となり失踪宣告がなされたとします。
Aさんの妻であったBさんは、この失踪宣告によってAさんとの婚姻関係が解消されました。
失踪宣告後、BさんはCさんと結婚しました。
BさんとCさんの結婚後、実は生きていたAさんが、自分が失踪宣告を受けていることを知り、申立によって失踪宣告が取り消されました。
BさんとCさんが、Aさんが生きていたこと知ったのは、結婚した後です。
このような場合は、失踪宣告がなされても、AさんとBさんの婚姻関係は復活せず、BさんとCさんの婚姻関係は維持されると考えられています。
しかし、BさんとCさんが結婚した時に、二人のうちのどちらか一方でも、実はAさんが生きていることを知っていた場合は、AさんとBさんの婚姻が復活し、Bさんは重婚状態となると考えられています。
この場合、AさんはBさんと離婚するか、BさんとCさんの婚姻の取消を主張することができます。
なお、失踪宣告が取消された場合の婚姻関係については、以上の説明と異なる説も提唱されているため、実際には、裁判所が以上の説明と異なる判断をする可能性もありますのでご注意ください。
また、失踪宣告によって、相続が発生する等して財産を得た人は、失踪宣告が取り消された場合は、残っている財産の範囲で財産を返還すればよいことになっています(失踪宣告を受けた人が生きていることを知らなかった場合)。
先ほどとは別のケースで説明します。
Aさんに失踪宣告がなされ、BさんはAさんが所有していた土地を相続しました。
BさんはAさんから相続した土地を分割し(分割後の土地を甲と乙とします。)土地甲をCさんに売却しました。
土地乙はBさんが引き続き所有しています。
ところが、実はAさんが生きており、Aさんの失踪宣告は取消されました。
BさんもCさんも、土地甲を売買した時点では、Aさんが実は生きていたことを知りませんでした。
この場合、土地乙はBさんの下に残っているので、Aさんに返還しなければなりません。
しかし、土地甲については、CさんはAさんに返還する必要はありません。
BさんはCさんに土地甲を売却して得たお金を残っている範囲でAさんに返還すればよいことになります。
なお、BさんかCさんのどちらか一方でも売買時にAさんが生きていることを知っていた場合は、CさんはAさんに土地甲を返還しなければなりません(ただし、BさんだけがAさんが生きていることを知っていて、Cさんは知らなかったという場合については異論も唱えられています。)。
また、相続した財産が土地ではなく動産の場合は、Cさんだけ事情を知らず、知らないことについて過失がなければ、BさんがAさんが生きていることを知っていても、即時取得(民法第192条)という制度によって、CさんはAさんにその動産を返還しなくても良い場合があります。
相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください
この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
ご希望の地域の専門家を探す