連れ子に相続権がない?相続させるための2つの方法
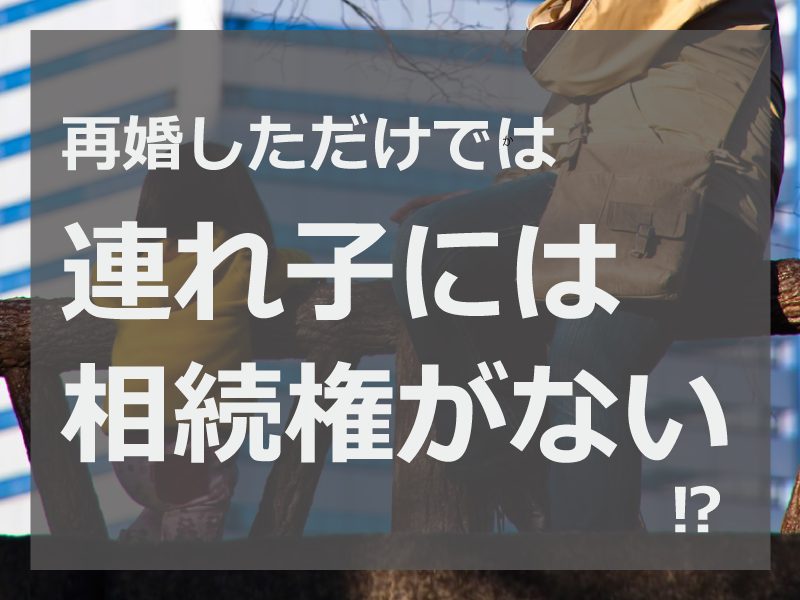
[ご注意]
記事は、公開日(2019年7月19日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
連れ子には相続権はない
設例を元に説明します。 A子とB男は結婚して、2人の間にCが生まれました。その後、A子とB男は離婚し、Cは、母であるA子が引き取りました。 やがて、A子はD男と結婚しました。Cを連れた、いわゆる子連れ再婚です。D男はCを我が子のように可愛がり、実の親子同然に暮らしていました。 しかし、ある時、不幸にもD男が亡くなってしまいました。その場合、CはD男の遺産の相続人となれるでしょうか? 残念ながら、基本的には、CはD男の相続人とはなれません。連れ子が遺産を相続できる2つの方法
しかし、Cには、D男の遺産を相続するための方法が2つあります。 一つは、D男と養子縁組をする方法、もう一つは、D男がCに遺贈する旨の遺言をする方法です。 以下、それぞれについて説明します。養子縁組
 連れ子に限らず、養子は養親の遺産を相続することができます。
D男とCが養子縁組をすることによって、CはD男の遺産を相続することができるようになります。
仮に、A子とD男が結婚しておらず事実婚(A子がD男の内縁の妻)であったとしても、CとD男が養子縁組をすることは問題なく、養子縁組をすることによって、CはD男の遺産を相続することができます。
連れ子に限らず、養子は養親の遺産を相続することができます。
D男とCが養子縁組をすることによって、CはD男の遺産を相続することができるようになります。
仮に、A子とD男が結婚しておらず事実婚(A子がD男の内縁の妻)であったとしても、CとD男が養子縁組をすることは問題なく、養子縁組をすることによって、CはD男の遺産を相続することができます。
法定相続分は実子と同じ
養子と実子の法定相続分に差はなく、養子には実子と同じ額の遺産を相続する権利があります。普通養子縁組と特別養子縁組
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。普通養子縁組とは?
普通養子縁組とは、通常の養子縁組のことで、わざわざ「普通」を付けなくても、単に「養子縁組」と言ったら、普通養子縁組のことを指しますが、特別養子縁組と区別するために、普通養子縁組と呼ばれることがあります。 普通養子縁組では、養親との間に法律上の親子関係が成立しますが、実親との親子関係が解消されるわけではなく、普通養子縁組によって養子となった人は、2組の親を持つことになります。 実親と養親の両方に対して、相続する権利や扶養を受ける権利(および義務)を持ちます。 このように普通養子縁組では、実親との親子関係が残るので、実親からも財産を相続できたり、養親だけで養子を十分に扶養できない事態になった場合には、養子は実親からも扶養を受けることができたりと、養子にとってメリットがあります。 余程の問題がない限りは、実親との関係を残しておいた方が、養子になる人にとってメリットがあるでしょうから、基本的には、普通養子縁組を検討することになるでしょう。 普通養子縁組は、離縁(養子縁組による親子関係を解消すること)することもできますが、離縁後は養方(養親及び養親を通じての親族)との親族関係は無くなり、養方の相続をすることはできません。 なお、離縁前に開始した相続については離縁は影響しません。養親の死後に離縁する死後離縁の場合は、養親の遺産を相続することに支障はありません。特別養子縁組とは?
一方、特別養子縁組とは、実親との親子関係を解消され、養親のみが法律上の親となる制度です。 実親の財産を相続する権利や、実親から扶養を受ける権利(および義務)は、特別養子縁組をすることによって無くなります。 このように、特別養子縁組は実親との親子関係を完全に断絶する制度です。 実親との親子関係を完全に断絶させた方が子にとって良いケースとしては、実親が、子を全く育てる気がないとか、虐待しているとか、経済的に極めて困窮していて育てようがないというようなケースがあり得ます。 具体的には、児童相談所や民間の養子縁組あっせん機関によるあっせんを受けて、親元で養育されていない子と特別養子縁組をするケースや、親が育てることができない親戚の子を引き取るケース、配偶者の連れ子で、もう一方の実親が養育費を一切支払わず危害を加えるおそれすらあるような場合に、再婚相手と連れ子の間で特別養子縁組をするケース等があります(連れ子のケースは実親が余程ひどくない限りは認められないようです)。 特別養子縁組によって実親との関係を断絶させるべきかどうかは、あくまで、養子となる子にとって、どちらが良いかという観点で考えなければなりません。 養親や実親の都合で考えるべきではありませんし、そのような考えで特別養子縁組を申し立てても認められにくいでしょう。 なお、特別養子縁組は原則として離縁することはできませんが、要件を満たせば、家庭裁判所が離縁を認めることがあります。 その場合、普通養子縁組と同様、離縁後は、養方の相続をすることはできませんが、離縁前に生じた相続には影響しません。また、特別養子縁組では実親との親子関係が消滅しますが、離縁によって復活します。 復活後は、実方(実の親族)の相続をすることができるようになります。しかし、特別養子縁組の離縁前に生じた実方の相続については、相続人となることはできません。 また、特別養子縁組前に実父の非嫡出子であった場合は、離縁後に実父に認知を請求することができ、認知されれば、実父を相続することができるようになります。連れ子の代襲相続はできる?
養子が亡くなった後、養親が亡くなった場合に、養子の子が代襲相続できるのかという問題があります。 この点については、養子縁組をした時点と養子の子が生まれた時点のいずれが早いかによって結論が異なります。 養子縁組後に生まれた場合は、代襲相続することができますが、生まれた後に養子縁組した場合は、代襲相続することはできません。養子縁組をしたときの相続税は?
相続税の基礎控除額は、以下の計算式で求めることができます。生命保険金の非課税
なお、法定相続人の数が増えると、基礎控除額だけでなく、生命保険金の非課税も増えます。生命保険金の非課税枠は、以下の計算式で求めることができます。遺贈
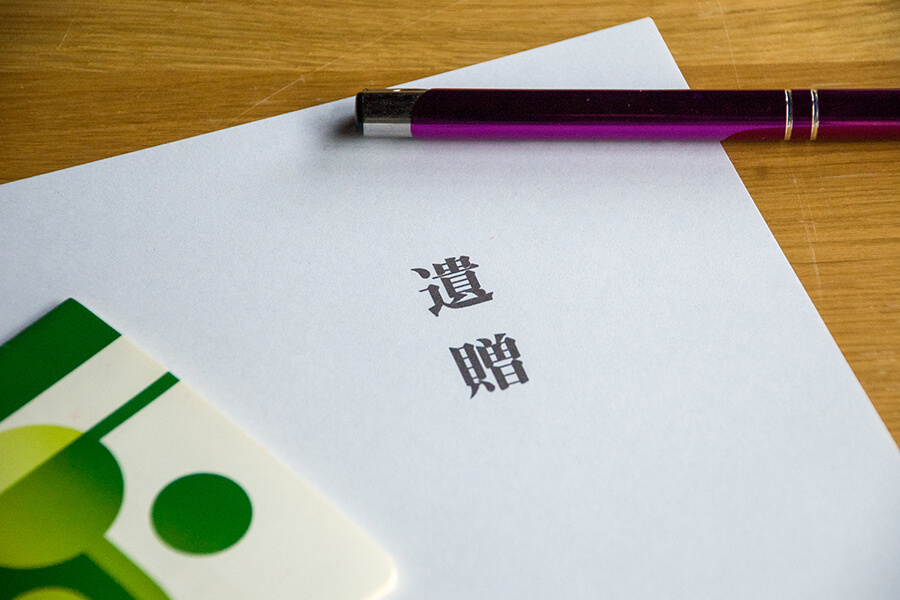 遺贈とは、遺言によって、自らの財産を無償で他人に与えることです。
遺贈は相続ではないので、「相続させる方法」として紹介すると不正確なのですが、遺産を取得させることができる手続きという意味では違いありません。
遺贈は、相続人に対してだけでなく、誰に対してでもすることができます。遺贈する場合は、遺贈する旨を遺言します。
遺贈は、遺言者の死亡の時から効力を生じます。遺言者の存命中には遺贈の効力は生じません。
また、受遺者となるはずであった人が被相続人(亡くなった人)よりも先に亡くなっても、受遺者となるはずであった人の子が代襲して受遺者となることはありません。
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。
遺贈とは、遺言によって、自らの財産を無償で他人に与えることです。
遺贈は相続ではないので、「相続させる方法」として紹介すると不正確なのですが、遺産を取得させることができる手続きという意味では違いありません。
遺贈は、相続人に対してだけでなく、誰に対してでもすることができます。遺贈する場合は、遺贈する旨を遺言します。
遺贈は、遺言者の死亡の時から効力を生じます。遺言者の存命中には遺贈の効力は生じません。
また、受遺者となるはずであった人が被相続人(亡くなった人)よりも先に亡くなっても、受遺者となるはずであった人の子が代襲して受遺者となることはありません。
遺贈には、包括遺贈と特定遺贈があります。
包括遺贈とは?
包括遺贈とは、財産の全部又は一部の割合を受遺者に与えるものです。 包括遺贈を受ける人を包括受遺者といいますが、包括受遺者は相続人と同一の権利義務を有します。 つまり、被相続人の権利義務を包括的に承継することから、包括受遺者は、相続財産に対して相続人とともに遺産共有の状態となり、債務も承継し、遺産分割に参加することになります。 包括遺贈の受遺者は、相続人と同様、遺贈の放棄(相続人でいうところの相続放棄)、受遺分の譲渡(相続人でいうところの相続分の譲渡)、受遺分の放棄(相続人でいうところの相続分の放棄)ができます。 遺贈の放棄は原則3か月の熟慮期間内に家庭裁判所に申述しなければなりません。 包括遺贈を放棄した場合、その受遺分は、各相続人が法定相続分に応じて相続権を取得します(他の包括受遺者の受遺分は増えません)。 包括遺贈について、以下の点にご注意ください。- 包括遺贈では寄与分や特別受益の規定の適用はない
- 包括受遺者は遺留分をもたない
特定遺贈とは?
特定遺贈とは、特定の財産を受遺者に与えるもの(割合で示されていない遺贈)です。 受遺者は、特定の財産を取得することができますが、それ以外の財産を取得することはなく、また、遺言に書かれていない債務を承継することもありません。 特定遺贈を放棄する場合は、包括遺贈の場合のような家庭裁判所での手続きは不要で、相続人等の遺贈義務者に放棄の意思表示をすれば足ります。 原則として、放棄に期間制限はありませんが、利害関係人が十分な期間を定めて催告したときは、その期間内に放棄の意思表示をしなければ承認したことになります。 また、相続開始前に、被相続人が特定遺贈の対象財産を手放していた場合は、遺言のその部分については無効になります。連れ子に遺産をあげるなら養子縁組と遺贈とどちらよい?
それでは、連れ子に遺産をあげる方法として、養子縁組と遺贈のどちらがよいのでしょうか? それぞれの特徴をまとめると、下の表のようになります。| 養子縁組 | 遺贈 | |
|---|---|---|
| 取得する遺産 | 法定相続分 ※遺言によって変更可能 | 遺言によって指定した内容 |
| 遺産を渡したくなくなった 場合の方法 |
|
遺言を書き換えるだけでよい |
| その他の影響 | 相互扶養義務が生じる | 特になし |
この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
ご希望の地域の専門家を探す



























