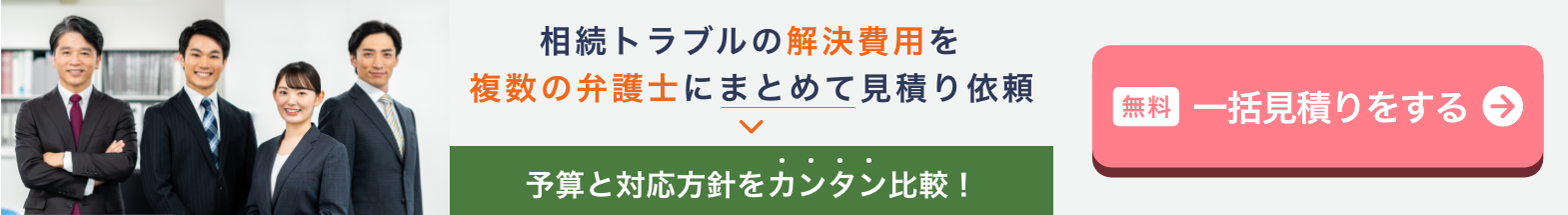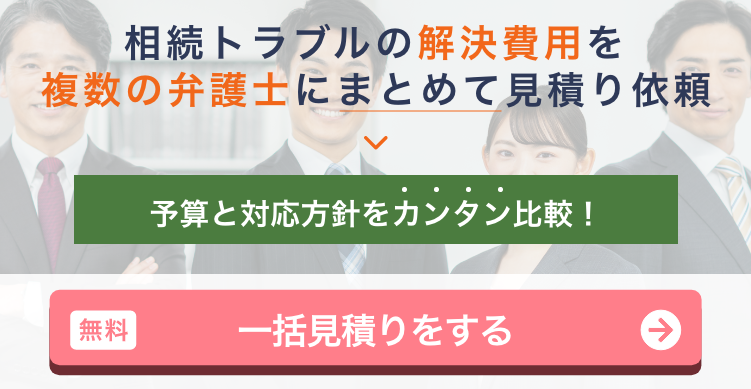兄弟へ遺留分侵害額請求はできる?遺留分について詳しく解説
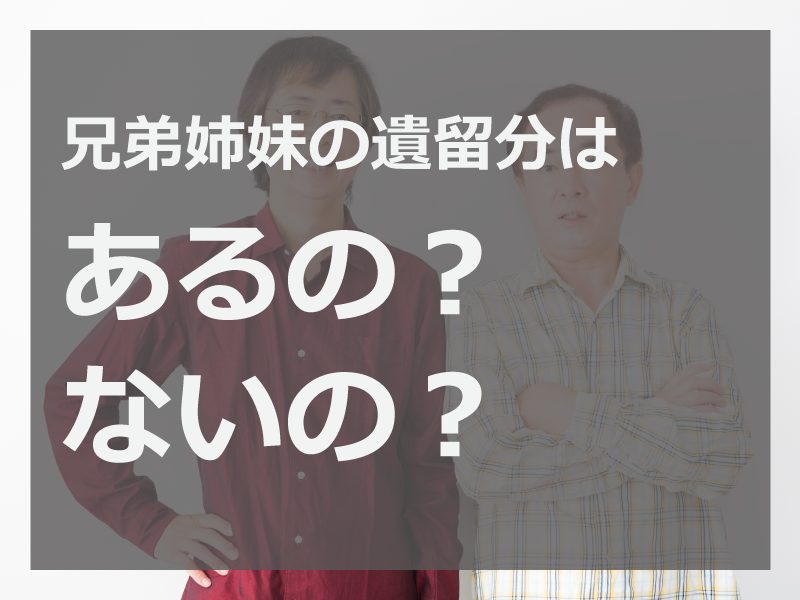
「遺留分 兄弟」というキーワードで検索をしたとき、まったく異なる次の2つの事柄の記事に行き当たります。
- 故人の兄弟姉妹の遺留分
- 親の相続における兄弟姉妹への遺留分侵害額請求
Google等の検索エンジンで「遺留分 兄弟」と検索した際に検索結果に表示されるページは、前者について解説したものと後者について解説したものが混在しているのです。
そこでこの記事では、前者と後者とに分けて、分かりやすく説明していきます。是非、参考にしてください。
[ご注意]
記事は、公開日(2019年1月11日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
遺留分とは?
遺留分と兄弟姉妹との関係の説明に移る前に、そもそも遺留分について簡単に説明しておきます。
遺留分とは、故人(被相続人)の配偶者や子など一定の範囲の相続人に留保された相続財産の割合のことです。
相続人となる人や各相続人の相続分については民法に定められていますが、これは遺言によって変更することができますし、生前贈与や死因贈与(贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与)によって相続財産が減ってしまったり無くなってしまったりすることもあります。
そのような場合に、民法では、一定の範囲の相続人に対して、法定相続分の一定割合を遺留分として相続できるようにしているのです。
そして、遺留分を侵害された人が、贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分侵害の限度で贈与や遺贈された財産の返還を請求することを遺留分侵害額請求と言います。
故人の兄弟姉妹には遺留分がない
結論から言うと、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。兄弟姉妹を代襲相続した甥や姪も同様に遺留分はありません。
被相続人に直径の親族がいない場合
被相続人に直系の親族(子、孫、父母、祖父母等)がいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。
この場合に被相続人に配偶者がいる場合は、兄弟姉妹と配偶者が、配偶者がいない場合は兄弟姉妹のみが相続人となります。
兄弟姉妹と配偶者のそれぞれの法定相続分(法で定められた相続割合)は、兄弟姉妹が4分の1、配偶者が4分の3です。兄弟姉妹が複数いる場合は、この4分の1をさらに按分します。
例えば、配偶者と兄と弟が相続人の場合のそれぞれの法定相続分は、配偶者が4分の3、兄が8分の1、弟が8分の1となります。
甥と姪には相続する?

このとき、例えば兄が被相続人よりも先に死亡していて、兄の長男と長女(被相続人の甥と姪)がいる場合、甥と姪が兄の相続人としての立場を代襲して相続人となります。
この場合の甥と姪の法定相続分は、兄の8分の1の相続分を2分の1ずつ按分するので、16分の1(1/8×1/2)ずつになります。
このように被相続人の兄弟姉妹やその代襲相続人である甥や姪は相続人となることがありますが、その場合でも前述の通り遺留分はありません。
つまり、例えば、被相続人が配偶者に全財産を相続させる旨の遺言をしていた場合は、兄弟姉妹は相続人であっても一銭も遺産を取得できないことになります。
このような場合に兄弟姉妹が遺産を取得できる可能性があるとすれば、例えば、遺言が無効であるような場合です。
遺言が無効となる場合について詳しくは以下の記事を参考にしてください。
遺言は正しく書き、正しく遺さなければ意味がありません。遺言の作成に迷ったりわからなことがある方は、専門の士業に相談することをおすすめします。
親の相続において兄弟姉妹に遺留分侵害額請求をすることはできる
兄弟姉妹に遺留分侵害額請求する場合の遺留分の割合
被相続人に子がいる場合、子が相続人となります(被相続人の配偶者がいる場合は、配偶者も相続人となります)。
子が複数いる場合は、兄弟姉妹で共同相続人となります。
この場合に、ある相続人に対して他の相続人の遺留分を侵害する遺贈や贈与があれば、遺留分を侵害された相続人は、遺留分を侵害する遺贈や贈与を受けた相続人に対して遺留分侵害額請求をすることができます。
例えば、被相続人の長男と二男が相続人の場合において、長男に全財産を相続させる旨の遺言がされていたとします。
その場合は、長男への遺贈が二男の遺留分を侵害しているので、二男は長男に対して遺留分侵害額請求をできます。
この場合の法定相続分は2分の1ずつ、遺留分は4分の1ずつです。
なお、長男が被相続人よりも先に死亡していて長男の子2人が長男の代襲相続人となった場合は、法定相続分が、二男が2分の1、長男の子が4分の1ずつ、遺留分が、二男が4分の1、長男の子が8分の1ずつとなります。
兄弟が共同相続人となる場合の法定相続分と遺留分について、ケースごとに表にすると、下のようになります。
| 相続人の組み合わせ | 法定相続分 | 遺留分 |
|---|---|---|
| 子2人 | 2分の1ずつ | 4分の1ずつ |
| 子3人 | 3分の1ずつ | 6分の1ずつ |
| 配偶者 子2人 |
配偶者:2分の1 子:4分の1ずつ |
配偶者:4分の1 子:8分の1ずつ |
| 配偶者 子3人 |
配偶者:2分の1 子:6分の1ずつ |
配偶者:4分の1 子:12分の1ずつ |
| 被代襲者A(子)の子2人 | 2分の1ずつ | 4分の1ずつ |
| 子A 被代襲者B(子)の子1人 |
A:2分の1 Bの子:2分の1 |
A:4分の1 Bの子:4分の1 |
| 被代襲者A(子)の子1人 被代襲者B(子)の子1人 |
Aの子:2分の1 Bの子:2分の1 |
Aの子:4分の1 Bの子:4分の1 |
| 子A 被代襲者B(子)の子2人 |
A:2分の1 Bの子:4分の1ずつ |
A:4分の1 Bの子:8分の1ずつ |
| 被代襲者A(子)の子1人 被代襲者B(子)の子2人 |
Aの子:2分の1 Bの子:4分の1ずつ |
Aの子:4分の1 Bの子:8分の1ずつ |
| 配偶者 子A 被代襲者B(子)の子2人 |
配偶者:2分の1 A:4分の1 Bの子:8分の1ずつ |
配偶者:4分の1 A:8分の1 Bの子:16分の1ずつ |
父母が離婚していた場合の兄弟姉妹の遺留分
父母が離婚していても兄弟姉妹の法定相続分や遺留分は変わりません。
例えば、父母が離婚し、長男を父が、二男を母が引き取って養育した場合、長男は父だけでなく、母の遺産を相続することができますし、二男も同様に母だけでなく父の遺産を相続することができますが、その際の法定相続分や遺留分についても、離婚していない場合と変わるところはありません。
兄弟姉妹の中に養子がいる場合の遺留分
養子縁組には、普通養子縁組と特別養子縁組があります。
普通養子縁組
普通養子は養親と実親の両方の遺産を同じように相続することができます。
特別養子縁組
特別養子は養親の遺産しか相続できません。
相続分や遺留分については、養子も実子も同じです。
つまり、兄弟姉妹の中に養子がいた場合、その養子も、実子の兄弟姉妹と同じ相続分、同じ遺留分をもちます。
なお、相続開始前に養子がなくなっている場合に、養子の子が養親の遺産を代襲相続できるかという点については、養子縁組と養子の子の出生とどちらが早いかによって結論が異なります。
養子縁組の後に養子の子が出生した場合は、代襲相続することができますが、出生後に養子縁組した場合は、代襲相続することができません。
代襲相続できる場合の法定相続分と遺留分は、実子の子が代襲相続する場合と同じです。
異母兄弟・異父兄弟がいる場合の遺留分
例えば、父と母が離婚して母に引き取れ、母が再婚し、母が再婚相手との間に子が生まれた場合、再婚した母の連れ子と、母と再婚相手との間の子の関係は、父が異なる異父兄弟姉妹です。
父は異なりますが母は同じなので、母の遺産相続については、法定相続分や遺留分は同じです。
そして、母の連れ子と母の再婚相手が養子縁組をしていない場合、母の連れ子は母の再婚相手の遺産を相続する権利はなく、当然、遺留分ももちません。
母の再婚相手が、母の連れ子を養子にしている場合は、前述のとおり、養子は養親の遺産を相続する権利をもち、実子と同様の法定相続分と遺留分をもちます。
なお、連れ子同士で、まったく血がつながっていない兄弟の場合で、かつ、どちらも自分の親の再婚相手と養子縁組をしていない場合は、同じ家で暮らしていても法律上の兄弟姉妹ではなく、親の再婚相手の遺産を相続することはできません(遺留分もありません)。
相続放棄があった場合の遺留分
ちなみに、相続放棄をした相続人がいる場合、法定相続分と遺留分の算定においては、その相続人は元々相続人でなかったものとして考えます。
つまり、子3人が相続人のケースで1人が相続放棄をした場合は、元々子2人のケースと同様に、法定相続分が2分の1ずつ、遺留分が4分の1ずつとなります。
なお、他の相続人が相続分や遺留分を放棄しても、遺留分が増えることはありません。
相続分の放棄、遺留分の放棄については、以下の記事を参考にしてください。
遺留分の計算方法

長男と二男が相続人の場合の遺留分について説明します。
例えば、財産総額が4,000万円であったところ、全財産を長男に相続させる旨の遺言がなされた場合、二男の遺留分侵害額は1,000万円(4,000万円×1/4)であり、二男は長男に対して1,000万円分の遺留分侵害額請求ができます。
減殺の方法は、原則として、遺留分侵害額請求をされた長男に委ねられ、遺留分権利者である二男は、返還される財産を選択することはでません。
例えば、減殺対象の財産に現金と不動産があった場合に、遺留分権利者の方から、現金での返還を指定したり、不動産での返還を指定することはできません。
基本的には、それぞれの財産に対して、遺留分に応じた持分を取得することになります。
例えば、遺留分が4分の1で、減殺されるべき財産が現金1,000万円と不動産であった場合は、現金250万円と不動産の4分の1の共有持分を取得することになります。
ただし、請求された人には価額弁償の抗弁権があり、上記のように現物を返還するのではなく、お金で清算することを提案することができます。
価額弁償とは?
例えば、先ほどの例で、不動産の価格が7,000万円であったとすると、現金1,000万円と併せて、遺留分算定の基礎となる財産の価額は8,000万円になり、遺留分が4分の1であれば、2,000万円を弁償することで、現物の返還に代えることができます。
価額弁償の抗弁がなされていないのに、遺留分権利者の方から価額弁償を求めることはできません。
なお、価額弁償の抗弁があったにもかかわらず、弁償されない場合は、遺留分権利者は、価額弁償の請求前であれば現物の返還を求めることができます。
一度でも価額弁償を請求したら、翻意して現物の返還を求めることはできません(請求された人が同意すれば可能)。
価額弁償の抗弁があったが弁償されないという場合に、弁償を請求するかどうか、慎重に判断しましょう。
なかなか弁償されない場合、相手方に弁償を行うだけの資力がない可能性が高いので、現物の返還を求めたほうが取りっぱぐれるリスクが比較的低いと考えられます。
とはいえ、ケースによりけりですので、このような場合は専門の士業に相談してみた方がよいでしょう。
また、請求された人は、一部の財産についてのみ価額弁償を選択することもできます。
なお、当事者同士の合意があれば、どのようなかたちで分割しても構いません。
例えば、減殺対象の不動産が複数あり、その内の一つを遺留分権利者が取得するかたちや、分割払いで支払うかたちでも、当事者の合意があれば構いません。
ただし、その場合には、当事者で合意した分割方法によって税金面で不利な取り扱いを受けないかに注意が必要です。
この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
ご希望の地域の専門家を探す