【兄弟姉妹の遺産相続】法定相続分や遺留分について解説!
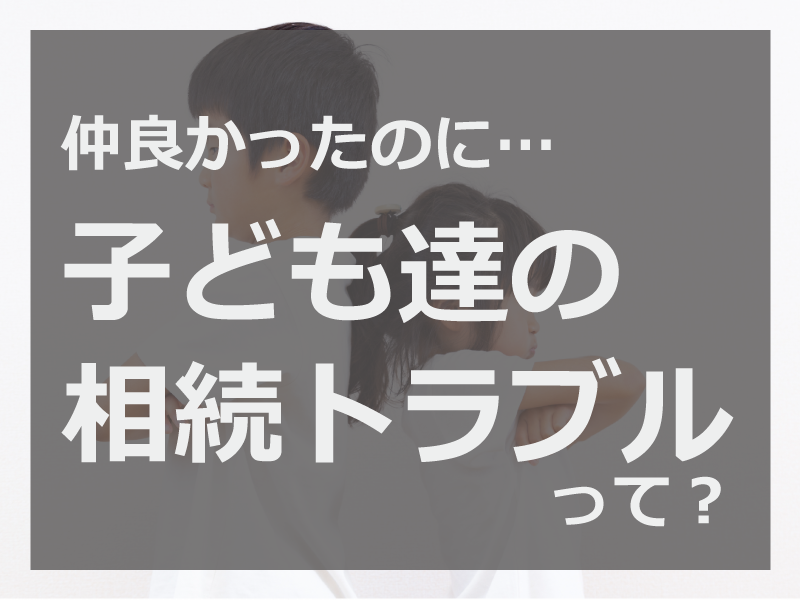
遺産「争族」と言われるぐらい、遺産を巡って親族間で争い発展することは珍しいことではありません。
中でも最も多いのは、兄弟間の相続トラブルです。仲の良かった兄弟の関係が遺産相続を境にぎくしゃくしてしまうのは、本当に切ないことです。
また、元々うまくいっていない兄弟間で遺産分割協議をまとめるのは、さらに至難の業と言ってもよいでしょう。
この記事では兄弟での遺産相続を徹底解説します。兄弟がいる人や、2人以上のお子さんをお持ちの人は是非参考にしてください。
相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください
[ご注意]
記事は、公開日(2018年11月22日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
兄弟で遺産相続する2つのパターン
兄弟で遺産相続が関係するシチュエーションには2通りあります。
一つは親の遺産を兄弟で相続するケース、もう一つは兄弟の遺産を相続するケースです。
親の遺産を兄弟で相続する
親の遺産を兄弟で相続するケースは、兄弟がいる人であれば、当然ながら誰にでも起こり得るケースです。
兄弟で共同相続人になるケース
子は第1位の法定相続人なので、親よりも先に亡くなったり、相続欠格や廃除にならない限りは、必ず法定相続人になります。
兄弟が親よりも先に亡くなっていなければ、相続人が兄弟だけというケースと、兄弟と亡くなっていない方の親が相続人というケースがあります。
先に亡くなった親の相続のときは、兄弟と亡くなっていない方の親が相続人になり、後に亡くなった親の相続のとき、父母が同時に亡くなったとき、父母が離婚していたとき等は、兄弟だけで相続人となります。
親よりも先に亡くなった兄弟がいる場合は、その兄弟の子が相続人になります(これを代襲相続と言います)。
兄弟が養子や異母兄弟、異父兄弟であっても相続人になることができます。
養子縁組をした場合
例えば、夫Aと妻Bの夫婦はCを養子に迎えて養子縁組をしたとします。その後、AとBにはDという子が生まれました。
CとDは、生物学的な兄弟ではありませんが、法律上の兄弟です。AやBが亡くなったときには、養子であるCも実子であるDと同じく相続人になります。婿養子であっても同様です。
しかし、養子縁組は夫婦の一方とのみ行うこともできます。
Cが、Aとのみ養子縁組をし、Bと養子縁組をしなかった場合は、Aの相続人にはなれますが、Bの相続になることはできません。異母兄弟、異父兄弟の場合も同様です。
異母兄弟、異父兄弟の場合
Aには前婚の子Eがいたとします。EとDは異母兄弟です。EとCは、生物学上の兄弟ではありませんが、法律上の異母兄弟です。
Aが亡くなった場合に、EはC、Dと同様に相続人になります。なお、相続に親権は関係ありません。
Eの親権をAが持っていなかったとしても、EはAの相続人になることができます。
非嫡出子の場合
EがAの非嫡出子(結婚していない男女の間の子)であっても、EがAに認知されていれば問題なく相続人となります。
EがAの非嫡出子であって、AがEを認知していない場合は、EはAの相続人にはなれません(死後認知がなされた場合には相続人になることができます)。
なお、相続するのに認知が必要なのは、非嫡出子の父についてです。
母については、被嫡出であっても、認知といった制度はなく(女性は自分が産んだ子は自分の子に決まっているので)、必ず相続人になれます。
なお、Bが亡くなった場合はBとEは親子ではないので、EはBの相続人にはなれません。
BがAの連れ子であるEのことを母親代わりとして育ててきたとしても、BとEが養子縁組しない限りは、EはBの相続人にはなれません。
BとEが養子縁組をした場合は、EはBの相続人になることができます。
兄弟で共同相続人になった場合の法定相続分
次に、相続分について説明します。
AとBが夫婦で、子がCとDだったとします。Aが亡くなった場合、B、C、Dが相続人になります。
配偶者と子の相続分は、2分の1ずつであり、子が複数いる場合は、兄弟で按分します。つまり、Bが2分の1、CとDが4分の1ずつということになります。
CとDのどちらかが非嫡出子であっても、異母兄弟であっても、養子であっても、婿養子であっても、相続人である以上は、相続分に違いはありません。
例えば、Dが婿養子D2を迎えたとすると、兄弟はC、D、D2の3人になります。そうすると、相続分は、Bの2分の1は変らず、CとDとD2が6分の1ずつになります。
それでは、CがAよりも先に亡くなっていて、Cの子EとFが代襲相続した場合はどうでしょうか?
その場合はCの相続分を代襲相続人で按分することになります。つまり、Bが2分の1、Cが4分の1、EとFが8分の1ずつ相続することになります。
遺言がある場合
遺言がない場合は、法定相続分をベースにして遺産分割協議を行うことになりますが、有効な遺言がある場合は、遺言による指定が優先されます。
例えば、「Bに全財産を相続させる」ことも、「Bに2分の1、Cに2分の1の割合で相続させる」ことも、「Bに自宅不動産を、Cにその余の財産を相続させる」ことも、法定相続人ではない「Gに全財産を遺贈する」ことも可能です(遺贈とは遺言によって財産を贈ること)。
遺留分
法定相続人でも、贈与や遺贈でほかの人のところに財産が行ってしまい、まったく財産を受け取ることができなくなってしまうことがあります。
それでは余りにかわいそうなので、法定相続人である被相続人の配偶者、子、直系尊属には遺産の一定割合の取得が保障されています。
遺留分は、例えば、子2人が相続人の場合は4分の1ずつ、子3人が相続人の場合は6分の1ずつ、配偶者と子1人が相続人の場合は4分の1ずつ、配偶者と子2人が相続人の場合は配偶者が4分の1で子が8分の1ずつです。
代襲相続が絡むケースでは、配偶者と子2人がいて、子の1人が先に亡くなっていて、その代襲者が2人いた場合は、配偶者が4分の1、生きている子が8分の1、代襲者が16分の1ずつです。
贈与や遺贈によって遺留分が侵害されている場合は、遺留分減殺請求を行うことで侵害分を取り戻すことができます。
寄与分
また、寄与分がある相続人は、法定相続分や遺言によって指定された相続分以上の割合で相続することができます。
寄与分とは、被相続人の生前に、相続人が、被相続人の財産の増加や維持に寄与した程度のことです。
親の介護を熱心にした場合、その分、介護施設への入所費用が節約できたことになります。このような人に寄与分が認められると、ほかの兄弟よりも多く財産を受け取れることになります。
特別受益
また、特別受益がある相続人は、特別受益の持戻しを受ける可能性があります。特別受益とは、相続人が複数いる場合に、一部の相続人が、被相続人からの遺贈や贈与によって特別に受けた利益のことです。
特別受益があった場合は、特別受益の価額を相続財産の価額に加えて相続分を算定し、その相続分から特別受益の価額を控除して特別受益者の相続分は算定されます。このようにして相続分を算定することを特別受益の持戻しといいます。
相続放棄
遺産は、プラスの財産ばかりとは限りません。借金等のマイナスの財産があることもあります。
プラスの財産よりもマイナスの財産の方が大きい場合は、相続人のお金で被相続人の負債を弁済しなければなりません。
しかし、相続放棄をすることによって、プラスの財産もマイナスの財産もどちらも相続しなくて済みます。
相続放棄は、相続人ごとに手続することもできますが、何人かの相続人でまとめて手続することも、相続人全員で手続きすることもできます。共通する書類が多いので、まとめて提出した方が手間が省けるでしょう。
遺産分割
具体的相続分が決まったら遺産分割協議に移ります。
遺産分割とは、亡くなった人が所有していた財産(遺産)を、その人の死亡と同時にもらい受ける権利のある人が複数いる場合に、その人たちの間で遺産を分けることです。
また、遺産分割にあたって、遺産の分け方を決めるために行う協議のことを遺産分割協議といいます。
遺産を受け取る権利がある人が1人以下しかいないか、または、遺産を受け取る権利のある人が複数いたとしても遺言によってすべての財産の処分(受取先)が決まっている場合は、遺産分割は不要ですが、後者の場合は、相続人全員の同意があれば、遺言に従わず、遺産分割協議によって財産の帰趨を決めても構いません。
また、兄弟で遺産分割協議を行う際に、最もトラブルになりやすいのは、誰も住まなくなった実家の相続についてです。
実家は思い入れのあるケースもありますし、不動産は分割がしにくいので、揉めやすいのです。
相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください
兄弟の遺産を相続するケース
次に兄弟の遺産を相続するケースについて説明します。
兄弟の法定相続人となる場合
兄弟の遺産を相続するケースは、亡くなった兄弟に子(代襲者含む)と直系尊属がいない場合です。
兄弟よりも子と直系尊属の方が相続順位が上なので、子、子の代襲者、直系尊属がいない場合のみ、兄弟間相続(兄弟の遺産を相続すること)が起こります。
亡くなった兄弟に配偶者がいる場合は、その人も相続人になります。
兄弟が相続人となる場合は亡くなった兄弟が、養子・婿養子、異母兄弟・異父兄弟、非嫡出子であっても相続人となります。
反対に生きている兄弟が、養子・婿養子、異母兄弟・異父兄弟、非嫡出子であっても相続人となります。また、兄弟の中で、今回亡くなった兄弟よりも先に亡くなった人がいる場合は、先に亡くなった兄弟の子(今回亡くなった人の甥姪)が代襲相続人になります。
甥姪も亡くなっていた場合には、再代襲はできません(甥姪の子は再代襲相続人になりません)。
兄弟の法定相続分
亡くなった兄弟に配偶者がいる場合の相続分は、配偶者が4分の3、兄弟が4分の1です。相続人となるべき兄弟が複数いる場合は、4分の1の枠を兄弟で按分します。
相続人となるべき兄弟が2人の場合は、8分の1ずつが相続分です。甥姪が代襲相続する場合は、親の相続するはずだった相続分を甥姪の人数で按分します。
父母の一方のみと養子縁組をした養子や、異母兄弟、異父兄弟の相続分は、全血の兄弟の2分の1です。有効な遺言がある場合は、遺言の指定に従います。
兄弟の遺留分
兄弟間相続の遺留分について説明します。亡くなった人の兄弟には遺留分はありません。
遺留分があるのは、配偶者のみです。配偶者の遺留分は2分の1です。
兄弟間相続の遺産分割について
寄与分や特別受益については、兄弟間の相続では、親子間の相続に比べて、寄与分や特別受益が生じているケースが少ないので、この点でのトラブルは多くありません。
もっとも、兄弟間の相続であっても、寄与分や特別受益がある場合は、主張することができます。
なお、兄弟間相続では相続人が高齢のケースが多く、またすぐに次の相続が生じて、相続税が度々かかってしまうことになりかねないので、甥姪に遺贈することが有効なケースがあります。この点については、後述します。
寄与分、特別受益、相続放棄、遺産分割に関する基本的なことについては、親の遺産を兄弟で相続するケースと変わりないので、前述の説明をご参照ください。
兄弟間相続は相続税が2割加算されるので注意
相続税額の2割加算とは、相続や遺贈などによって財産を取得した人が、亡くなった人の一親等の血族(代襲相続人を含む)と配偶者以外の人の場合には、その人の相続税額にその相続税額の2割に相当する金額が加算されるという制度です。
兄弟は二親等なので、相続税が2割加算されてしまうのです。この場合、甥姪に遺贈することで世代飛ばしによる節税が可能になります。
世代飛ばし
相続税対策の一つに、世代飛ばしという手法があります。相続では通常、一世代下の子の世代に財産が引き継がれます。
そして、次の相続で、子の世代から、孫の世代に財産が引き継がれます。そうすると、孫の世代に財産が引き継がれるまでに、2回の相続を経ることになり、2回分の相続税がかかってしまいます。
そこで、子の世代を飛ばして、遺贈や贈与によって孫の世代に直接引き継ぐことで相続税を節税しようというのが世代飛ばしです。
2割加算に話を戻すと、兄弟姉妹が相続する場合でも、甥姪に遺贈させる場合でも、このケースではどちらも2割加算が適用されます。
したがって、相続税の基礎控除額を超える資産を持っている場合は、甥姪に遺贈した方が相続税対策になる可能性があります。なお、兄弟姉妹や甥姪を養子にすると2割加算を避けることができます。
しかし、推定相続人を養子にすると、基礎控除額の算定の元となる法定相続人の数が減ってしまって、却って相続税額が増えることがあるのでご注意ください。相続税の控除額は以下の計算式で求めることができます。
しかし、基礎控除額の算定の元となる法定相続人の数に算入することができる養子の数には、法律によって一定の制限が設けられています。
実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までが限度です。
相続税の手続きは理解の難しい仕組みや制度がたくさんあります。正しく、そして不利益が出ないようにするために、ぜひ専門家に相談してみることをご検討ください。
相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください
この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
ご希望の地域の専門家を探す






























