内縁の妻・夫や愛人には相続権はない?!遺産を受け取る方法は?
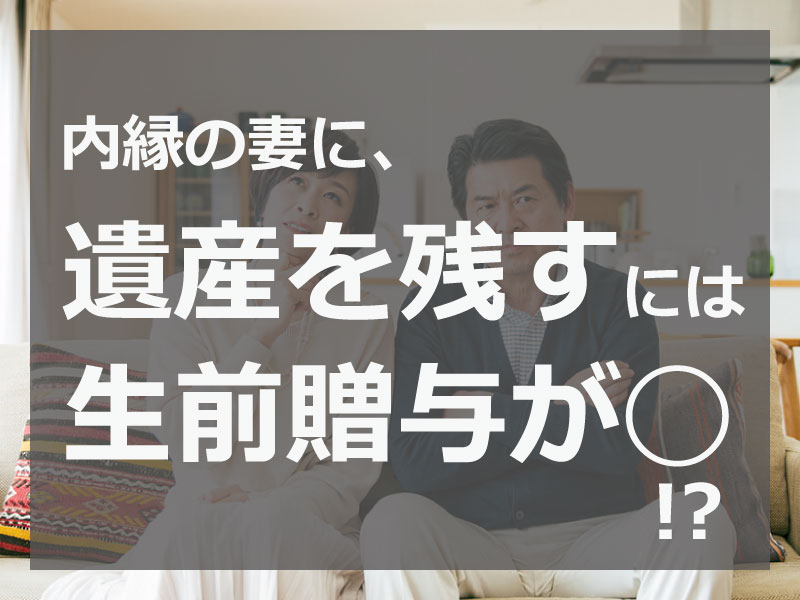
家族同然に暮らしてきた内縁の妻、愛人に遺産を残したい…との相談をよくお聞きします。その場合、遺産を受け取れるよう、生前のうちに準備することが重要です。
なぜなら内縁の妻、愛人に相続権はなく、死後に財産がもらえる可能性が低いからです。
そこで、この記事では内縁の妻、愛人が遺産を受け取る方法がいくつか紹介します。最も確実な方法は結婚することですが、遺言書や生前贈与などでも財産を残すことが可能です。
制度についての知識を十分に得たうえで、必要なら行政書士や税理士などの専門家を活用することをおすすめします。
相続手続きに必要な書類がわからない…とお考えの方などは是非、参考にしてください。
[ご注意]
記事は、公開日(2019年7月25日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
内縁関係とは
内縁関係とは、婚姻の意思があり共同生活を送っているものの、婚姻届を提出していない男女関係を言います。法律上は夫婦として認められていません。
事実婚とも言い、見た目は普通の夫婦と変わりませんが、相続などで法律上の夫婦とは異なる点があります。
内縁関係の判断基準
- 同居をしているか
- 同居の期間
- 生計を共にしているか
- 周囲(友人、知人、近所になど)に紹介して夫婦と認識されているか
- 結婚式の有無
- 認知した子どもがいるか
愛人との違い

いわゆる「愛人」と内縁の妻・夫は違います。愛人はあくまで親密な男女関係の延長にすぎず、法的に保護された関係ではありません。
そのため愛人が遺産を受け取れるか、というのは難しい問題です。長年被相続人(故人)の世話をしていたり生計を共にしていたなどの関係であれば、内縁関係として認められることもあります。
内縁の妻・夫が遺産を受け取る方法
内縁の妻・夫が財産を受け取れる方法として、以下が挙げられます。
- 亡くなる前に結婚する
- 遺贈を受ける
- 生前贈与を受ける
- 特別縁故者として財産分与を受ける
- 遺族年金をもらう
- 生命保険金の受取人にしてもらう
亡くなる前に結婚する
王道ではありますが、相手が亡くなる前に結婚すれば法律上夫婦となるため、相続人として認められます。
以前の配偶者との籍が残っている場合は、まず離婚届を出す必要があります。女性の場合は、離婚してから100日間は再婚禁止期間ですので、それも踏まえて早めに検討しましょう。
遺贈を受ける
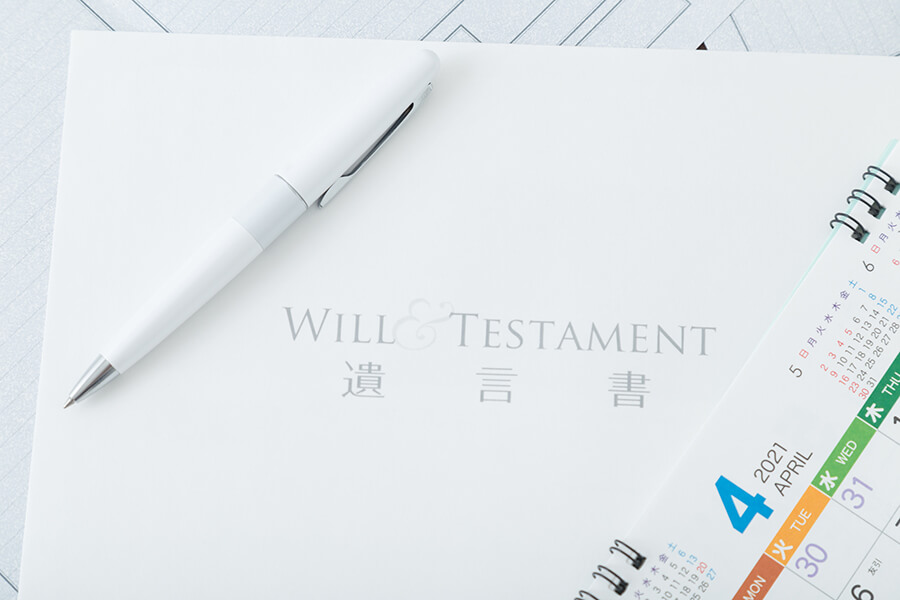
遺贈とは、遺言書によって自らの財産を無償で他人に譲り渡すことです。遺言書に「内縁の妻に◯◯(預金、不動産など)を遺贈する」などと書かれていれば、内縁関係でも財産を受け取ることができます。
さらに、遺言書は法定相続よりも優先されます。そのため遺言書にきちんと書いてもらえれば、確実に遺産をもらうことができるでしょう。
遺言書は日付を忘れたり書き方を間違えると、遺言書として認められない場合があります。詳しくは関連記事を参考にしてください。
また、遺言書の作成は、行政書士などの専門家に依頼することも可能です。
多額の相続税がかかる可能性がある
また、相続財産が相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税を納めなくてはなりません。
内縁の妻・夫は「配偶者の税額軽減」の適用を受けることができず、相続税の2割加算の対象となるため、受け取った遺産額によって、多額の相続税がかかることも。
配偶者の税額軽減とは、配偶者が「相続財産の1/2」もしくは「1億6,000万円までの相続財産」を下回れば、相続税がかからない制度です。
被相続人(故人)の一親等以外の血族(代襲相続人を含む)と配偶者以外の人が遺産を取得した場合、相続税額にさらに2割分の金額が加算される制度です。
遺留分を請求される可能性がある
遺言書があれば、内縁の妻・夫でも財産を受け取ることができますが、遺留分を侵害する遺言書については、本来の相続人から遺留分を請求される可能性があります。
遺留分とは、配偶者や子、父母などの一定の相続人が最低限受け取れる、最低保障の取り分のことです。内縁の妻・夫にはありません。
遺留分を侵害された人は、遺贈を受けた人(受遺者)に対し、財産の返還を請求することができます。これを遺留分侵害額請求と言います。
遺言書の内容より遺留分侵害額請求権が優先されます。
遺留分侵害額請求が必ずされるとは限りませんが、遺留分に配慮した遺言書にしておくと後のトラブルを回避できるでしょう。
生前贈与を受ける
相手から生前贈与を受けることによって、内縁の妻・夫でも財産を受け取ることができます。生前贈与は、相手との関係に関わらず行うことができます。
生前贈与には基礎控除があり、年間110万円以内であれば贈与税がかかりません(暦年贈与)。したがって毎年110万円ずつ20年にわたって生前贈与をすれば、合計2,200万円を税金がかからず生前贈与することができます。
しかし、税務署から「暦年贈与」ではなく「連年贈与」とみなされると、贈与税がかかるので注意してください。
連年贈与とは
複数の年に分割して行われた、ひとつの贈与を連年贈与と言います。例えば2,200万円の贈与を約束して毎年110万円ずつ贈与した場合は、暦年贈与になります。
連年贈与は、約束をした年または最初の贈与があった年にまとめて課税されます。また、そもそも贈与が有効に行われていないと判断された場合、相続時に相続税の課税対象となってしまいます。
連年贈与ではなく暦年贈与であると税務署に認めてもらうには、次のような対策が有効です。
- 贈与の都度、贈与契約書を作成する(確定日付つき)
- 受贈者が管理している口座に振り込む
- 登記や登録の制度のある財産については名義を変更する
特別縁故者として財産分与を受ける
故人に相続人がいなかったり、すべての相続人が相続放棄をした場合に、特別縁故者として家庭裁判所に財産分与の申立てを行い、それが求められれば、相続財産の全部または一部を取得することができます。
特別縁故者とは
次の要件を満たせば、特別縁故者として財産を受け取れる可能性があります。
- 被相続人に相続人(配偶者、子ども、両親、兄弟姉妹など)がおらず、かつ遺言書もないこと
- 被相続人と生計を同じくしていた者であること
- 被相続人の療養看護に努めた者であること
- 被相続人と特別の縁故があった者であること
特別縁故者として認めてもらうためには、陳述書だけでなく、医療機関の領収書などの客観的な証拠が必要です。
この申立てができるのは、相続人捜索の公示期間の満了から3か月以内です。
財産分与の申立ての流れや必要書類などは、関連記事を参考にしてください。
遺族年金をもらう
遺族年金とは、生計を維持していた人が亡くなった場合に、残された遺族が受けられる年金を言います。
遺族年金がもらえる「配偶者」は、年金法において「事実婚関係にある者を含む」とされています。したがって日本年金機構から内縁関係と生計維持関係があると認められれば、年金受給者となります。
なお、子どもがいて18歳を超えていれば、通常は遺族年金を受け取ることはできません。
公的年金を受け取れる子どもの要件は、「死亡当時、18歳になった年度の3月31日までの間にあること」もしくは「20歳未満で障害等級1級または2級の障害の状態にあること」とされています。
生命保険金の受取人にしてもらう
被相続人が加入している生命保険金の受取人を内縁の妻・夫にしていた場合です。実際に受取人を指定できるかは、保険会社や商品によって異なるので、加入する前にきちんと確認しておく必要があります。
内縁の妻・夫に相続権はない
そもそも、内縁の妻・夫に相続権はありません。遺産相続できる「配偶者」は法律上の婚姻関係がある人を言うからです。
このため婚姻届を出していない内縁の妻・夫に相続権はないのです。
ちなみに法律上の夫婦であれば、婚姻期間問わず配偶者は常に相続人となることができます。
内縁の妻・夫には寄与分、特別寄与料も認められない

寄与分、特別寄与料は相続人、親族が対象となるので、内縁の妻・夫には認められません。
寄与分とは
寄与分とは、被相続人の生前に、相続人が被相続人の財産の増加や維持に寄与した程度のことです。寄与分がある相続人は、その分多くの財産を相続することができます。
例えば何もしない兄弟姉妹に代わって父親の介護をしたり、嫁が義両親の家業を手伝うなどです。
しかし、寄与分を与えられるのは相続人だけです。内縁の妻・夫は相続人ではないので、寄与分に相当する財産を相続することはできません。
特別寄与料とは
特別寄与料とは、相続人以外の親族が、無償で被相続人の療養看護などをした場合に、相続人に対して寄与に応じた金銭(=特別寄与料)を請求できる制度です。
この制度は、相続法の改正によって2019年7月1日から導入されました。これにより、寄与分が認められなかった相続人以外の親族でも、財産を取得することができるようになりました。
ただし、内縁の妻・夫は親族ではないので、特別寄与料の請求はできません。
内縁の妻・夫に居住権はある?

一緒に暮らしてきた家が持ち家だった場合、家の所有者が亡くなったら立ち退かなくてはいけないのでしょうか?
この点については、法律上、引き続き居住する権利は保証されていません。しかし、裁判例ではそのまま住むことを認められたケースがあります。
この根拠としては、差し迫って相続人にこの建物を使用させる必要がなく、逆に、内縁の妻・夫側がこの家屋を明け渡すと家計上相当な打撃を受けるおそれがある等の事実関係のがあれば、相続人が内縁の妻・夫に対して明渡請求をすることは権利の濫用に当たるとしているからです。
相続人が内縁の妻・夫に明け渡しを求めるには、立退き料の支払いなどの配慮が必要になることも。
アパート、マンションなどの賃借権はある?
一緒に暮らしてきたアパート、マンションなどについてはどうでしょうか?
結論としては、こちらも法律上引き続き居住する権利はありません。マンションの賃借権(賃料を払って借りたものを使用できる権利)を認めた裁判例があります。
共同で家を借りたとみなされれば、内縁の夫が亡くなってもすぐに貸借権がなくなるわけではない、と考えられた場合です。
しかし、どんな場合でも認められるわけではないので、遺言書に賃借権を誰に譲るのかを明示してもらうのが良いでしょう。
内縁の妻の子どもは父の遺産を相続できる?

母が内縁関係でも愛人でも、子どもは母の遺産を相続できます。
しかし婚姻関係にない男女の子ども(非嫡出子)は、父に認知されていなければ父の遺産の相続権をもちません。父子間にDNAの一致などの生物的な親子関係があってもです。
父から認知されていれば、非嫡出子でも相続人になることができます。法定相続分(法律で定められた財産の取り分)も、配偶者との子どもと同じになります。
父が役所に認知届を提出することで認知ができます。このとき届出地は、父または子どもの本籍地、もしくは住所地の役所です。
死後認知とは
父が生きている間に認知されていなければ、死後3年以内であれば認知の訴えを提起することができます(死後認知)。
しかし、生前に認知を受けるほうが簡単かつ確実です。さらに遺言書で認知することもできるので、死後認知を当てにせず、早めに対策をしたほうが良いでしょう。
死後認知の請求方法や費用については、関連記事を参考にしてください。
この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
ご希望の地域の専門家を探す

































