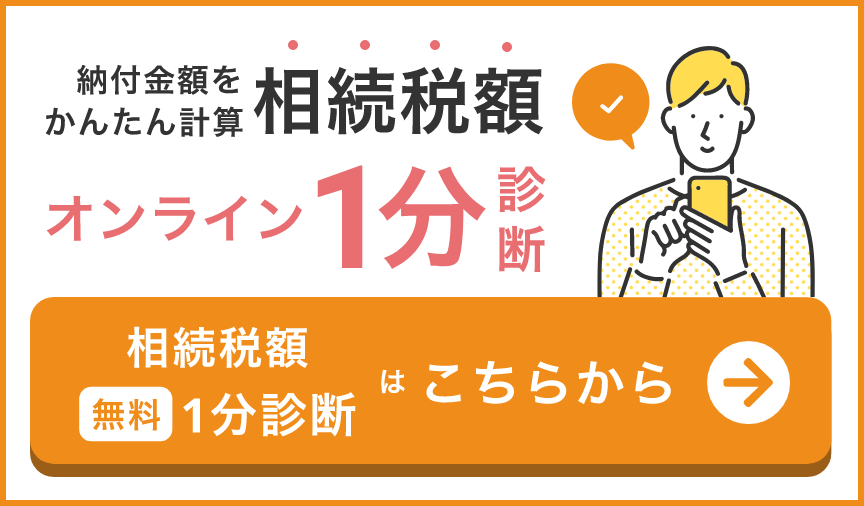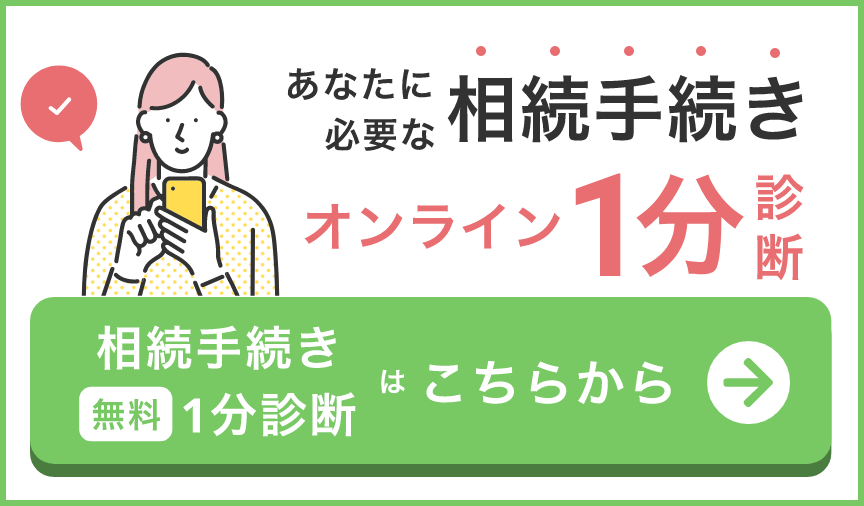相続法改正で何が変わる?いつから適用?ポイントをわかりやすく説明

[ご注意]
記事は、公開日(2018年12月12日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
相続法の改正でどう変わる?
今回の相続法の改正で変わるポイントは多岐に渡るため、次の項目ごとに分けて説明します。- 配偶者の居住権
- 遺産分割
- 遺言
- 遺留分
- 相続の効力
- 相続人以外の者の貢献
配偶者の居住権
今回の相続法の改正で、配偶者(妻や夫)の居住権がより強く保護されるように変わります。 配偶者の居住権は、次の2つに分類されます。- 配偶者短期居住権
- 配偶者居住権
遺産分割
遺産分割とは、亡くなった人が所有していた財産(遺産)を、その人の死亡と同時にもらい受ける権利のある人が複数いる場合に、その人たちの間で遺産を分けることです。- 特別受益の持戻し免除の意思表示が推定されるようになる(条件を満たした場合)
- 遺産分割前に預貯金の仮払いを受けられるようになる
- 分割前に遺産を処分した相続人の具体的相続分から利益分が差引けるようになる
特別受益の持戻し免除の意思表示が推定されるようになる
相続人が複数いる場合に、一部の相続人が、被相続人(亡くなった人)からの遺贈や贈与によって特別に受けた利益のことを特別受益と言います。 特別受益があった場合は、特別受益の価額を相続財産の価額に加えて相続分を算定し、その相続分から特別受益の価額を控除して特別受益者の相続分は算定されます。 このようにして相続分を算定することを特別受益の持戻しといいますが、被相続人が特別受益の持戻しを免除する意思を表示した場合は、持戻しは免除されます。 つまり、特別受益は持戻しがあるのが原則で、持戻し免除の意思表示があった場合は、例外として、持戻しが免除されるというのが現行法です。 この点、改正法では、婚姻期間が20年以上の夫婦の間で居住不動産(配偶者居住権を含む)が遺贈や贈与された場合は、持戻し免除の意思表示があったものと推定し、持戻しを免除しない意思表示があった場合のみ、持戻しを行うこととされました。 つまり、「婚姻期間が20年以上で夫婦間における居住不動産の遺贈または贈与」の場合は、原則と例外が逆転するというのが、今回の改正法の内容です。遺産分割前に預貯金の仮払いを受けられるようになる
相続財産の預貯金の遺産分割前の払戻しは、相続人全員の同意がない限り、原則として認められません。 しかし、今回の法改正で、相続人全員の同意がなくても、遺産分割前に預貯金の仮払いを受けることができるようになります。 その方法は、次の2つがあります。- 金融機関の窓口で直接仮払いを求める
- 家庭裁判所に仮払いを申し立てる
金融機関の窓口で直接仮払いを受ける
銀行等の金融機関の窓口で直接仮払いを求める方法のメリットには、次の2つがあります。- 裁判所での手続きが不要(手間も日数も費用もかからない)
- 仮払いが必要な理由を求められない
| 相続開始時の預貯金債権の額(預貯金残高)× 1/3 × 仮払いを求める相続人の法定相続分 |
家庭裁判所に仮払いを申し立てる
それほど緊急ではないが、遺産分割協議が長引きそうなので、遺産分割前に仮払いを受ける必要がある場合は、家庭裁判所に仮払いを申し立てることによって、預貯金債権の法定相続分の全額の仮払いを受けることも可能です。 この方法は、上限金額の縛りがないというメリットがある反面、次のようなデメリットがあります。- 家庭裁判所に遺産分割調停(または審判)を申し立てたうえで、さらに仮払いを申し立てなければならない(手間と日数と費用がかかる)
- 仮払いを受ける理由が求められる
遺産を処分した相続人の具体的相続分から利益分を差引けるようになる
現行法の下では、遺産の全部または一部が分割前に一部の共同相続人によって処分された場合、処分された財産は遺産分割の対象とならず処分で得た利益分が処分した相続人の具体的相続分から差引かれることもありません。 その点、今回の改正によって、遺産の全部または一部が分割前に一部の共同相続人によって処分された場合、処分した人以外の共同相続人全員の同意があれば、処分された遺産も遺産分割の対象とし、処分で得た利益を処分した人の具体的相続分から差引くことできるようになりました。遺言
遺言とは、亡くなった人が、主に自分の財産等について残した意思表示のことです。 例えば、「全財産を妻に相続させる」というような意思表示のことです。 遺言に関する改正点には、次の4つの点があります。- 自筆証書遺言に添付する財産目録が自書でなくてもよくなる
- 自筆証書遺言を法務局で保管することができるようになる
- 遺贈の目的物が不特定物でも相続開始時の状態で引渡せばよくなる
- 遺言執行者の権限が明確になる、復任可能になる
自筆証書遺言に添付する財産目録が自書でなくてもよくなる
自筆証書遺言とは、自筆(自書)で書かれた遺言のことです。 現行法の下では、自筆証書遺言は、全文自書しなければなりません。 特定の財産を特定の人に与える場合は、財産を特定できる項目を記載する必要があります。 例えば、預貯金であれば金融機関名や口座番号、不動産であれば登記事項(所在地、地目、地番、地積など)を記載しなければなりません。 現行法下では、これらも含めて全文を自書しなければなりません。 この点、改正法では、パソコンで作成した財産目録や預貯金通帳のコピー、登記事項証明書を添付することができるようになりました。 自書ではない別紙を添付する場合は、別紙のすべてのページに(両面ある場合は両面にそれぞれ)署名と押印が必要です。自筆証書遺言を法務局で保管することができるようになる
現行法の下では、自筆証書遺言を公的機関で保管する制度はありません。 この点、改正法では、自筆証書遺言を法務局で保管することできるようになります。 この制度の手続の流れは次のようになります。- 遺言者(代理不可)が、(遺言者の住所地・本籍地または遺言者の所有する不動産の所在地を管轄する)法務局に、法務省令で定める様式で作成した無封の遺言書を持参して申請
- 法務局で本人確認と形式審査を行い、問題なければ、遺言書を保管
- 相続開始
- 相続人や受遺者(遺言によって遺産を与えられる人)等の相続関係人が、法務局に、遺言書情報証明書の交付や、遺言書の閲覧を請求
- 遺言書が保管されていれば、法務局は、請求に応じるとともに、他の相続人や受遺者等に、遺言書を保管していることを通知
- 遺言書の検認手続は不要で、遺産の承継者は、すぐに相続手続可能
- 遺言書の紛失や破棄の心配がない
- 形式不備で無効となる心配がない
- 検認不要ですぐに相続手続に入れる
遺贈の目的物が不特定物でも相続開始時の状態で引渡せばよくなる
遺贈とは、遺言によって財産を与えることです。 不特定物とは、取引当事者が単に種類、数量、品質等に着目し、その個性を問題としていないもののことです。 「米100キログラム」などは不特定物です。 不特定物を引渡す義務を負っている場合には、一定の時点で、不特定物の中のから特定の物を引渡しの対象とすることが決まります(たとえば、米100キログラムを引渡す義務を負っているときに、実際に100キログラムの米を用意し、その他の米と分けて保管し、その旨を受取人に通知した場合には、その用意された100グラムの米が特定物として引渡しの対象となります。 遺贈の目的物が不特定物の場合、現行法の下では、遺贈義務者(遺贈を実行する義務がある人のことで、通常は法定相続人)は、受遺者に対して、瑕疵のないものを引渡す義務があります。 例えば、遺贈の目的物が米100キログラムで、遺産の米100キログラムが腐っていた場合は、現行法の下では、遺贈義務者は、遺産のお金等で米100キログラムを購入して、受遺者に引き渡さなければなりません。 この点、改正法では、遺贈の目的物が不特定物でも、特定した時の状態で引渡せばよいことになりました。遺言執行者の権限の権限が明確になる、復任可能になる
改正法では、遺言執行者の権限が明確になります。 遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために必要な手続きを行う人のことです。 現行法の下では、遺言執行者の個別の類型における権限規定はありませんが、改正法では、個別の類型における権限が規定されます。 例えば、次のような権限が規定されます。- 遺産分割方法の指定で承継する遺言がされた場合、対抗要件具備のための行為(登記申請等)ができる
- 預貯金が遺産分割方法の指定で承継された場合、 対抗要件具備(通知・承諾)、預貯金の払戻しの請求をすることができ、一定の場合には預貯金契約の解約の申入れもすることができる
遺留分
遺留分とは、一定の相続人のために、相続に際して、法律上取得することを保障されている相続財産の一定の割合のことで、被相続人の贈与や遺贈によっても奪われることのないものです。 遺留分に関する改正点には、次の4点があります。- 遺留分減殺請求の効力が金銭請求に一本化される
- 遺留分の算定において価額を算入できるのは特別受益に当たる贈与であっても相続開始前10年以内のものに制限される
- 不相当な対価による有償行為の減殺時の対価の償還が不要になる(不相当な対価によって譲渡された財産の価額からその対価が控除される)
- 相続債務弁済による控除が認められるようになる
遺留分減殺請求の効力が金銭請求に一本化される
遺留分減殺請求とは、遺留分を侵害された人が、贈与や遺贈を受けた人に対し、遺留分侵害の限度で贈与や遺贈された財産の返還を請求することです。 現行法の下では、遺留分減殺請求があった場合、贈与または遺贈された財産そのものを返還する現物返還が原則で、金銭での支払いは例外という位置づけでした。 この点、改正後は、金銭請求に一本化されます。 つまり、4000万円の不動産に対して、4分の1の遺留分減殺請求する場合、現行法の下では、4分の1の共有持分を取得することが原則でしたが、改正後は、1000万円の金銭請求に一本化されます。 また、請求を受けた人は、一定期間、支払いの猶予を受けるために、裁判所に申し立てることができるようになりました。遺留分の算定において価額を算入できるのは特別受益に当たる贈与であっても相続開始前10年以内のものに制限される
現行法では、特別受益に当たる贈与は、期間制限なく、遺留分算定においてその価額を算入します。 この点、改正後は、相続開始前10年以内という制限がつきます。不相当な対価による有償行為の減殺時の対価の償還が不要になる
不相当な対価による有償行為とは、価値が釣り合っていない取引などのことを言います。 例えば、時価1000万円の土地を100万円で譲渡するような場合です。 このような場合は、土地の買主にとって、900万円(1000万円-100万円)の贈与を受けたと同様の利益が生じ、また、その分、相続財産が減少して遺留分権利者に損害を与えているので、遺留分権利者は、この差額分の減殺を請求することができます(有償行為の当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってした場合に限ります。)。 ただし、現行法では、差額を減殺するのではなく、対価である100万円を償還して(支払って)から、有償行為の目的物の価額である1000万円について減殺します。 この点、改正後は、対価の償還が不要で、直接、差額の減殺を請求できるようになります。相続債務弁済による控除が認められるようになる
法改正によって、遺留分減殺請求を受けた受遺者や受贈者(贈与を受けた人)が、遺留分権利者の相続債務(相続された被相続人の債務)を弁済等によって消滅させていた場合は、その消滅させた限度で、遺留分減殺請求による金銭債務を消滅させることができるようになります。 つまり、遺留分減殺請求がある前に、受遺者や受贈者が相続債務を弁済していた場合、遺留分権利者の相続債務も減って、その分、遺留分権利者が得しているので、その分については、遺留分減殺請求の請求額から差し引くということです。相続の効力
相続の効力に関する改正点には、次の2つがあります。- 「相続させる」旨の遺言の場合でも対抗要件が必要になる
- 遺言執行を妨げる相続人の行為の無効は善意の第三者に主張できなくなる
「相続させる」旨の遺言の場合でも対抗要件が必要になる
事例を元に説明します。 例えば、被相続人の長男Aと長女Bの2人が相続人だったとします。 被相続人は甲土地をAに遺贈しました。 しかし、Bは法定相続分に応じた甲土地の2分の1の持分を第三者であるCに譲渡しました。 この場合、Aが甲土地の全部の持分を取得できるのか、甲土地の2分の1の持分はCが取得するのかという争いが生じます。 AとCの甲土地の2分の1の持分を巡るような関係を対抗関係と言い、対抗関係において相手方に優先して目的物を取得するための要件を対抗要件と言います。 対抗要件は、目的物の種類によって異なり、不動産の場合は登記、自動車の場合は登録、登記や登録の制度のない動産の場合は引渡です。 つまり、AとCのうち先に登記を備えた方が、甲土地の2分の1の持分を取得することができます。 現行法では、法定相続分を超えて財産を取得した人が、どのようにしてその財産を取得したか、取得方法によって、Cと対抗関係になるかどうかが異なります。 遺贈や遺産分割によって取得した場合は対抗関係になりますが、「相続させる」旨の遺言によって取得した場合は対抗関係にならず、Cが先に登記を備えたとしても、CがAに優先することがありません(「相続させる」と「遺贈する」の違いについては、関連記事を参考) この点、法改正後は、取得方法にかかわらず、対抗要件が必要になります。遺言執行を妨げる相続人の行為の無効は善意の第三者に主張できなくなる
遺言執行者が置かれている場合に、相続人が、遺産を処分する等、遺言執行を妨げる行為を行った場合、現行法では、誰に対してもその行為の無効を主張することができました。 この点、法改正後は、善意の第三者に対しては、無効を主張することができなくなります。 この場合の善意の第三者とは、財産を処分した相続人が、処分する権限を持っていないことを知らない人という意味です。相続人以外の者の貢献
寄与分(被相続人の生前に、相続人が、被相続人の財産の増加や維持に寄与した程度)がある相続人は、その分、多くの財産を相続することができますが、改正前の現行法では、寄与分は、相続人にしか認められていません。 つまり、相続人以外の人が、被相続人の財産の増加や維持に寄与しても、その人が、その分の財産を取得するための制度はありませんでした。 この点、改正法では、被相続人の相続人でない親族(特別寄与者)も、無償で療養看護などの労務提供をして被相続人の財産の維持増加に特別の寄与をした場合、相続の開始後、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できることとされました。 改正法の特別寄与者となり得る親族とは、6親等内の血族と3親等以内の姻族のことです。 血族とは血縁関係にある人のことです。 ここでいう血縁関係とは、生物学的な血縁関係ではなく、法的な血縁関係を指します。 例えば、養子と養親の間には生物学的な血縁関係はありませんが、法的な血縁関係はあるため、養子と養親の関係は血族に当たります。 また、認知されていない非嫡出子(婚外子)と実父との間には生物学的な血縁関係がありますが、法的な血縁関係はないため、認知されていない子と実父との関係は血族には当たりません(認知された場合は血族)。 そして、姻族とは、配偶者の血族と血族の配偶者のことです。 なお、次に該当する人は、改正法の特別寄与者となることはできません。- 相続人(現行法の寄与分を主張し得ます)
- 相続放棄をした人
- 相続欠格事由に該当する人
- 推定相続人の廃除を受けている人
相続法はいつから変わる?
今回の相続法改正は、2018年現在、まだ施行されていません。 施行日は、項目によって異なりますが、まとめると下表の通りです。| 改正項目 | 施行日 |
|---|---|
|
2020年7月12日までの間の政令で定める日 |
| 自筆証書遺言の方式の緩和 | 2019年1月13日 |
| 遺贈義務者の引渡義務 | 2020年4月1日 |
| 相続人以外の者の寄与 | 改正法の施行日(2019年7月12日までの間の政令で定める日)と改正人事訴訟法の施行日(2019年10月24日までの間の政令で定める日)のいずれか遅い日 |
- 預貯金の施行日後の仮払い
- 施行日後に遺言執行者となった人の通知義務
この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
ご希望の地域の専門家を探す