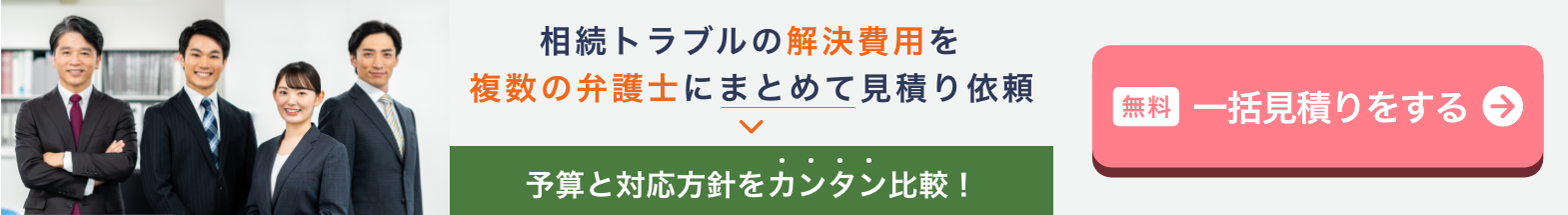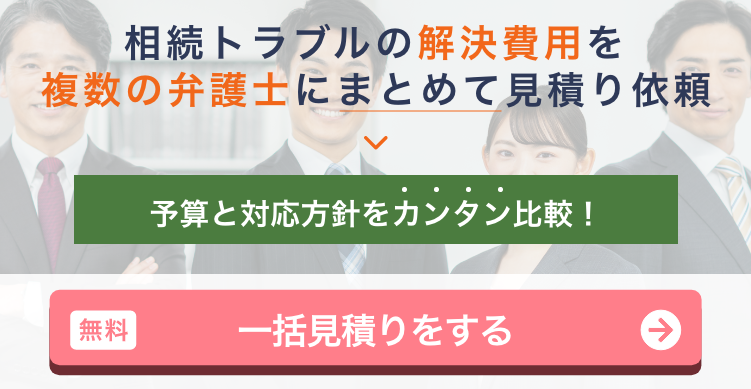相続人不存在は相続人がいないすべてのケースに当てはまる?遺産の行方は?
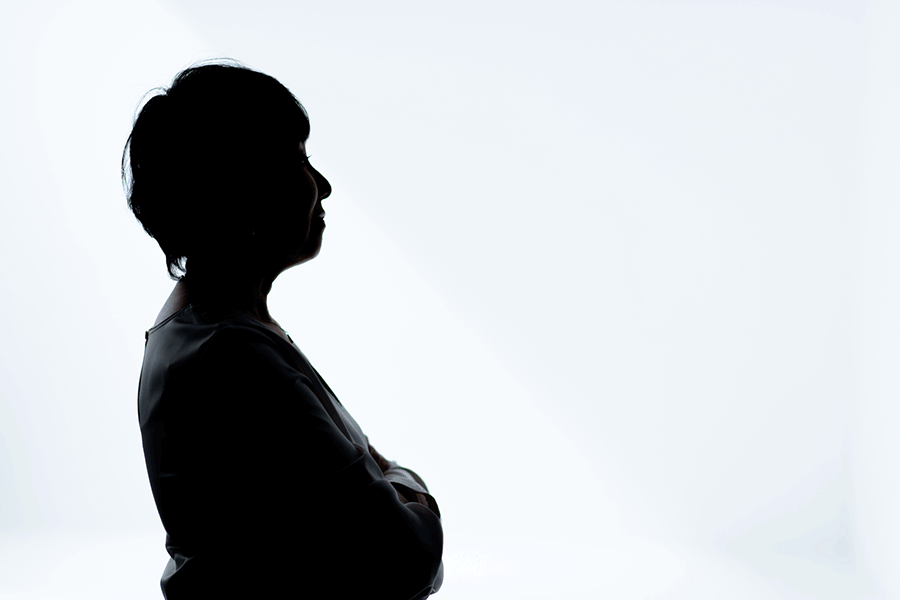
今は、ひとり世帯は決してめずらしくありません。家族に先立たれた人など理由もさまざま。そんなひとり世帯の方が亡くなり、
相続人がいない場合には、遺産はどうなるのでしょうか。
相続人はいるけれど、全員が相続を放棄や、他の理由で相続をしないとしたらどうなるのでしょうか。
相続人が行方不明の場合も相続人不存在になるのでしょうか。
この記事では、以上のような相続人不存在に関する疑問を解消することを目的としています。
是非、参考にしてください。
相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください
[ご注意]
記事は、公開日(2019年2月14日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
相続人不存在に該当するケースと該当しないケース
相続人不存在とは、文字通り、相続人が存在しないことですが、具体的に、どのようなケースが該当し、どのようなケースが該当しないか説明します。
相続人不存在に該当するケース
相続人不存在に該当するケースは、簡単に言うと、相続人が存在しないか、存在したが全員相続人ではなくなったかのどちらかです。
相続人が存在しないケース
誰が相続人になるかは、民法の規定に従って決まります。
▼法定相続人について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼
民法の規定に従って相続人となる人が存在しない(被相続人よりも先に亡くなった場合を含みます。)場合は、基本的には相続人不存在に該当します。
ただし、遺産全部の包括遺贈がされていた場合は、その包括遺贈を受けた人(包括受遺者)が遺産を承継するので、相続人不存在とはなりません。遺贈とは、遺言によって財産を無償で譲与することですが、包括遺贈とは、遺贈の対象となる財産を特定せずに包括的に承継する遺贈のことです。
例えば、「全財産を○○に遺贈する。」とか、「全財産の3分の2を○○に、3分の1を××に遺贈する。」というような遺贈が包括遺贈に当たります。
▼包括遺贈について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼
全員相続人ではなくなったケース
相続人であったものが相続人でなくなるケースとしては、相続放棄、廃除、相続欠格の3つがあります。
—相続放棄—
相続放棄とは、相続人が被相続人の権利や義務の一切の相続をしない選択をすることいい、相続放棄をした人は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
したがって、全員が相続放棄をした場合は、初めから相続人がいなかったものとみなされ、相続人不存在となります。そして、包括遺贈がされた場合も同様に、包括受遺者が遺贈を放棄すれば、相続人不存在となります。
▼相続放棄について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼
—廃除—
また、廃除とは、推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき人)が、被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱を加えたり、著しい非行があった場合に、被相続人が、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することによって、推定相続人の持っている相続権を剥奪する制度のことです。
▼廃除について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼
—相続欠格—
そして、相続欠格とは、相続に関して不正をはたらいた人などについて、その相続について相続人や受遺者となることをできなくする制度です。
▼相続欠格について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼
廃除を受けた人や相続欠格事由に該当する人は相続人ではなくなりますが、代襲相続することはできます。
—代襲相続—
代襲相続とは、相続人となるべき者(被代襲者)が、相続開始以前に死亡しているときや相続欠格または廃除により相続権を失ったときにおいて、その被代襲者の直系卑属(代襲者)が被代襲者に代わって、その受けるはずであった相続分を相続することをいいます。
▼代襲相続について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼
以上のことをまとめると、次の場合は相続人不存在に該当するということになります。
- 法定相続人がいない場合(被相続人よりも先に死亡した場合を含む)で、かつ、相続財産全部の包括受遺者もいない場合
- 法定相続人の全員が相続放棄をするか、廃除を受けるか、相続欠格事由に該当する場合(かつ、廃除を受けた人と相続欠格者に代襲相続人がいない場合)、または、包括受遺者が遺贈の放棄をした場合
相続人不存在に該当しないケース
相続人不存在に該当するのではないかという誤解されやすいが、実際は相続人不存在に該当しないというケースには、次のようなものがあります。
- 相続人が行方不明
- 相続人がいないが、遺産全部の包括受遺者がいる
包括受遺者については前述の通りなので、ここでは、行方不明のケースについて説明します。
相続人が行方不明
相続人が行方不明であっても、存在はしているので、相続人不存在には当たりません。
相続人が行方不明の場合、利害関係人は、家庭裁判所に、失踪宣告か不在者財産管理人の選任を申し立てることができます。失踪宣告が下されると、その失踪者は相続人から除外されますが、普通失踪の場合、生死不明の状態が7年間継続していなければ失踪宣告は下されません。
▼失踪宣告について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼
不在者財産管理人の選任については、不在期間が失踪宣告の要件よりも短くても認められます。概ね1年以上の不在であれば認められる傾向があるようです。
—不在者財産管理人—
不在者財産管理人は、不在者本人や債権者のために、不在者の財産を管理します。
▼不在者管理人について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼
相続人不存在の場合の手続きの流れと遺産の行方
相続人不存在の場合は、次のような流れで手続きが進みます。
- 利害関係人等が家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立てます。
- 家庭裁判所が必要があると判断したときは相続財産管理人が選任されます。
- 家庭裁判所が相続財産管理人が選任されたことを知らせるために公告を行います。
- 2か月後、相続財産管理人が相続債権者と受遺者に対して請求を申し出るべき旨を2か月以上の期間を定めて官報に公告します。
- さらに上記の公告期間経過後、家庭裁判所は、財産管理人の申立てによって、相続人を探すために、6か月以上の期間を定めて公告を行います。
- 期間満了までに相続人が現れなければ、相続人がいないことが確定します。
※通常は、申立て前に既に相続人調査を行い、相続人がいないことを確認したうえで、申立てを行っているでしょうから、この期間に相続人が現れることは、ほとんどありません。 - 特別縁故者がいる場合は、特別縁故者は、相続人を探すための公告期間満了後3か月以内に、財産分与の申立てを行います。
- 必要に応じて、相続財産管理人は、家庭裁判所の許可を得て、相続財産を換価します。
- 相続財産管理人は、債権者や受遺者への支払いをしたり、特別縁故者に相続財産を分与するための手続きを行います。
- 財産が残った場合は、残余財産を国庫に返納します。
相続財産管理人
相続財産管理人とは、相続人不存在の場合に、相続人の代わりに相続財産を管理する人のことをいいます。
▼相続財産管理人について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼
特別縁故者
また、特別縁故者とは、次のいずれかに当てはまる人のことをいいます。
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- その他被相続人と特別の縁故があった者
▼特別縁故者について詳しく知りたい方へおすすめの記事▼
相続人不存在の場合の不動産の登記
相続人不存在の場合は、前述の通り、特別縁故者が遺産を取得できる可能性があります。
特別縁故者が遺産を取得できる可能性があるのは、相続人不存在の場合のみです(特別縁故者に対する財産分与の審判が確定した場合)。
稀有なケースですが、その登記手続きについて、説明しておきます。
特別縁故者の登記手続き
この場合の登記は、相続不動産を取得する特別縁故者が所有権移転登記を単独で行うことができます。登記原因は「民法第958条の3の審判」となります。
特別縁故者が相続不動産を取得した場合の登記における必要書類は、次の2点です。
- 確定証明付審判書正本
- 特別縁故者の住民票
なお、登録免許税は、遺贈、贈与、売買の場合と同じく、固定資産税評価額の2%です。
特別縁故者の不存在の場合の登記手続き
また、特別縁故者の不存在が確定した場合は、被相続人と不動産を共有している人が、被相続人の共有持分を取得することができます。この場合の持分移転登記は、相続財産管理人との共同登記になります。登記原因は「相続人不存在確定」です。
以下の書類が必要になります。
- 登記済権利証または登記識別情報
- 相続財産管理人の印鑑登録証明書
- 共有者(持分の取得者)の住民票
- 相続財産管理人の選任審判書
相続人不存在の場合、固定資産税は誰が払う?
相続財産に不動産がある場合、その不動産にかかる固定資産税は、相続財産法人が申告・納付しなければなりません。
相続財産管理人が選任されていない場合は、納税通知が相続財産法人宛に公示送達されることもあるようです。
まとめ
以上、相続人不存在のケースについて説明しました。
相続問題でお悩みの方はまずは弁護士にご相談ください
この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
ご希望の地域の専門家を探す