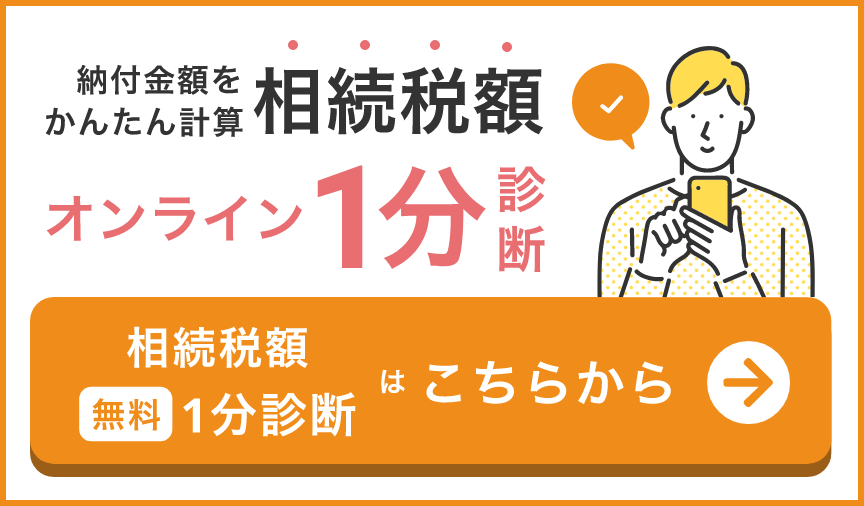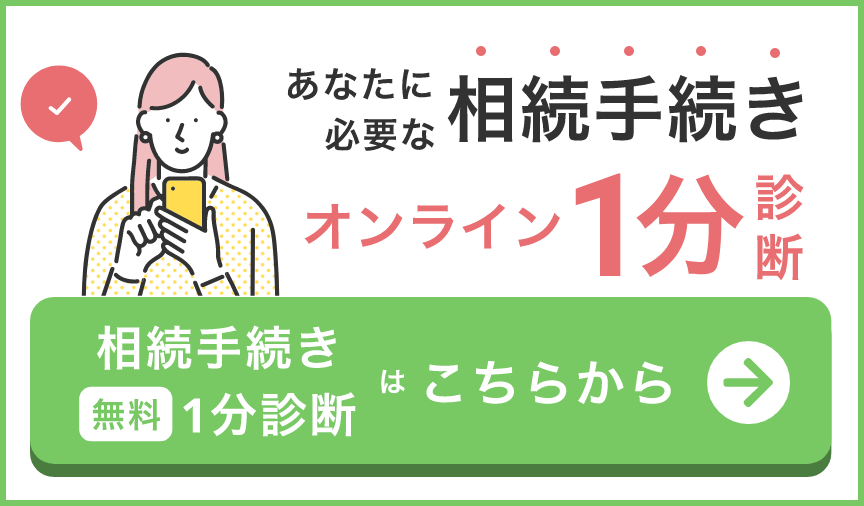【相続争い】事例から学ぶ予防と解決策

[ご注意]
記事は、公開日(2019年9月20日)時点における法令等に基づいています。
公開日以降の法令の改正等により、記事の内容が現状にそぐわなくなっている場合がございます。
法的手続等を行う際は、弁護士、税理士その他の専門家に最新の法令等について確認することをおすすめします。
相続争いのよくある事例12選
相続争いには、次のような典型事例があります。- 他の相続人から相続放棄を求められる
- 遺産を勝手に使い込まれた
- 相続開始を知らないうちに他の相続人が相続していた
- 遺言書が有効か無効かで意見が割れている
- 遺言の内容が偏っている
- 決められた相続分よりも多くの遺産を取得しようとする人がいる
- 特別受益について意見が割れている
- 寄与分について意見が割れている
- 誰がどの財産を取得するかで意見が割れている
- 不動産の分割方法で意見が割れている
- 不動産の評価額について意見が割れている
- 不動産を取得することになったが他の相続人が登記に協力してくれない
他の相続人から相続放棄を求められる
例えば、長男が、他の兄弟に対して相続を放棄するように求めることがあります。相続人である以上、相続する権利はありますから、相続放棄をするかどうかは、その人の自由です。 しかし、ひとたび相続放棄をすると、後から撤回することができません。相続放棄を求められても、すぐには応じず、どうすべきかじっくり考えた方がよいでしょう。 相続放棄の期間は、原則としては相続の開始を知った時から3か月以内ですが、家庭裁判所への申立てによって伸長することもできます。 慌てて結論を出すと後悔することになりかねないので、弁護士に相談する等して、よく考えた上で結論を出しましょう。 また、相続放棄ではなく、相続分の放棄(または相続分の譲渡)を求められることもあります。 相続分の放棄や相続分の譲渡の場合は、相続放棄のような家庭裁判所での手続きがないので、気軽に応じてしまいがちですが、ひとたび同意書に押印してしまうと基本的には撤回できないので、やはり慎重に判断するようにしましょう遺産を勝手に使い込まれた
相続人の一人が被相続人の預貯金を勝手に引き出して使い込むトラブルは比較的よく起こります。予防策
被相続人の預貯金がある金融機関は、死亡を把握すると、口座を凍結して勝手に引き出すことができないようにします。 2019年7月1日に改正民法が施行された後は、相続された預貯金の一定額に限り、生活費や葬儀費用の支払、相続債務の弁済の資金需要に対応できるよう、遺産分割前にも払戻しが受けられる制度が創設されましたが、相続人の一人が一定額以上の預貯金を勝手に引き出して使いこむトラブルは依然として起こり得るでしょう。 相続人の一人が一定額以上の預金を勝手に引き出してしまうようなおそれがある場合は、金融機関に被相続人の死亡を伝えて口座を凍結してもらうとよいでしょう。死亡の事実は誰から伝えても構いません。 伝える先は、亡くなった人が口座を開設していた金融機関の支店です。直接赴いて伝えてもよいですし、電話で伝えてもよいでしょう。 亡くなった人の氏名、住所、生年月日、口座番号等の確認があるので、スムーズに答えられるように準備しておくとよいでしょう。 複数の金融機関に口座を持っている場合は、金融機関ごとに連絡する必要があります。なお、一つの金融機関の複数の支店に口座を持っている場合は、一つの支店に連絡すれば十分です。解決策
一定額以上の預貯金が既に使い込まれた後の解決策としては、次のようなことが考えられます。なお、下記不当利得返還請求については、法律上、預貯金の引き出しが正当な権利行使として認められる場合もありますので、必ずしも全てのケースで使用できる解決策ではありませんのでご注意ください。- 口座の履歴等から使い込んだ金額を明確にして遺産分割の際に使い込み分を差し引く
- 不当利得返還請求(または不法行為に基づく損害賠償請求)をする
相続開始を知らないうちに他の相続人が相続していた
相続人が複数いる場合に相続手続きをして遺産を取得するためには、相続人全員が実印を押印した遺産分割協議書が必要になります(遺言がある場合は不要なケースもあります)。 したがって、基本的には、相続開始を知らないうちに他の相続人が相続していたということは起こらないのですが、相続人の一人が勝手に被相続人の口座から一定額以上の預貯金を引き出したり、手続きの必要がない動産を勝手に持って行ったりすることがありえます。 このような場合は、不当利得返還請求や不当行為に基づく損害賠償請求等をすることが考えられます。弁護士に相談するとよいでしょう。遺言書が有効か無効かで意見が割れている
遺言は次のような場合に無効となることがあります。- 遺言者が遺言時に認知症等で意思能力がなかった
- 自書でない箇所がある
- 日付がない
- 署名がない
- 押印がない
- 変更が所定の方式にのっとられていない
- 表現が曖昧
予防策
遺言は、遺言者である親が亡くなって初めて内容が明らかになるものですから、相続人である兄弟が取りうる予防策は特にありませんが、遺言者の取りうる予防策としては、公正証書で遺言書を作成することが考えられます。 公正証書で遺言書を作成する場合は、法務大臣に任命された法律の専門家である公証人が本人から遺言内容を聴き取って遺言書を作成してくれるので、遺言書が無効になる可能性が低くなります。 他方、自筆証書遺言の場合であっても、2020年7月10日に改正民法が施行された後は、法務局での保管制度が施行され、保管時に形式不備のチェックがあるため、この制度を利用することで自筆証書遺言でも無効になるケースは少なくなることが期待されますが、施行日までは利用できないので、公正証書遺言を利用するとよいでしょう。解決策
遺言者が亡くなった後は遺言に不備が見つかっても修正することができません。したがって、遺言を有効化するような対策はありません。 遺言が有効か無効か判断するためには、高度な専門知識が必要となりますので、弁護士に相談することをお勧めします。弁護士を交えた当事者間の協議で決着しない場合は、裁判で争われることになります。遺言の内容が偏っている
遺言の内容が、一部の人ばかりが遺産を取得できるようになっていると、不公平感からトラブルに発展しやすいです。 また、一定範囲の相続人(配偶者、子(および、その代襲者)、直系尊属)には、遺留分といって、相続できる最低限の割合が法律上決められています。 遺留分を侵害する遺贈や贈与がなされた場合は、遺留分権利者は、遺贈や贈与を受けた人に対して、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。予防策
遺言者である親による予防策としては、遺言書を作成する際に、遺留分を侵害しない内容にすることが挙げられます。 遺言書の作成について不安があるときは、行政書士などの専門家に相談すると安心です。 また、親が会社を経営している場合、後継者である子供に株式等の事業資産が集中することによって、他の兄弟の遺留分を侵害してしまうことがあります。 そこで、「将来の紛争防止のため経営承継円滑化法に基づく遺留分に関する民法の特例」を活用すると、後継者を含めた先代経営者の推定相続人全員の合意の上で、先代経営者から後継者に贈与等された非上場株式について、一定の要件を満たしていることを条件に、 ①遺留分算定基礎財産から除外(除外合意)又は ②遺留分算定基礎財産に算入する価額を合意時の時価に固定(固定合意)をすることができます。 事業承継時の遺留分対策については、専門的な内容ですので、事業承継に精通した弁護士に相談することをお勧めします。解決策
遺留分を侵害された遺留分権利者は、遺留分侵害額請求によって、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができます。決められた相続分よりも多くの遺産を取得しようとする人がいる
遺言がなく相続人が複数いる場合は、法定相続分に応じて各相続人が遺産を取得できることになっていますが、相続人の間の力関係によって、一部の相続人が多くの遺産を取得しようとすることがあります。予防策
相続人間の力関係に差がある場合に、遺産分割を相続人間の協議に委ねてしまうと、トラブルに発展しかねません。そこで予防策としては、遺言で誰がどの財産を取得するか、きっちり定めておくことが考えられます。 もっとも遺言があっても、相続人と受遺者(遺贈を受ける人)全員の合意があれば、協議によって遺言とは異なる遺産分割をすることも可能です。解決策
実際にこのようなトラブルが生じてしまった場合は、当事者間の協議で解決することは難しいことが多いので、弁護士に相談し、間に入ってもらうことを検討すべきでしょう。特別受益について意見が割れている
特別受益とは、相続人が複数いる場合に、一部の相続人が、被相続人からの遺贈や贈与によって特別に受けた利益のことです。 特別受益があった場合は、特別受益の価額を相続財産の価額に加えて相続分を算定し、その相続分から特別受益の価額を控除して特別受益者の相続分が算定されます。このようにして相続分を算定することを「特別受益の持戻し」といいます。 遺贈や死因贈与(贈与者の死亡によって効力を生ずる贈与)によって取得した財産については、基本的に、すべて特別受益に該当しますが、贈与によって取得した財産については特別受益に該当する場合としない場合があるため、その解釈を巡ってトラブルになることがあります。予防策
この予防策としては、持戻しの免除が考えられます。特別受益の持戻しの免除とは、特別受益の持戻しをさせないことです。 特別受益の持戻しがあると、贈与財産の価額が控除されますが、持戻しが免除されると、控除されません。持戻し免除の意思表示の形式に指定はありません。 ですが、遺贈による特別受益の持戻しの免除は、同じく遺言によるべきとする見解もあるので、念のため、遺言によって行うべきでしょう。 贈与による特別受益の持戻しの免除は、遺言で行う必要はありません。明示の意思表示は勿論、黙示の意思表示も認められます。ですが、黙示の意思表示は、しばしば相続人間におけるトラブルを引き起こします。 黙示の意思表示の有無で相続人同士が揉めることがあるのです。黙示の意思表示の有無については、総合的に判断されますが、次のような事情があれば、意思表示があったと認められやすいでしょう。- 受贈者(贈与を受ける人)により多くの財産を与えようという被相続人の意図がある場合
- 贈与の代わりに被相続人も利益を得ている場合
解決策
生前贈与が特別受益に当たるかどうかの判断には高度な法的知識が必要ですので、弁護士に相談することをお勧めします。寄与分について意見が割れている
寄与分とは、被相続人の生前に、相続人が、被相続人の財産の増加や維持に寄与した程度のことです。寄与分がある相続人は、その分多くの財産を相続することができます。 寄与分の有無や金額については杓子定規に決まるものではないので、寄与分を主張する相続人と、それを否定する相続人との間でトラブルになることがあります。予防策
被相続人が取りうる予防策としては、寄与分がありそうな相続人には、贈与や遺贈をして、かつ、必要に応じて特別受益の持戻し免除の意思表示をすることが考えられます。 寄与分自体を遺言で定めることはできません。 例えば、「長男○○の寄与分は○○円とする。」とか「長女○○の寄与分は相続財産の〇割とする。」というような遺言をすることはできないのです。 しかし、遺言で、相続分や遺産分割方法を指定することは、当然できます。 寄与分がありそうな相続人に対して、例えば、法定相続分が4分の1であるところ、2分の1を相続させる旨の遺言をしたり(「相続分の指定」といいます)、法定相続分が2分の1のところ、相続財産の4分の3の価値を占める不動産を相続させる旨の遺言をしたり(「遺産分割方法の指定」といいます)することは当然ながらできるのです。解決策
寄与分が認められるかどうかや、認められるとして何円分の寄与分が認められるかの判断には、高度な法的知識が必要なので、寄与分について意見が割れている場合は、弁護士に相談することをお勧めします。誰がどの財産を取得するかで意見が割れている
遺言がない場合は、法定相続分に従って遺産分割することになります。 遺産が現金や預貯金などの簡単に分けられるものだけなら問題ないのですが、現金や預貯金以外の財産について、誰がどの財産を取得するか意見が割れ、トラブルになることがあります。予防策
予防策としては、誰にどの財産を相続させるのか、主要な財産についてはすべて遺言で指定することが考えられます。また、財産に変更が生じた場合には、遺言書の書き換えを忘れないようにしなければなりません。解決策
遺言がなく、遺産分割協議で意見が割れた場合、まず、各財産を正しく評価することが重要です。 財産の評価は時価で行います。時価とは、その時に売った場合に買い手がつく値段のことです。財産が正しく評価されていないと不公平が生じてしまいます。 遺産分割協議と財産評価を同時並行で進めようとするとうまくいかないことがあります。ある財産を取得する人にとってはその財産が低く評価をされた方が得で、取得しない人は高く評価された方が得だからです。 この点、各財産の評価額を固めてから遺産分割協議に入った方が、協議がうまくいくことが多いです。また、遺産分割協議が上手くいかない場合は、遺産分割調停や遺産分割審判を申し立てる方法があります。不動産の分割方法で意見が割れている
不動産の分割方法を巡っては、遺産分割協議の中でも特にトラブルになることが多いです。 不動産は、遺産の財産価値の多くを占めることが少なくありませんし、自宅の場合は特に相続できるかどうかによって住む場所が変わってくるので生活に与える影響も大きいためです。 また、不動産の分割方法(分割しない方法も含みます)は、選択肢も豊富で、それぞれにメリットとデメリットがあるので、なかなか意見がまとまらない原因になっています。 不動産の相続について詳しくは関連記事をご覧ください。予防策
予防策としては、やはり、遺言によって分割方法を指定することが考えられますが、相続人のためになる合理的な内容にすることが重要です。解決策
当事者間で解決できない場合は、前述のとおり、調停や審判を申し立てるという方法があります。不動産の評価額について意見が割れている
前述のとおり、ある財産を取得する人にとってはその財産が低く評価をされた方が得で、取得しない人は高く評価された方が得であるため、評価額について意見が分かれることがあります。予防策
各財産の評価額を固めてから遺産分割協議に入った方が、協議がうまくいくことが多いです。解決策
不動産については、通常は実勢価格(実際に取引きされる価格)で評価されます。 不動産を売却して価額弁償を行う場合は、売却価格を評価額とすればよいのですが、売却しない場合は、どのように実勢価格を見積もるかという問題になります。 この点、固定資産税評価額や相続税評価額から実勢価格を見積もる方法が手軽です。 固定資産税評価額は実勢価格の7割程度、相続税評価額は実勢価格の8割程度になっているので、固定資産税評価額に7分の10を掛け算するか、相続税評価額に8分の10を掛け算することで、およその実勢価格を見積もることができます。 なお、土地の場合は固定資産税評価額と相続税評価額がありますが、建物の場合は固定資産税評価額しかありません。 土地の相続税評価額の算定方法についてはこちらの記事も参考にしてください。 建物の固定資産税評価額は、固定資産税の納税通知書に記載されている課税明細書の「価格」(または「評価額」)欄に記載されています。 マンションの場合は、価格欄は一棟丸ごとの評価額になっており、自分の所有している部屋の固定資産税評価額は課税標準額の欄に記載されています。 この方法で算定した評価額で双方納得できればそれでよいのですが、この方法では実勢価格との乖離が生じることもあります。 相続税評価額や固定資産税評価額から算定した評価額に納得がいかない場合は、不動産鑑定士に鑑定してもらうと、より正確な算定が期待できます。ただし、鑑定料が数十万円かかります。 また、双方が別々に鑑定を依頼すると、鑑定料も倍かかりますし、鑑定結果に開きが生じた場合に、せっかく鑑定したのに、争いが収束しないこともありえます。 合意形成のためには、鑑定を依頼する専門家を双方の合意の下で選び、鑑定結果に従うことを合意のうえで、鑑定を依頼するとよいでしょう不動産を取得することになったが他の相続人が登記に協力してくれない
取得した不動産の登記に、他の相続人の協力が必要な場合があります。 遺産分割協議によって取得した不動産の登記には、すべての相続人の実印が押された遺産分割協議書(または遺産分割協議証明書)と印鑑登録証明書が必要です。遺贈によって取得した不動産の登記には、すべての相続人または遺言執行者と不動産の取得者が共同で登記申請をしなければなりません。 以下、遺産分割協議によって不動産を取得した場合と、遺言によって不動産を取得した場合に分けて、それぞれ説明します。遺産分割協議によって不動産を取得した場合
まず、遺産分割協議によって不動産を取得した場合から説明します。 遺産分割協議書の押印に時間がかかってしまう場合に、遺産分割協議証明書にすることでスムーズに進むことがあります。 両方とも遺産分割協議で決まった内容を証明する文書ですが、各相続人が個別に証明するものが遺産分割協議証明書、すべての相続人がまとめて証明するものが遺産分割協議書であるという違いがあります。 相続人が近くに住んでいる場合は、全員が一堂に会して遺産分割協議書に署名・押印することができるので、このような場合は、遺産分割協議書が適しています。 しかし、相続人全員が集まることができない場合は、郵送等で各相続人に順次回していき、署名・押印を集めることもできます。 相続人の数が多いと、全員の署名・押印が終わるまでに日数がかかるでしょうし、途中で紛失することもあるでしょう。 この点、遺産分割協議証明書の場合は、各相続人が個別に署名・押印することができるので、遺産分割協議書の場合よりも日数が短縮できることが期待できますし、途中で紛失されて一からやり直しということもありません。 したがって、相続人の数が多く、かつ、散り散りに住んでいる場合は、遺産分割協議書よりも遺産分割協議証明書の方が便利であるといえます。 しかし、遺産分割協議証明書にも欠点があります。遺産分割協議書の場合は、各相続人がそれぞれ原本を1通ずつ持ちますが、遺産分割協議証明書の場合は、基本的には代表者しか原本を持ちません。 一人が代表してすべての相続手続きを行う場合は、遺産分割協議証明書で問題ありませんが、それぞれが相続手続きを行うのであれば、遺産分割協議書の方が便利でしょう。遺言によって不動産を取得した場合
次に、遺言によって不動産を取得した場合について説明します。 遺贈によって取得した不動産の登記は、相続人全員または遺言執行者の協力が必要です(なお、遺贈ではなく「相続させる旨の遺言(2019年7月1日改正後は、「特定財産承継遺言」と呼ばれます)」によって取得した不動産の登記は不動産の取得者が単独で申請できます)。 協力してくれない相続人がいる場合は、遺言執行者を選任することで、相続人の協力は必要なくなります。弁護士に相続争いの解決を依頼するメリット・デメリット
弁護士に依頼する最大のメリットは、弁護士の法的な知識や相手方(他の相続人等)との交渉力を活用して、依頼者にとって望ましい結果を実現させることができるという点にあると言えます。 また、相手方との交渉を弁護士が代理することによって、精神的な負担や手間を削減できることもメリットと言えるでしょう。 これに対して、弁護士に依頼するデメリットは、基本的には、費用がかかるという1点のみです。弁護士費用
弁護士費用について説明します。誰が払う?相続人全員で分担する?
そもそも、弁護士費用は誰が払うのでしょうか?結論からいうと、「弁護士費用は弁護士に依頼した人が払う」ということになります。 弁護士は、裁判所のような中立な機関ではなく、基本的には、依頼者の利益になるように業務を遂行します(法令を遵守することは当然です)。 当事者間に利害の対立がある場合、弁護士は、依頼者の利益になるように主張を組み立て、相手方と交渉するのです。 相続人全員で一人の弁護士に依頼して妥当な遺産分割方法を決めてもらうというような利用方法は、本来、予定されている弁護士の利用方法ではありませんが、このような依頼にも応じてくれる弁護士はいるでしょう。 しかし、当事者の利害が対立する中、弁護士が提案する遺産分割方法に、相続人全員が納得できないことも多いでしょう。弁護士の提案を受け入れるかどうかは、結局は、各相続人に委ねられるのです。 したがって、弁護士にこのような依頼をする場合は、弁護士の出す結論を受け入れることを予め当事者間で合意をしておくといったように、争いが終局的に解決するような工夫が必要でしょう。 なお、このような依頼をした場合に誰が弁護士費用を負担するかは、当事者である相続人で話し合って決めることになります(均等になるように負担するのが無難かと思われます)。 もっとも、このような利用方法であれば、家庭裁判所の遺産分割調停や遺産分割審判の手続きを利用する方が一般的でしょう。法律相談料
法律相談料の相場は次の表のとおりです。| 初回市民法律相談料 | 30分ごとに5,000円から1万円の範囲内の一定額 |
|---|---|
| 一般法律相談料 | 30分ごとに5,000円以上2万5,000円以下 |
着手金、報酬金
着手金や報酬金の対象となるのは、主に、利害の対立する相手方との交渉、調停、裁判等が必要な場合です。例えば、遺産分割協議や遺留分侵害額請求等が該当します。着手金
着手金は、弁護士に事件を依頼した段階で支払うもので、事件の結果に関係なく、つまり不成功に終わっても返還されません。報酬金
報酬金は、事件が成功に終わった場合、事件終了の段階で支払うものです。 成功というのは一部成功の場合も含まれ、その度合いに応じて支払いますが、まったく不成功に終わった(裁判でいえば全面敗訴)場合は支払う必要はありません。 着手金と報酬金は、経済的な利益の額に応じて変動するのが一般的で、裁判になった場合の相場は次の表のとおりです。 表中の「%」は、経済的利益の額に対する割合です。| 経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 300万円以下 | 8% ※ただし最低10万円 | 16% |
| 300万円超3,000万円以下 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
| 3,000万円超3億円以下 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
| 3億円超 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
相談前に事前準備は必要?
相談前に事前準備が必要かどうかは、相談内容によります。 まずは、電話やメール等で弁護士に問い合わせましょう。問い合わせる際には事前準備は不要です。弁護士や事務員が、必要な情報を質問して引き出してくれます。 相談時に用意した方がよい資料等がある場合は、弁護士や事務員から指示があるでしょうから、あれこれと気を揉むよりも、まずは問い合わせた方がよいでしょう。この記事を書いた人

相続専門のポータルサイト「いい相続」は、相続でお悩みの方に、全国の税理士・行政書士など相続に強い、経験豊富な専門家をお引き合わせするサービスです。
「遺産相続弁護士ガイド」では、遺産分割や相続手続に関する役立つ情報を「いい相続」編集スタッフがお届けしています。また「いい相続」では、相続に関連する有資格者の皆様に、監修のご協力をいただいています。
▶ いい相続とは
▶ 監修者紹介 | いい相続
ご希望の地域の専門家を探す